学校設立を目指した学生が、DJになって野外フェスをつくるに至った話
どうせ将来はニートにでもなるんだと思ってた
夢がない、って言ったら嘘になるかもしれないけど
なんとなくそういうことはごまして、実現しそうな未来だけ話す少年期だった。
今が楽しければそれでいい、とも思ってなかった。
ひっかかるものがある、でもそれが何かは分からず
「自分らしさ」とか「ありのまま」とかそんな言葉を多く使って
自由に生きてるぜっぽくはしたけど、結局そんな言葉こそが繭だったんだと思う。
今すぐ手が届くものより先は視界がぼやけて
手に取れることが分かる目標だけを、ただ当たり前にとっていった。
「人は死んだらどうなるのだろう」って、週刊少年ジャンプが発刊されくらいのペースで考えては
「希望も何もない人生だ」と考えるような少年期だったから、小学校の卒業文集の「あなたの20年後は?」っていう頁には無表情にバイトする自分の絵が描かれていた。
ここが地獄かなって思ってた
中学に入った部活は、テニス部だった。
友達に誘われて始めたテニス、でも気づいたら同学年は皆辞めていた。
ストレスで血尿がでたり、疲労骨折したり、皆テーピングでぐるぐる巻きにして試合にでるような
平成らしからぬ環境だった。
後輩の失態は先輩の失態というような文化があって
自分が3年になったとき、後輩は30人はいたのだけれど、とても1人ではまとめきれず
説教され続ける日々で、中間管理職の厳しさを中学生ながら痛感していた。
肉体的にも精神的にもかなりきていて、ここが地獄かなと思っていた。
本気で死を考え、自殺サイトなんかも当時流行っていたから、一番痛くないのはなにかななんて
見たこともあった。
それでも辞めないでいたのはたぶん、ちっぽけな責任感と、ここで苦しんだ分将来きっといいことがあるっていう、淡い希望だけだった。
後輩30人のマネジメントの相談なんて、だれにいってもロクな答えはでない気がしたので、だれにも相談できず、部活、友達、家族、ネット、いくつものレイヤーを使い分けていた気がする。

この感覚が大切だと思ってた
そんな時期を越えて、高校、大学を進んでいく。
淡い希望だった「人生山あり谷あり論」はそこそこに合っていて
楽しいキャンパスライフだったんだと思う。
大学ではテニスサークルに入り
周りと同じように踊るだけで十分楽しかった、そう、それは全然間違ってなくて。

ただまだそこに
アルコールでは流しきれない、なにかひっかかるものがある気がしていた。
表題である「学校」に関わってくるのはここから
テニスコーチのバイトを始めたことが転機だった。
子ども達にテニスを教えて上手くなってもらうことが、基本ミッション。
ただ、そこには親に連れてこられてやってるとか、友達と話に来るために来ているとか
そういう子どもたちも当然いるわけで、その子たちに対してテニスを上手くさせる練習をさせるのに
違和感があった。
そういう子たちに何ができるだろう、全員がプレーヤーを目指すわけではない前提で、このスポーツを通して、いま何を感じてもらうのがいいのだろうと悩み、本来の仕事と違和感との間で葛藤していた。
そこで、これまで学んでいた心理学や脳科学などのアプローチを組み合わせ
子どもたちだけで成り立つような、レッスンメニューを企画し、試していった。
基本的には最初にメニューとルールを伝えて、あとは安全監督をするだけのスタンスで見守っていた。
ただ、子ども達はそれだけでレッスンメニューを更に昇華させていき、成長していく。
その感覚に、強い納得感を持った。
例えば森は、ただ放っておくよりも、ある程度人の手を入れ、日光が当たりやすいように間伐したほうが、早く成長していく。意図的に、少しだけ手を加え、あとは放っておけば子どもたちは、自然と自分のなりたい方向に向けて成長していく、そんな事実に手応えがあった。
ちょっとした仕掛けで、いつもより人と話すようになったり
いつもより笑うようになったり、独創的なアイディアを言うようになったり
そんな空間をつくっていくことが楽しかった。
やりたいことはこれだと思った。
恐らくこれは教育という領域に属するのだろうと考え
多くのセミナーやワークショップにも顔を出すようになった。
学校をつくろうと思ってた
大学3年、進路もそろそろ考える頃、子どもたちの自由を保障していくだけで、伸びていくことを発見したとはいえ、通常の学校でそんなことはできないので、教師という選択肢はすぐに消えた。
目指したい形の1つとして、サドベリースクールというものがあり、それは時間割がなく、教師もいない、更に学費の使い道も生徒同士で決めるという、民主主義を形にしたような学校。

ただこれからの時代は専門的なスペシャリスト同士が、クラウドで繋がり仕事を生んでいく働き方が主流になるなんてことを聞き、専門的な技術を高める工夫がもう少し必要に感じた。
そこで、習い事教室の集合体としてのアフタースクールを設立できないか考えた。
子どもたちが、世界をより鮮やかな感性で感じていくために自由を保障していく第三の学校。
例えて言うなら子どもの大学のようなもの、ただそこに単位やセメスターはなく
主体性と感性、コミュニケーションに重きを置いたシステム。イエナプランに近いともいえる。
2m×2mくらいの模造紙いっぱいにマインドマップを描いて
校舎はどこにして、どうやってお金をつくってまで事細かく決めて行った。
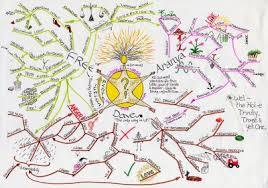
とりあえず就活してみようと思ってた
ただ資金計画をしていくうちに、まだ会社に入社したこともない学生がつくりあげていくには高すぎる壁を感じた。と、同時に違和感に気付く。
それは、学校をつくることは目的ではないということ。
そもそも、教育をするのに学校である必要はなくて、本当に自由な空間をつくりたいなら
それはカフェとか、家とか、心理的にリラックスできる場所であるべきだと考えた。
そこでファシリテーターが在中するミーティングスペース件シェアリングカフェのような場所を作って、少ない準備資金で始めようと練っていたが、気づけば周りは就活真っ只中。
まぁ確かに社会人経験は必要だし、、なんて無理矢理納得させ、流れに任せ就活を始める。アイディアは奥底にしまいながらも、企業に足を運び、某人材大手に入社してしまう。
似た経験をしたことがあると思ってた。
入社式のあとは、そのままバスで山梨の宿泊施設まで連れて行かれ、その道中「あ、これバトロワ始まるやつだ・・」と思ったことを覚えている。現場に着くと通信機器は圏外になり、カラスがうるさかったのでいよいよ感は漂ったが、なにもなかった。
これまで理論として語っていたスキルを体に身につけるのに、人材系のコミュニケーション量はいい修行の場になると考えたのが入社の理由、なのだが日々厚くなっていく右手首横あたり、マウスをずっと動かしているとたいがいこうなるらしい。
カチカチ、カチカチしているうちに気づいた
また、手が届く範囲で自分を納得させようとしていることに。
ミーティングスペースの計画も、具体性が立たないまま徐々に薄れていき
それでも、大切したいあの感覚だけは失わないようにと、公私ははっきり断絶させた。
会社の規範のなかで、当たり前に日々循環してぶつかってくるストレスに
同僚たちは次々に辞めていき、統合失調症になり入院する人もいた。
中学の時に似たような光景を見たことがある。
なにが原因なんだろうと考えた。
原因は、積み重なる仕事の結果や目的が、本来目的とするものと
ズレて感じてしまっているということかと思った。
テニスでいうなら、テニスをうまくなるために練習しているのに、顧問の機嫌をとることが
目的となっているようなそんな感じ。
更に言うと、その行動の意義を考える余裕がないということが原因だと思った。
つまり自由が、なかった。
自分の中の自由というのは、言葉を分解すると”自らに由る”つまり自らに基づくということで
自分の内部にある、価値観に基づき行動することだと考える。
英語でいうとFreeというよりRiberty。
ちょうどその時「リバ邸」という誰でも駆け込めるシェアハウスをつくったのだけど
それはまた置いておいて。
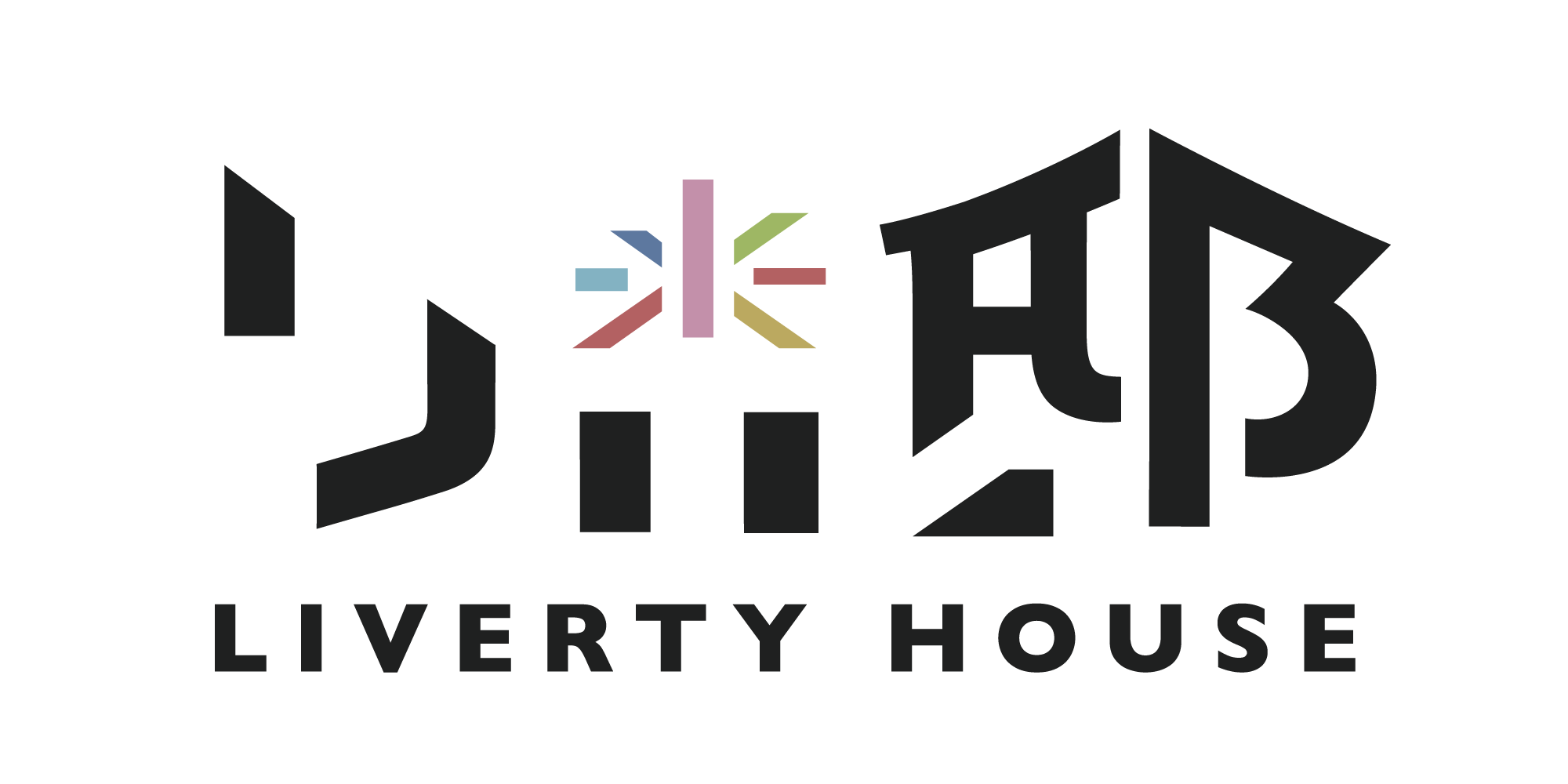
あなたの親御さんの人生を雑誌にしませんか?

著者の雨宮 優さんにメッセージを送る
著者の方だけが読めます
 LINE
LINE
