シニア向け分譲マンション「中楽坊」物語:1
今、私の手の中にあるペンダント。おばあちゃんが、いつも身についていたもの。亡くなったとき、母はこれを棺の中に入れたけど、私はどうしても欲しくて、「おばあちゃん、もらうね」と声をかけて手に入れた。
あれから10年も経つけれど、今も、命日と嬉しいことがあったときと、落ち込んだときに首にかける。そうすると、嬉しいときは「良かったね」、落ち込んでいるときには「だいじょうぶ」という声が聞こえてくる。
おばあちゃんは、ずっと私の憧れだった。
若い頃から俳句をたくさん作った。78歳のときに句集にまとめ、100部印刷して知り合いに配った。亡くなる1年前、84歳で初めて全国紙の俳句欄に掲載されたときは、「もう死んでもいいわー」と言うから、皆で大笑いした。
おばあちゃんは、その半年後に寝込んでしまうまで、毎日、料理を作った。亡くなったおじいちゃんも大好きだった豚汁や粕汁は本当に美味しく、母の作るそれとも違った。80歳の誕生日に、私が作った豚汁を食べてくれた。そういえば、その時も「こんなに美味しく作れるんだったら、おばあちゃんはもう死んでもいいなあ」と言っていた。
おばあちゃんは、おじいちゃんと一緒に田舎から出てきた。母たち4人の兄弟は巣立ち、おじいちゃんも死んで一人になった。おばあちゃんは、大きな家から小さな高齢者向けのマンションへ引っ越した。母によると、「自分のことは、何でも自分でやりたいから」だという。そういえば、いつも私が何かを手伝おうとすると、「あんたがすることじゃない」「もったいない」と言われた。
そのマンションでは、新しい友だちがたくさんできた。新しいことを一緒に楽しんでいた。俳句も昔よりいいものが出来たといって解説してくれた。大浴場が最高だと言っていた。七夕には「マンションの皆さんが、いつまでも元気で幸せでありますように」と書いた短冊を飾った。今が一番、楽しいけれど、友だちの名前を覚えるのが大変だと笑っていた。
3年前、父と母は、おばあちゃんが残してくれたマンションへ引っ越した。2人とも、おばあちゃんと同じように新しい人生を楽しめるかどうか・・・、特に父が心配だったが、スポーツ吹き矢とかいうものに夢中らしい。初心者ながら書道を始め、たまには自分で料理も作るというから驚きだ。そんな父の変わりようもあってか、母は「身軽になれたわ」と言って、嬉々として飛び回っている。そうか、おばあちゃんは私にとっては憧れだが、両親にとっては見本なのかもしれない。
私の息子は12歳になった。学校のテストで悪い点をとって落ち込んでいたとき、主人は叱ったが、私はペンダントをかけてあげた。本棚には、おばあちゃんの句集が1冊ある。息子は、最初に出てくる一句だけは覚えている。ああ、おばあちゃんは生きているんだ。
行動者ストーリー詳細へ
PR TIMES STORYトップへ
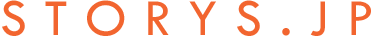
 LINE
LINE
