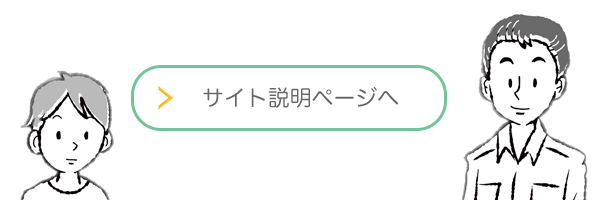理想と現実、出発点が違う。経営者を通じて見た己の立ち位置
9月某日のブックオフ。
買取の査定を待つ間に、目に留まった1冊の本がありました。
そのタイトルは『「好き嫌い」と経営』(楠木建編著、東洋経済出版社)。
何となく興味を引かれ、ページを開いてみます。
開いた先にあったのは新浪剛史ローソン取締役会長と著者の対談。
面白そうな本だという直感が働き、まえがきに飛びました。
曰く経営者の「好き嫌い」に焦点を絞った対話の記録、とのこと。
ここで査定結果が出たと呼び出され、本を元あった場所に戻します。
ですが既に直感は確信めいたものに変わっており、数分後私は再びその本を手にしていました。
今度はそれを買う為に。
実際に読み進めていくと、これが実に面白いのです。
登場するどの経営者も尖り方が半端ない。率直に思った感想です。
そのうちに気付いたことが1つ。
それはこの本を通じて、無意識に私は自分自身の立ち位置を確認していたということです。
「OSのような基本的な精神や基本原理を全員が理解していて、その上に1人ひとりが(中略)、自分の良識に従って経営者として判断する。そういう組織が一番」(ユニクロ・柳井正氏)
「モチベーションを上げるには、お互いに同じ方向を向くというのが重要」(ローソン・新浪剛史氏)
例えばこのような発言に共感している自分がいて、その背景に目を向けて。
自分が大事だと思っているところ、そうでないところの整理をしていたのでした。
昔『本を読んだら、自分を読め』(小飼弾著、朝日新聞出版)という本を読んだことがあります。
その内容はもう覚えていませんが、今回恐らく著者小飼氏が伝えようとしていたことを無意識にやっていたのでしょう。
本とはある人の世界の観え方を形にしたものに過ぎない。
それを通じて、自分というものを浮き彫りにするのが重要なのだと今は思っています。
最近参加したとある勉強会で「これから聞く話を通じて、各自の立ち位置をはっきりさせるのが大事」と、そう言われた場面がありました。
それも頭にあったのかもしれません。
***
さて、ここからはお互いに同じ方向を向くという話です。
世の中にはそれをさせる為に細かいルールがいる、と考える組織もある。
逆に言えば、そうやって管理しなければ同じ方向を向かせられない。
そう捉えている人もいるのでは?
ふとそんな考えが浮かんできました。
いわゆる性悪説的なものの見方。
人間はどうしても怠けたり楽な方に流される弱い面があるので、それを教育によって強化しようという考え方。
それ自体はとても合理的だし、その立場が否定される理由もありません。
ただ、それは自分とはまるで前提が違うお話だったのです。
私は性善説から考えを出発させている。自分ではそう思っています。
人のことを信じたいし、人の性は善なりと断言したい自分がいます。
管理はするのもされるのも嫌で、自由に価値を感じます。
一方でこれまで触れてきた現実は、多くが性悪説の論理で動いている。
そう感じてきたように思います。
とある勉強会の後の懇親会、そこで言われた「悔しさをずっと抱えてきたように観える」という言葉。
何となく心に引っかかっていました。
悔しさって何にだ、自分ではそう思っていなかったのだけど、と。
それが今回すっとつながりました。
自分の性善説的な理想と、目に映る性悪説的な現実。
「こんなはずじゃない」、その思いを悔しさと呼ぶならきっとそうなのでしょう。
こうやって整理がついて、何だかスッキリした感じになりました。
自分が進むべき道、そのパズルの1ピースを見つけた。
そう感じた瞬間でした。
著者の石黒 雄太さんに人生相談を申込む
著者の石黒 雄太さんにメッセージを送る
著者の方だけが読めます
 LINE
LINE