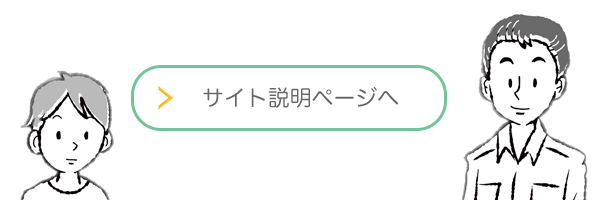自分がない!!自分をなくす!!
これを社交的な性格と呼んでよいのか?
その定義はひとまず抜きにして、基本的には誰とでも話を合わせることはできる。
ただし、あくまで「基本的」に。
無論適当に合わせるのではなく、「適度に」という繊細さは必要だ。
相手の雰囲気や話し方から、それとなく探りを入れていく。
そして差し障りのないように、傷つけないように、怒らせないように、話し方や話の内容を選別していく。
大抵の場合はこれで円滑に関係は築ける。可もなく不可もなくといったところではあるが。
しかし、こういう立ち回り方はダメというか逆効果な場合もある。
それは相手がイエスかノーの二択主義の時。
腹を探るような、時にはご機嫌を伺うようなファジーな態度は通用しない。
こちらの本性が見えていないうちはそれなりにかわいがってもらえたり、積極的に声をかけてくれたりするのだが、ある瞬間を境にスパッと嫌われるのだ(笑)
なぜか?
その適度な言葉の中に「自分がない」ことを見抜かれてしまうからだ。
相手に合わせるということは、どこかで自分を殺すことになる。
自分を殺すこと事態はそんなに苦でもないのだが、「本音はどうなんだ?」と突き付けられたらひとたまりもない。
所詮は作り物の会話だ。いとも簡単に崩れさる。
実際こういった崩落事故で途絶えた関係もいくつかあるのでこんなことを書けるわけだが。
ならばそんな姑息な手段を講じなければいい。自分らしさを前面に出して直球勝負をすればよいのだろう。
しかし…しかしだ。自分を出すことには抵抗もあるし怖さも感じる。
さらに言うならば、本当に「自分がない」から、そんな無謀なことはできないというのが本音。
おそらく幼少期から培ってきた処世術が、今の「自分がない」自分を形成してしまったのだろう。
一人っ子という立場は競争心が起きにくい。日々の生活の中で競争する必要がないからだ。
食事一つ、おもちゃ一つにしても兄弟姉妹と取り合うということはない。
目の前にあるものはすべて自分のものだ。
やがて幼稚園であれ小学校であれ、共同生活する場に身を置くことになる。
そこで幼いながらも考えていたことは
「自分がどう立ち回れば誰とでも分け隔てなく仲良くできるのか」
誰とも競争なんかしたくない(したことがない)から、必然的に嫌われない人になろうとする。長いものに巻かれようとする。
これとは逆に、典型的な一人っ子の「わがまま言い放題」になるケースもあるのだろうが、わがままを言うことがどういう結論を導き出すのかは薄々理解していたので、そちらの選択肢は選ぶことはなかった。
幼い頃の自分はどれだけ子供らしさの欠片もないガキだったのか。
でも周りの友達や大人はそんなことは気づかない。
「おとなしい子」「聞き分けのいい子」「手のかからない子」
そんな風に理解されていた…はずだ。
自身もそれでいいと思っていた。事なかれ主義の信条が着実に形成されはじめたのもこの頃だろう。
だから小学生の時に一度親友と大げんか(事の詳細は「心友 【その八・理由なき喧嘩】」をお読みいただければ幸いです)したことと、高校の時に友人の身勝手な発言(自分にではなく第三者に向けてなのだが)についキレてしまい、胸ぐらをつかんでロッカーに押しつけたことを除けば、例え怒りの感情が湧いたところで行動に移すことはしなかった。
「やらなくてもいいことなら、やらない。やらなければいけないことは手短に。」
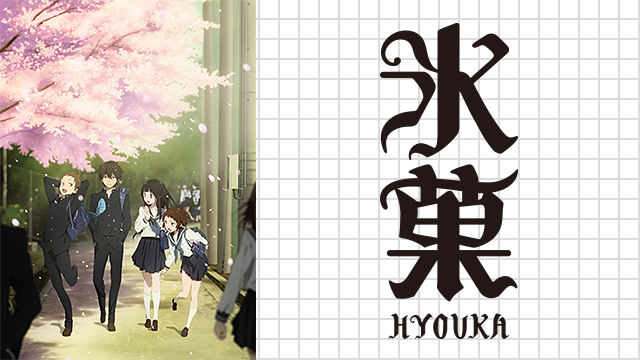
作家・米澤穂信さんの作品「氷菓」シリーズに登場する主人公。折木奉太郎の座右の銘だ。
私にとって怒りを表現することは「やらなくてもいいこと」に入る。
怒ることは正直疲れる。いかに怒らないようにするか。それを考える方がよほど気楽だったりする。
これは言い換えれば「自分をなくす」作業だ。
主観的に見るから感情に火がついてしまうわけで、第三者の視点に立って眺めれば案外大した問題ではないことも実際ある。
結果、怒っていることそのものがバカバカしくなったりするのだ。
実際にこんな形で自分をなくそうとする人は稀かもしれない。人は感情の動物。喜怒哀楽があって当たり前なのだから。
自分がないのに自分をなくすという効率的なのか非効率なのかわからない生き方。
と、収拾のつかないようなどうでもいいことを考える自分が案外好きだったりする。
著者の山口 寛之さんに人生相談を申込む
著者の山口 寛之さんにメッセージを送る
著者の方だけが読めます
 LINE
LINE