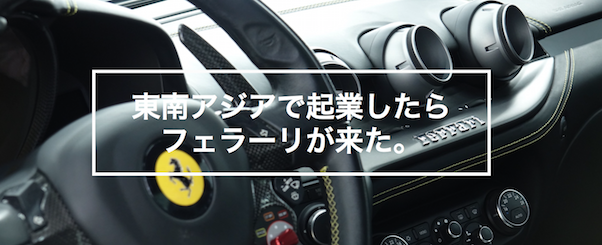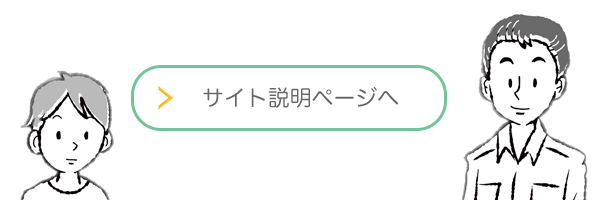震災後にボランティアをするため退職。その後被災地支援を継続しようと起業したストーリー。の前に自己紹介
これまで私は、3.11東日本大震災の被災地である岩手県大槌町に住所を移し1年半ほど瓦礫撤去、対人支援活動をしてきました。活動内容は多岐にわたるのですが、主な内容は被災者からの24時間電話相談対応、仮設住宅・在宅避難者・みなし仮設世帯の各戸訪問。物資配布、病院送迎、各支援機関とのつなぎでした。仮設や在宅など、訪問回数にすると延べ回数で1万8000回ほど。

東北入りしたのは震災の発生した2011年の7月1日。当時25歳。現地入りをキッカケに全国へ情報発信をするためブログ(アメブロ)や、facebook、twitterを始めました。
私は昨年1月に沖縄に住居を移し、有志とともに被災地支援ネットワーク『東北・沖縄つながる会議』を立ち上げ、また同年7月には起業をしました。自動車部品輸入販売、建設機械買取&輸出を主たる事業としています。
仕事を辞め被災地へ行った理由や被災地で見たものというのはあとで書きますが、被災地では多くの事を学ばせていただいたのですが、その中のひとつに活動資金がありました。私もそうでしたが、自己責任と呼ばれる災害ボランティアは多くのかたが手弁当で活動をされていました。そのため、被災地では「必要とされる活動」を守るために試行錯誤をしています。助成金、補助金、寄付金を募る、スポンサーを募る、別で仕事に就くなど。そのようにしながら被災者支援活動を維持しているといった状況です。
高齢者の見守り、仮設住宅の訪問、在宅被災者の把握、病院送迎、支援機関へのつなぎ。私が続けていたこの活動を維持するために、『社会的起業』のことを学びました。
被災地での活動が終われば、セミナーに参加し収益事業の確立を目指す毎日。



東北に災害ボランティアに来たはずが「必要とされる活動」を維持するために収益事業を模索する毎日。震災発生から2年以上。見守り活動等が必要でなければ、引けば良いのです。しかし、現場は違いました。必要とされる活動がありました。
昨年の1月に沖縄へ戻り、自動車部品の輸入販売を行うため台湾へ行きました。
被災地で学んだ社会的起業。
利益を独占するのではなく社会へと還元する。
利益をもとに、社会課題の解決に起業が挑む。
被災地支援もそうですが、困窮者支援のなかで資金確保が難しいのは痛感しました。
一般社会のなかでサービスに対する対価を得ることはできます。しかし、困窮者、災害の発生した地でサービス(ここではボランティア活動からの移行)に対する対価を受け取るのは難しく、助成金頼みの活動になってしまいます。それでは資金集めに必死で本来必要とされる活動に重きを置けません。
そこで私にできる事として、収益が見込める事業を確立するべきではないかと考えるようになりました。事業内容は自動車部品輸入販売。建設機械の買取、輸出。被災地支援とは無縁とさえ思える事業内容です。しかし、被災地での活動中に多くの外国人(スペシャリスト)と出会うことができました。台湾、中国、アフリカ、ヨーロッパ、アメリカ等で自動車アフターパーツを製造している企業との出会い。さらに中東のドバイ、パレスチナのバイヤーとの出会い。私自身、東京では自動車チューニングカーマガジンの編集部に在籍していましたこともあり、この道だと感じました。
自動車関連の会社ですが、その利益を社会に還元する。これも立派な社会的企業です。ただ、利益を寄付するだけではなく「必要とされる活動」被災地支援団体等を運営することを目的とし起業しました。現場での活動のため、現地に残られているかたがたがいます。みなさん、関東やその他の地域で勤めていたなか活動のため退職し、現地で家を借り、手弁当で活動を続けています。
震災から3年が経過しようとしていますが、被災者全員の復興住宅入居が終了するのもまだ数年先です。
まずはその時まで活動を継続するためにも、私にできることは被災地を離れ収益性のある事業を確立することだと気づかされました。この先支援する側もろとも共倒れとならないよう、私にできる事として努力していきたいと思います。そして社会的企業のビジネスモデル、企業市民のあり方を被災地から発信したいと思います。

著者のTKD Cさんに人生相談を申込む
著者のTKD Cさんにメッセージを送る
著者の方だけが読めます
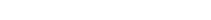

 LINE
LINE