「予備校生活はもう慣れたかい?」
「はい、何とか、やってます」
東川はアイスコーヒーのグラスを傾けながら、小さくうなづいた。
「そう、それは良かった。初めての一人暮らしは大変だものね」
「はい、まあ]

外は雨だった。梅雨明けはまだ遠いようだった。
東川は、雨の匂いが地元のものとは違うことに気がついていた。そんな違いを知ることが、故郷を思い出すってことなのかなと思う。まだ家をでてから数ヶ月だから、実感はないのだが。
「東川君は、その、何か大人になってやりたいことはあるのかい?」
「ひがし、でいいですよ。職業のことですか」
「そうだね。夢っていうか、叶えたいことっていうか」
「まあ、一応学校の先生になろうと思ってます」
「そうなんだ。先生って立派な仕事だよ」
「いえ、そんな夢っていうほどのことじゃ、ないです」
東川は雨空をぼんやり見つめていた。
特にほかになりたいものもないし、なれるとも思えない。目の前にいつも先生っていう存在がいて、何とか自分もやれそうだったから、そうだと思っているだけ。夢なんてかっこいいものじゃない。
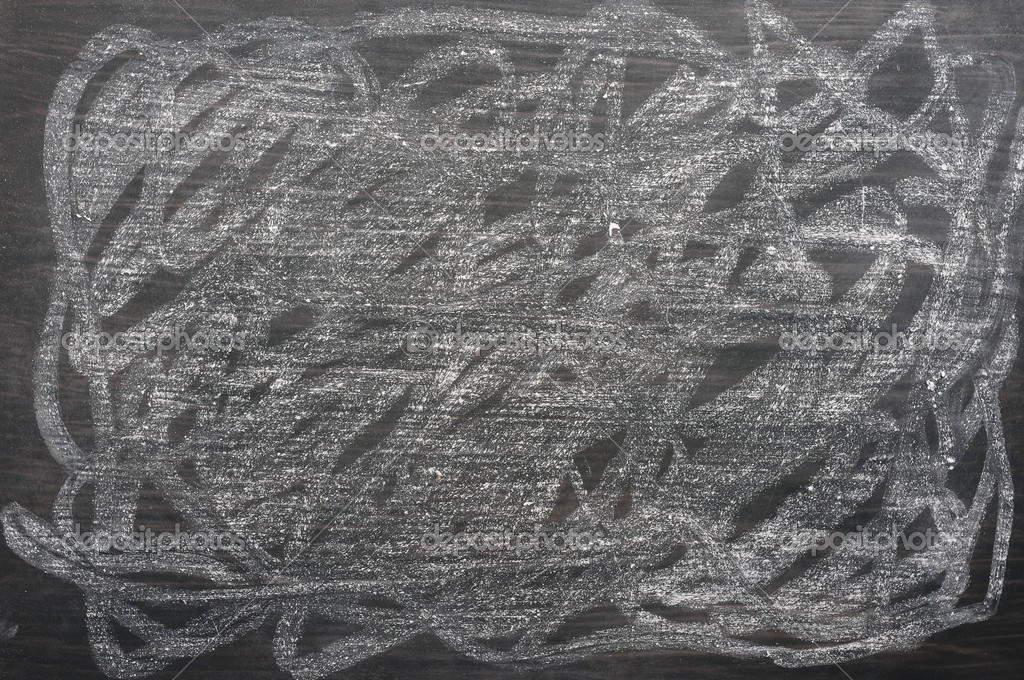
雨音が波のように近づいては去っていった。
自分には、自信もないし、意欲もない。
でも、やらないこといけないことはどんどん増えていく。難しくなっていく。
予備校に慣れたことは本当だけど、正直うまくやっているかどうかわからない。何とか課題をこなしているだけで、学力が伸びている実感はなかった。このままでは、また同じことになってしまうかもしれない。
自然と肩が落ちた。
「そんなにうまくはいかないです」
「まだ、予備校生活もこれからじゃない。東君なら、大丈夫だよ」
この人は、まだ会ってから数回なのに、何で大丈夫なんて簡単にいうんだろ、と東川は思った。でも、不思議な説得力があるのだけど。

「失礼。君は予備校生なの?」
北本が横から口を挟んだ。
「え、あ、そうです」
「何だ、北さん、黙ってると思ったら、話聞いてたの」
「いや、ごめんね。別に詮索するつもりはないんだ。ただ、懐かしくてさ。いや、俺もね、予備校生だったんだよ」
「そうなの」
「そう。いやー、あのときは楽しかったな」
楽しい?
「授業も自分で選べるし、学生もいろんなやつがいてさ。そいつらと夜遅くまで結構ばかしてたなーって」
「へー、北さんってもっと真面目なタイプだと思ってたけど、そんな頃もあったんだね」
「いや、勉強だって、まあ、そこそこやってたよ。予備校はさ、何かあそこでしか味わえない雰囲気があって、それが俺とあってたんだよなぁ。彼女もできたしさ」
「カノジョ?ますます真面目なのか、怪しくなってきたね」
「はは、でもさ、俺はその彼女に何より大切なことを学んだんだぜ」
「ほー、どんな楽しいことを勉強されてたのやら」

白々しそうに返す中さんに、北本はトーンを大げさに下げて話し続けた。
「中さん、これは真面目な話さ。彼女は俺と同じ予備校生で、引越しして一人暮らししてた。俺と彼女は、予備校の近くの河川敷で、よく話したんだ。これまでのことや、将来のことをね。
俺はそれまでそんな自分のことを人に話したことはほとんどなかったよ。彼女が、そういう話が好きだったし、俺のことを知りたがったんだ。最初は苦労した。自分のことを話すって案外難しいものだなって思った」
東川は話を聞きながら高校生のころの少しの間付き合った彼女を思い出していた。何も話せることがなくて、どちらからともなく別れた。女の子とただ話すのは難しい。

「でも、俺も段々自分のことを話せるようになってきたんだ。そうしたら、彼女の俺の話の反応をみるのが楽しみになってきた。彼女は話を聞くのがうまくてさ、何でも自然に話してしまうんだ。で、何か俺の中で自分がまとまってきたんだ」
「まとまってきた?」
「そう。俺がいまどんな俺で、どんな俺でいたいか。これから、どうしていくか。そんなことが、言葉にできるくらいはっきりしてきた。」
「彼女を本気で好きになったってことなの?」
中さんは微笑みながら聞いた。
「中さん、茶化すのはそれぐらいでね。
そのときは驚いた。そらさ、俺も大学合格しなきゃってプレッシャーは人並みにあったさ。でも、そういう不安なところとは別にさ、何か落ち着けるところっていうか、平静でいられるところが見つかったのさ。
何ていうか、俺はこういう自分を信じてるんだなって確かめられたし、頼りにできたのさ。とにかく、人に自分のことを話すって大事だって思った、とっても真面目な話だよ。
東君だっけ。予備校は大変なこともあるけど、面白いこともたくさんあるよ。まあ、勉強もそんなに気張らずに、いろいろと楽しめばいいさ」
「まあ、北さんと違って東君は真面目だから大丈夫だと思うけど」
「中さん、俺は真面目なんだって。案外、結構、さ」
北本がニヤリとする。

「あの、自分が信じられる自分なんてあるんでしょうか」
「あるよ。俺だってあったんだからさ。予備校に行って、彼女にも会った。それからも、いろいろとあった。そうしてさ、どんな大変なときでも、どうにもできなくても、幸せでいられるって俺は信じてるの。
大人になっても大変なことはあるよ。でも、そこで出会いがあったり、わかることがある。すぐはわからなくても、時間が教えてくれる。
夢や希望もいいし、何かやりたければやってみたらいい。ただ、どんなときでもいつも自分は俺の傍にいる。生まれてから最後まで続いていくんだろうな」
「お子さん、まだお腹の中だっけ」
「そうだよ、中さん。そろそろお腹が大きくなってきて、俺は家事に仕事に大わらわだよ。あと、さっきの話、奥さんには内緒だよ、真面目なはなしさ」
「なに、予備校の彼女が今の奥さんっていうオチじゃないのか。大変だなぁ」
北本さんが、またニヤリとして、中さんのお腹が揺れる。
東川は首を少し傾ける。正直よくわからない。自分を信じるなんて、僕にもできるんだろうか。
でも、北さんという人の話は何か響いた。
何ができるかできないかじゃなくて、何かを大切にしていけばいいんだ、そう思うとホッとした。その何かをこれから探していけばいいのか、いや、北さんの話だと、それはもう持っているものらしい。それが見つかればいいなと彼は思った。

