ぴったし黄身がまん中になっている目玉焼き
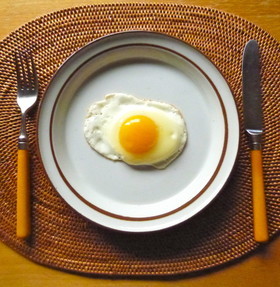
首が右に回らず、右腕が痺れる。無理に動かそうとすると首、肩、腕と体の右側に沿ってズキリと鈍い痛みが走る。
内科医へ行くと、
「微熱が出ています。扁桃腺の腫れからくる微熱です。」
「扁桃腺ですか?」
点滴を打ち、扁桃腺の薬を処方された。
整形外科医を訪ねる。上半身の触診をし、右腕から肩のレントゲン写真を数枚撮る。
「腰が張っています。痛みはありませんか?」
「いいえ。腰は何ともありません。」
「腕も肩も骨には異常ありませんから。」
アルファビームという赤外線治療器で腰を暖めた。
内科医も整形外科医も腕の痺れを治せないと嘆くと、妻が整体整骨医の名刺をもってきた。
「教えてあげよかな。骨盤を矯正するのに通った女医さん。」
細身の女医だった。
仰向けに寝た僕の襟筋をまっすぐになぞり、
「肩が両方とも内側に食い込んで固まっています。たとえば、右腕の付け根のここを押すと。」
「痛っ。」
細い指のどこに力があるのだろうかと思うほど強烈に痛い。一押し毎に汗を吹く。筋肉がギリギリと鳴っているように感じる。思わず体をねじって逃れようとするが、女医は細い指を僕の腕の付け根から離さず容赦なく締め上げる。
「肩をずっと内側に向けた姿勢をしていると、腕の付け根に負担がかかります。体が固まっていますね。」
翌朝、小学校に入学したばかりの長女に揺すぶられ起こされた。長女はうきうきとした顔をして、
「おとうさん。おとうさんが子供のときってどんなの?」
扁桃腺が腫れて声が出ない。しゃべるのがとても億劫になるが、こんなときに限って長女が饒舌になる。
「おとうさんは、どんなのやった?」
「どんなのって、どういうこと?」
僕はガラガラ声で問いかける。
「たとえば、料理をつくった?」
「あんまりできんかったな。」
「そうやろ。きっとそう。」
長女は勝ち誇ったように、
「今度、お誕生日のとき、つくってあげるで。」
「何をつくってくれるの?」
「できるようになったんやよ。」
「すごいな。何ができるようになったの?」
「それはな、お誕生日になったらな。」
「でも、ずっと先やよ。今は春やけど、おとうさんの誕生日は秋やで、きっと忘れてしまうと思う。」
「それはそうやな。そしたら、教えてあげよかな。」
長女は、妻の口調を自然とまねるようになっている。
「それはな」
たっぷりと間をとって、
「ぴったし、黄身がまん中になっている、目玉焼き」
思わず頬笑むと咽喉の奥がずきりとした。
「ぴったし、黄身がな、まん中になっている目玉焼きができるんやよ。すごいやろ」
体中が心地よく弛緩していく。
まどろむような日曜日の朝は、こうして過ぎていく。
著者の松本 晃一さんに人生相談を申込む
著者の松本 晃一さんにメッセージを送る
著者の方だけが読めます
 LINE
LINE
