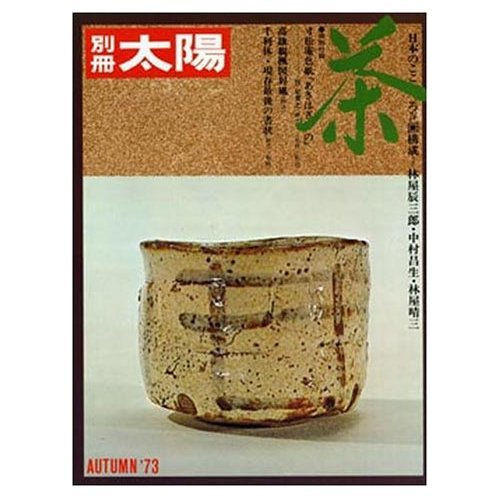出版界の異端児
「別冊太陽」は、出版界にあって異端の存在だった。
通常の雑誌では、「別冊」というのは通常号の補完的存在として発行され、雑誌コードは本誌に準じてつけられる。
そして発刊の条件も決まっていて、月刊誌なら月に1回以内、季刊誌なら年4回以内。
つまり、本誌の発行数を上回る別冊は出せないのだ。「臨時増刊」という名称も世の中にはあるが、実態は別冊である。
しかし「別冊太陽」は、月刊「太陽」とは別の雑誌コードをもっていた。すなわち出版流通上は、別の雑誌ということになる。
おまけに雑誌としては極めて異例なことに、普通の書籍と同様に増刷をした。それも1度や2度ではなく、創刊号の「百人一首」などは三十数回の増刷、改版をしている。その結果、累計部数は百万部を超えた。
今ではこのスタイルの雑誌は「ムック」と呼ばれ、書籍とも雑誌とも異なる「ムックコード」がつけられているから、流通で混乱することはない。しかし当時は取次、書店を巻き込んで、大騒ぎになった。
創刊編集長の馬場一郎氏が出版営業の実力者でなかったら、とても実現しなかっただろう。
なぜ騒動になるのかというと、出版界の問屋である取次店(日販、トーハンなど)は、どこも雑誌部門と書籍部門に分かれていて、流通も別だ。雑誌は新刊書しか存在しないのに対して、書籍は新刊委託のほかに、増刷再搬入の商品や注文品があるためだ。ところが雑誌ルートを流れる「別冊太陽」が「増刷をする」というので、雑誌部門がパニックになったわけだ。
たった1誌のために、流通システムを改変する必要が生じたのである。
普通の雑誌は、発行部数の35〜50%に卸価格を乗じた金額が適正原価といわれる。
広告収入が大きく見込める雑誌はその限りではないが、そのくらいに原価を抑えておかないと、返品がたくさんあったときに赤字になるからだ。
しかし増刷前提の雑誌は、もっと原価率が高くてもいい。そのため「別冊太陽」はカラー96ページ、モノクロ96ページに折り込み付録1点、貼り込み付録1点、綴じ込み付録1点という豪華仕様にすることができた。
付録というのは、和紙風の「新鳥の子」という印刷用紙に原寸大でカラー印刷された、さまざまな「お宝」である。国宝、重文クラスの紙に描かれた古美術を大判カメラで複写したものだ。軸装、額装すれば、床の間のコレクションにもなる。これもまた人気を呼んだ。
ぼくが配属されてすぐ、編集長が説明してくれた「別冊太陽」の特徴は以上のようなものだった。
「たった3人で、太陽本誌を上回る利益を稼いでいるんだぞ。お前も真剣にやれよ」
編集長はそう言ってくれたが、翌日にはもうお説教が待っていた。