日本酒ブランドと種麹メーカーがタッグ。産業課題の解決とお客様の体験価値向上を目指した、オリジナル種麹の共同開発ストーリー
近年の健康への意識の高まりや嗜好の広がりから、料理に塩麹や醤油麹を使ったり、米麹から味噌を自宅で仕込んだりと、一般消費者の方にも麹の存在が少しずつ身近になってきました。麹は日本酒や味噌、醤油、酢、みりんなどの発酵食品に欠かせない原料であり、麹のもととなる麹菌は2006年に日本醸造学会にて「国菌」認定されるほど、日本にとって重要な菌です。
しかし、麹菌を扱うメーカーの統廃合が進むなど、産業課題も抱えています。
課題を解決し麹文化をさらに発展させるため、そして原料に徹底的にこだわり高い品質を追求するために、日本酒ブランド「SAKE HUNDRED(サケハンドレッド)」と種麹メーカー・株式会社糀屋三左衛門が実験や研究を重ね、オリジナルの種麹「SH-NB-02」「SH-HG-02」を開発しました。
SAKE HUNDREDのブランドオーナー 生駒 龍史と、株式会社糀屋三左衛門 代表取締役 村井 裕一郎氏が、この度の種麹開発におけるねらいと開発背景について対談しました。世に語られることの少ない種麹の話。本ストーリーでは、開発の難しさや品質の特性、そして地球規模で期待される可能性についてお伝えします。

日本酒の製造工程「種切り」。種麹を使い蒸米に麹菌をふりかけて米麹をつくる。
種麹とは:
種麹とは、麹をつくる際に「種」として使われるものです。米を原料に麹菌を培養し、胞子を十分に着生させた後、乾燥させて種麹をつくります。種麹を使って、麹菌を米に振りかけて培養したものが米麹、麦や豆に振りかけて培養したものが麦麹、豆麹です。酒蔵は種麹を種麹メーカーから仕入れ、自社で米麹を造り、日本酒の原料とします。塩麹や醤油麹は、米麹に塩や醤油を混ぜて発酵させたもので、日本酒や味噌、醤油などの原料となる米麹や麦麹とは造り方や使い方が異なります。
共同開発のきっかけはTwitter(現X)から与えられた衝撃
生駒:村井さんと種麹開発の検討を始めたのは、2020年にSAKE HUNDREDがリブランディングをしたタイミングでした。
リブランディングによって、SAKE HUNDREDはブランドの装いや哲学を一新しました。この目的の1つは、高単価市場をつくり産業全体の裾野を大きくし、サステナブルに成長させていくための手法です。当時僕が、PR TIMES STORYの中で「飲む量が1/3になったんだったら、3倍の値段でも買っていただけるいいお酒をつくればいい」と語ったことに対し、村井さんが「種麹の金額が変わらなければ種麹市場は1/3になる」とTwitter(現X)で投稿されました。
僕は恥ずかしながら村井さんに指摘されるまで、そこに考えが至っていなかったことに気づいたんです。酒蔵からの仕入れや、酒米農家からたくさんのお米を安定的に買っていることで、十分にサステナブルだと思い込んでいました。日本酒の原料は他にもある、麹菌も含めて流れに乗らなければ、という気づきは衝撃でした。
SAKE HUNDREDブランドオーナー 生駒 龍史
村井:もともと私には、種麹がコモディティ化しているという課題意識がありました。種麹は酒造用のカタログが成立するほどに、統一的な規格や流行りの酒質のための基準があり、性能差だけでは品質に差をつけにくい。日本酒の原料として必要な量も少なく、年間数袋の購入で済む酒造メーカーがほとんどで、悶々とした気持ちを抱えていました。

株式会社糀屋三左衛門 代表取締役 村井 裕一郎氏
麹産業の苦境は日本酒産業の首も絞める
村井:私が種麹業界に入ってからの10年間で、知る範囲だけでも3社が廃業ないし統合されました。日本酒の種麹をつくっている会社は、今は5〜6社ほどでしょうか。日本酒の出荷量が減るに従い、自社の売上も数量で見れば下がってきています。
生駒:日本酒は日常的に量を求める習慣から変化して、ハレの日のものになりつつあり、日本酒産業にとって高単価化の流れは必然です。しかし、原料として重要な種麹のメーカーが苦境となるのであれば、結果、日本酒業界自体の首も絞めることに繋がります。種麹そのものも高単価にしていくことが、セットで必要だと改めて感じます。

村井:麹は日本酒造りにおいて「一麹、二酛、三造り」という言葉がある通り、一番に大切なものです。
しかし、種麹メーカーは酒蔵にとって出入り業者の立ち位置なので、値上げは強く主張しづらいんです。これには歴史的背景もあります。弊社は室町時代の創業ですが、種麹メーカーは江戸時代初期にはたった2社だったものが、明治には最大30社ほどにまで増えました。高度経済成長期頃には種麹の供給量は多く、価格競争が行われていました。大衆酒で経済効率が求められる中で、種麹も経済的な低価格が求められ、さらにその後の平成期のデフレ下で、低価格傾向が加速していきました。
種麹の差別化をどのように行っていくか、それが今の種麹メーカーの大きな課題です。今回のオリジナル種麹の開発もその取り組みの1つです。開発したオリジナル種麹は、お酒と同じ原料米を使ってつくっています。これまでに「原料米にこだわってみたい」という発想自体はあったのですが、高単価になることもあり、それが果たして蔵元様に受け入れられるのかが疑問で踏み出せずにいました。
種麹は今後も数量ベースで減っていくことは間違いありません。この状況を防ぐために、日本酒のラグジュアリーへの追求に貢献できるのは、私どもとしても喜ばしい取り組みでした。
何度も試行錯誤を繰り返し、原料米を見極め開発する
村井:開発は、弊社にある研究室で行いました。SAKE HUNDREDから原料米を3種類受け取り、試行を繰り返しました。
種麹をつくる際には「胞子」がキーになってきます。米を原料に麹菌を培養する際、麹菌に酵素をつくらせるのではなく、胞子をつくることに麹菌のエネルギーを使わせる必要があります。そのために原料米の特性を見極めることが重要で、また最も難しいポイントです。原料米はたとえ同じ品種であっても栽培された年や保管状況によって条件が変わります。小規模で試行を繰り返し、データを取って予測しながら見極めていきます。
また、求められる酒質を実現するためにどの麹菌を使うべきかの選定も重要です。酵素の強さや菌の生育速度、酒粕の変色に与える影響度などを元に設定した5〜6つの条件ひとつひとつに対して透析と検体処理などの分析を行い、菌株を選んでいきます。
今回は複数の菌株を混ぜています。菌によっても生育速度が違うので、1:1で混ぜても最終的な胞子の割合が1:1になるとは限りません。商品にしたときに胞子の特性が設計通りに出るようにいかに培養するか、カクテルをつくるソムリエのように、条件に見合うレシピを開発します。

種麹の実体顕微鏡画像
生駒:今回開発したオリジナル種麹には、どんな特徴があるのでしょうか?
村井:高グルコ活性の菌株と、少なくとも100年ほど前から伝わっている大吟醸向けの菌株をメインにつくりました。また、酒粕にも色がつかないものを使っています。
高グルコ活性の菌株は、糖がたくさん分解されてグルコース濃度が高くなる性質を持つもので、香りを高める酵母との相性がいいと、一般的に言われています。豊かな香りを持つ『百光』を造るために、香りを表現しつつ甘くなりすぎないように、また、醪を仕込む段階によって麹を使い分けると聞いていたので、その使われ方も含め、SAKE HUNDREDの目指す酒質に嵌めるように設計しています。
しかし、味わいや香りで知覚できるほど、種麹による直接的な影響は少ないのが正直なところです。ただ私としては、原料米を揃えるというこだわりによって、味のまとまりや、スムーズに味が流れる余韻が出ているのであれば嬉しいと思います。
酵母による味や香りへの影響が内装やインテリアだとすれば、種麹は建物における基礎、土台のコンクリートや柱の建材の部分にあたります。内装やインテリアのように直接目に触れるものではないですが、土台の根幹となる部分は建物の基本的な構造に影響を与えるため、華々しさよりも、むしろ安定性が求められると考えています。それが、「一麹、二酛、三造り」という言葉の通り、「麹」が最も大切な理由です。
そして、人間の五感が感知しない繊細さだとしても、ラグジュアリーブランドは、建材となるコンクリートの質に至る細部までこだわることが大事だと考えています。
麹菌の実体顕微鏡画像
実は“見た目の美しさ”にもこだわっているんです。種麹をつくるときに、表面はふさふさと胞子がついていても、裏側が禿げていることがしばしばあります。今回の種麹は、1粒だけ手に取って見ても美しくあるようにこだわりました。美しいものは機能的でもあります。ムラなく胞子がついていると、酒蔵で米麹をつくるときに、麹菌を振る杜氏さんの持つ微細な感覚を遮りません。そのため、杜氏さんの意図通りに麹菌を米に振りかけることができ、最終品質の安定、ひいては総合的な顧客体験へと繋がります。
生駒:単体で見たときには小さなことでも、お客様の総合的な体験に確実に貢献しているもの、それを追求し積み上げることが大切ですよね。私たちも今回の開発でご一緒することで、味が劇的に変わることは良い意味で期待していませんでした。日本酒造りの土台である麹にこだわることで、お客様の体験を押し上げたかった。細部にまで徹底的に追求し続けることが、僕らの使命であり責任です。
地球規模の課題を解決しうる麹の可能性
生駒:今後の麹の可能性について、村井さんはどう感じていらっしゃいますか?
村井:今、日本の発酵技術が世界中から注目されています。種麹メーカーは600年も前から麹菌という微生物を商品化させてきました。それほど昔から、醸造に必要な微生物だけを自然界から取り出して、菌株から安定した品質の種麹をつくる体制を確立したのはすごいことです。世界で他に類を見ない、日本の伝統技術です。微生物という醸造条件が安定しコントロールできる要素になったことで、日本酒の“杜氏の腕”という概念が確立し、醸造技術も発展してきました。こういった麹文化を含む日本の精神性や技術を発信していきたいです。
もう1つは技術的な話になりますが、麹菌の特徴は、ひとことでいうと「物質変化」です。例えば、大豆を溶かし味噌にして、消化しやすくする。麹は、人間が食べることができないものすらも、菌の力を借りることで、アルコール飲料や味噌のように化ける可能性があります。実際に奄美大島では米や麦が乏しく、戦後の食糧難のときにはそのままでは毒性があり食することができない蘇鉄の実や幹を、麹菌を使い発酵させることで食糧源にしていたそうです。今後、例えば食糧不足を課題に抱える地域において、植物の根などを可食性のあるものに変化させることができるのではと考えています。
生駒:麹は地球規模の大きな課題を解決しうる可能性を持っているんですね。ぜひその文化を世界に広げて欲しいです。

村井:SAKE HUNDREDは、日本酒ラグジュアリーの先陣を切っています。日本酒の価値をもっともっと高めていっていただきたいです。それが日本の発酵食品の価値を高めることにも繋がります。あんなに手間暇をかけて造られている醤油が、なぜ海外産の炭酸水よりも安いのか。大衆品として手に取りやすいよう普及することも大事ですが、原料、造る工程、生産者の想い、技術の高さ、労力を考えても、発酵という業界は、このままでは次の世代が経済的に継続していける業界ではありません。SAKE HUNDREDには今後も、サステナブルに繋がる活動をしていくことを期待しています。
生駒:ありがとうございます。僕らが思っている以上に、SAKE HUNDREDの活動の延長線上に良い未来が波及していくんだと感じました。僕らはもちろん、グローバル・ラグジュアリーブランドを目指していますが、1社ができることは限られています。大事なのは、産業全体で同じ志を持つことであり、その総和が大きな価値を生んでいきます。ラグジュアリーの先陣を切りながら、真似してみようと思ってもらえるようなブランドであり続けます。
行動者ストーリー詳細へ
PR TIMES STORYトップへ
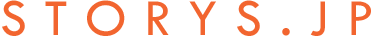


 LINE
LINE
