北野天満宮の梅、醍醐寺の桜──。名木のクローンを作り、「記憶」まで後世に残す。住友林業で組織培養に取り組む研究者の思い

菅原道真が愛した京都・北野天満宮の「飛梅」や、豊臣秀吉が花見をしたという醍醐寺の「太閤しだれ桜」、そして東日本大震災で生き延びた岩手・陸前高田の「奇跡の一本松」──。
歴史的・文化的にも重要な意義を持ち、人々に愛され続けている名木は日本をはじめ世界各地に数多く存在する。けれども樹木にも寿命はあり、人間と同じように歳を取り、病気に罹り、いつかは朽ちていってしまう。そんな木々を後世まで残すために、近年「組織培養」という技術が注目を集めている。
組織培養とは、バイオテクノロジーの手法のひとつであり、もとの木とまったく同じ苗を作ることができる技術である。従来、木を増殖させる際には「挿し木」や「接ぎ木」といった手法が使われるが、これらの手法だと、樹齢や樹木が持つウイルスなどをそのまま引き継いでしまうため、寿命を伸ばすことはできない。けれども組織培養の技術を使えば、樹木の遺伝子はそのままに、「幼若化」という若返り現象を起こすことが可能と言われているのだ。
住友林業は、1998年から組織培養研究に取り組み、世界でも指折りの技術を有している。中でも梅と桜に関しては、世界で随一の知見がある。木に宿る歴史や文化を後世まで残していくために必要な技術──。今回は、2009年に住友林業に入社し、組織培養技術を牽引する中川麗美に話を聞いた。

中川麗美。2009年住友林業入社。筑波研究所資源グループで主任研究員を務める
祖父母の畑が、研究者の道に導いてくれた
中川が研究者の道に進むことになった原体験は、小学生時代にまで遡る。祖父母が長野で農業を営んでいて、幼い頃からよく遊びに行っていた。
「畑に行くのが楽しみで仕方ありませんでした。小さかったトマトが水だけでどんどん大きくなる姿が私にとってはすごく不思議で、どうして勝手にこんなに大きくなるんだろう?って。その過程への興味や興奮が今も冷めない。研究者を続けている理由は、植物が好きだから。ただそれしかないんです」
幼い頃から感じていた、植物という生命が「育つ」ことに対する興味──。高校時代には、もっと植物を知りたいという気持ちを抑えきれず、農学部への進学を決意した。周囲にはたいそう驚かれたという。そして大学院に進学する際に、とある新聞記事をふと見かけたことをきっかけに組織培養の道へ進むことになった。それは、中川の大学の先輩であり、住友林業の研究者である中村健太郎の記事だった。
「当時、中村がインドネシアで熱帯雨林再生のための樹木増殖技術の開発に成功したという記事を読んだんです。ああ、世の中にはこんな研究があるんだと、組織培養に一気に気持ちが傾きました」
記事に感化された中川は、大学院で組織培養の研究を始めた。博士課程まで進み、その後もポストドクター(博士研究員)として研究を続けていたところ、海外の学会でなんと中村健太郎に再会する。そして彼から直接話を聞くうちに、住友林業での研究に魅力を感じるようになった。
当時、海外で研究をしたいという思いを強く持っていた中川はかなり悩んだというが、ポストドクターは研究のスパンが短いことも多く、成果が出る前に次の研究に進まなくてはいけないこともあった。住友林業だったら、もっと長い時間をかけ、腰を据えて自分の研究に没頭できるのかもしれない。そう思い、この環境を選ぶことにした。

住友林業筑波研究所。木の総合的な活用を目指し、1991年に設立。
写真は2019年完成の新研究棟
北野天満宮の「飛梅」を、後世に残すプロジェクト
2009年に住友林業に入社したあと、中川はすぐに梅の組織培養に取り組んだ。2000年に中村が枝垂れ桜の組織培養に世界で初めて成功していたが、梅での実績は当時、世界中どこを探しても無きに等しかった。中川に与えられたミッションは、京都・北野天満宮で菅原道真が愛したと言われる名木「飛梅」を培養すること。
当時、梅やモモなどのバラ科に感染する「プラム・ポックス・ウイルス(PPV)」が流行し、日本各地の梅が伐採されるという事態が起きていた。そんな背景もあり、貴重な名木を後世に残していくために北野天満宮と住友林業が共同で研究開発をすることになったのだ。

「梅が好きなんです。実は食べられるし、かわいいので」と中川。
桜や梅の木は芽が小さくとても繊細で、組織培養の中でも特に成功させるのが難しい樹木だ。何年かかるかもわからない大きなプロジェクト。中川が北野天満宮に足を運ぶと、こんな声に出会った。
「おじいちゃんやおばあちゃんが梅を見に来ていて、今年は花が少ないとか、私がお嫁に来た頃はもっと花が濃かったのよ、なんて言うんです。何十年もこの梅と共に生きてきた人がいる。木には記憶が宿っているんだと実感しました」
そんな思いを聞くたびに、「絶対に成功させなければいけない」という思いを中川は抱いたという。
成功まで5年間。一筋縄ではいかない組織培養の技術
組織培養は、成功するまでに長い月日を要する研究だ。
まずは「冬芽(とうが)」と呼ばれる冬季の芽を採取し、顕微鏡下で芽の皮を剥き、細胞分裂がもっとも活発である「茎頂(けいちょう)」と呼ばれる組織を摘出する。梅の場合、冬芽はなんと1mm程度。そこからさらに小さな茎頂を取り出すというのだから、その作業の大変さは語るまでもない。

これまで取り出した茎頂の数は数千個に及ぶという
取り出した茎頂をさまざまな栄養が配合された培養液で3か月ほど育てると、「多芽体(たがたい)」と呼ばれる芽の塊に成長する。中川いわく、この培養液の配合が一番難しいのだと言う。数多ある組み合わせの中から、ぴったりの配合をゼロから考えなければいけないからだ。そして育
った多芽体を寒天培地でさらに3か月ほど育て、茎を伸ばし、人工土壌に移して発根させ、そうしてようやく苗木が完成する──。

茎頂はこんなに小さい。これが立派な樹木に育つのだ(写真は桜の茎頂)

培養液の中で育て、多芽体まで成長させる
北野天満宮の飛梅から毎年採れる冬芽の数は、たったの30個だった。貴重な名木なので造形を崩してはいけないし、樹齢も高いのでそもそも芽が少ない。この梅を大切にする人がいる限り、研究本位な枝の伐採は絶対にできなかった。
毎年30個の小さな芽を育て、失敗したらまた翌年まで待つ。チャンスは年に1回。培養液の配合、温度や湿度、何十もの条件がぴたりと重ならなければ、小さな小さな芽は育ってくれない。まさに、針穴に糸を通すような成功確率だった。
「毎年冬になるたびに、北野天満宮さんに行っては芽を採らせていただいて、それを7年ほど続けました。毎年、今年もダメだったと伝えるのが申し訳なくて、それ以上に成功させられない自分に悔しくて、泣きながら帰ることもありましたね」
5年ものあいだ、成功するかどうかもわからない小さな小さな芽と向き合い続ける。「好きだからしんどくはないんですよ」と中川は笑うけれど、それはどれほど孤独で大変なことだっただろうか。
ついに2015年に苗木の増殖に成功した時には、喜びよりも安堵の方が強かったのだという。成功の喜び、達成感、プレッシャーからの解放、さまざまな気持ちが一気に押し寄せてきたのだろう。
中川は、増殖が成功し、北野天満宮に苗木が里帰りしてからというもの、毎年京都までその梅を見に行っている。「私の子どもみたいなものなので。今ではもう見上げるほどの大きさになっていて、花も咲いて、可愛くて仕方がないですよ」。そう言う中川の目は、慈愛に満ちていた。

住友林業の筑波研究所にも、当時中川が増殖した「飛梅」の木がある。
取材時はまだ蕾だった

北野天満宮の梅は、色濃く可憐に咲く(写真撮影:住友林業)
「いつかは世界中の木々も受け継いでいけたら」。
中川は、北野天満宮の梅と並行して、仁和寺の桜や長浜の盆梅など、さまざまなプロジェクトにも関わっていた。
組織培養の研究はなんといっても時間がかかる。北野天満宮の事例からもわかるように、ひとつのプロジェクトで10年単位のものも多いのだ。「生きているうちに、あと数個実験が成功したらいいなというところです」と言う中川が今後いつか取り組みたいのは、世界の名木を残すことなのだという。
「アムステルダムに、アンネ・フランクが逃亡時に窓から眺めていたと言われる栗の木があるのですが、それが倒れてしまって大変だというニュースをずいぶん前に見かけて。組織培養の技術は木が倒れても芽が生きていれば増殖ができるので、そのような名木を救いたいです」
日本だけに止まらず、世界中の文化や歴史が宿る木々を守っていきたい。そんな彼女の言葉からは、樹木を愛するまっすぐな貪欲さが伝わってくる。
ほかにも、まだ成功したことのない松の組織培養も、中川が必ず成功させたいことのひとつだ。「奇跡の一本松」は、まだ接ぎ木でしか増殖できておらず、中川は大学時代も松の研究で苦戦していた経験がある。「松は大変なんですよ」と困りながら口にする彼女は、それでもどこか楽しそうでもある。


奇跡の一本松と、種子からつくられた苗木
(写真撮影:住友林業)
最後に中川に、組織培養の仕事のやりがいを聞くと、このような答えが返ってきた。
「梅でもどんな植物でも、綺麗で優秀な種類はいくらでもあるんです。どんどん新しい品種が作られてるし、おいしい実を作る果樹を作ろうと思えば作れる時代。でも、単に品質が良いということだけではなく、これまで木を大事にしてきた人の気持ちまで受け継いで、今までの技術では残しきれなかったものを残したいなと思います」
名木を後世に残すために人生をかける研究者。
彼女の植物への愛は、今日も誰かの記憶や愛を守り、受け継ぐことにつながっている。
行動者ストーリー詳細へ
PR TIMES STORYトップへ
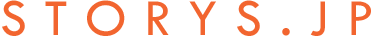
 LINE
LINE
