株式会社エール 創業ストーリー
株式会社エールの真鍋聖司氏をご紹介します
真鍋氏は1973年京都に生まれました。
エールを立ち上げたのは2006年、32歳のときです。
このページでは、真鍋氏がエールを立ち上げるまでの経緯や、これからの目標などを記しています。
株式会社エールのことを知っていただけるきっかけになれば、とてもうれしいです。
どうぞよろしくお願いいたします。
世に喜びと笑エール仲間を
京都府大山崎町にある株式会社エールの社屋に近づくと、室内から大きな笑い声が聞こえてきた。
声の主はエール代表の真鍋聖司氏。
「笑エール(わらえーる)仲間をもっと増やしたいんです!」
オヤジギャグだが、彼は真剣そのもの。
笑える仲間を増やすには、まずは自分がよく笑うこと、そう信じ、いつも冗談を飛ばして笑いをとっている。
陽気な彼を贔屓にする取引先も多い。
明るい性格だが、エールを立ち上げるまでは順風な人生とは言えなかった。
社会人のスタートは経費自腹の訪問販売
「弟と二人で居酒屋を開きたい」真鍋氏はずっと考えていた。
幼い頃から人を喜ばすことが好きだったから、学校を卒業したらサービス業に就きたいと思っていた。なかでも居酒屋はいつも笑いであふれいてるイメージだったので、働くなら居酒屋に決めていたという。
居酒屋を始めるために必要な条件を調べると、まずは料理の腕を磨く必要がある。
でも、修行は最低で10年かかることがわかった。
「10年かかったら30歳過ぎてまうやん。そこから、店を開くための費用を稼いでいたら、40歳なんてすぐや!」
彼は店の資金を稼ぐことが先決と考え、高額報酬の仕事を探すことにした。
求人誌を購入してすぐに「月給70万円」の文字が目に飛び込んだ。
面接に行くと即採用。翌日から働くことになった。
高額な教育教材を販売する仕事だった。
スーツを新調し、意気揚々と会社に行くと、社長から 「真鍋くん、君の名刺つくったから1万円ね」と言われた。
真鍋氏はすぐに1万円を支払った。
その後も、「ガソリン代」「電話代」「交通費」すべてを請求される。
世間を疑うことを知らなかった彼は「仕事はこういうもんなんやな」と納得し、なんの疑いもなく経費を支払い、営業に回った。
もちろん、ローンで購入した自家用車で。
「真鍋くん、営業いうもんは契約取れるまでは帰ってこないもんや。もちろん休みもなしや」
そういわれ、真鍋氏は土日も関係なく深夜まで飛び込み営業に回った。
会社に戻るのはいつも深夜過ぎ。
それでも契約は一本もとれなかった。
経費はかさむ一方なのに。
食パンの耳だけをかじって営業に回り、喉が乾いたら公園の水で潤した。
交渉にかかる時間は平均で4〜5時間。
長いときには12時間、早朝まで説得を続けたこともある。
はじめて契約がとれたときは本当にうれしかった。お客様が喜んで契約してくれたあの時。
忘れられない瞬間だ。
「人を喜ばさせたい」という気持ちと努力の結果から、その後は成績が順調に伸びていく。
1年後にはトップ営業マンになり、給料も月額70万円を超すようになった。
父親に毎日連れて行かれたスナックが原点
「人を喜ばせたい」そう思うようになったのは自然なことだった。
真鍋氏は子供時代、遊園地に行ったことがない。
その代わり、父親に連れられて毎日のようにスナックへ通ったという。
スナックには陽気な大人が集まっいた。
そんななかで、彼はアイドルのような存在だったのだろう。
真鍋氏と弟がカラオケで「3年目の浮気」を初めて歌ったとき、みんなが笑い、喜んでくれた。
もちろん父親も。
それがとてもうれしかっただという。
父親にとっても二人は自慢だったに違いない。
奔放だった父親は、彼が社会人になったとき自己破産した。
今はどこにいるのかも分からないという。
幼いころの体験が性格を決定づけたのだろう。
成長するにつれて「人を喜ばせる」ことに磨きがかかっていく。
中学・高校時代の弁論大会では爆笑をとり続け、6年連続優勝という快挙を成し遂げた。
真鍋氏にとって、営業という仕事は天職だったのかもしれない。
会社を去って北海道へ
営業成績が順調に伸び続け、生活に余裕が出始めると疑問が湧くようになった。
高額教材を謳っていたものの、原価が数千円ぐらいだったからだ。
「これっていったい!」
落ち込んだ。怖くなった。
彼の言葉を信じてお金を払ってくれた人。仲良くなって夕食までごちそうしてくれた人。
お客様の顔が浮かぶ。
悲しくてたまらなくなった。
彼は会社に辞意を伝えた。
驚いた社長は引きとめようと必死だった。
成績トップの営業マンを失うのは会社にとって痛すぎる。
なかなか辞められないまま、また1年が過ぎようとしていた。
いよいよ耐えられなくなった彼は、置き手紙をして突然会社を去る。
そして、会社を辞める報告をするため、契約してくれたお客様のもとを1軒ずつ回った。
「真鍋さんだから契約したのにひどい!」
先々で罵声を浴びたが、謝ることしかできなかった。
最後のお客様のもとを去ったあと、急に北海道へ行きたくなった。
いつか開きたいと思っている居酒屋は北海道で生まれたと聞いたからだ。
北海道は想像以上に広く、美しく、穏やかだった。
安宿で出会った人たちも新鮮だった。
50歳を過ぎた“職業旅人”、短期のアルバイトを繰り返して1年の大半を北海道で過ごす人、九州から自転車できたという人。
いろいろな人に出会い、たわいもない話をして過ごした。
幸先のよい再スタートが一瞬でお先真っ暗に
北海道の旅を続けるうちに、再び働く意欲が湧いてきた。
そして今度こそ、自分のやりたかった仕事をするんだと心に決めて京都に戻る。
仕事を探しを始めたとき、京都でも屈指の高級料亭がマネージャーを募集していた。
あこがれのサービス業である。
給料もいい。
面接に行くと、当時の女将さんから「元気があってええなあ、あんたに決めるわ」といわれ、その場で採用が決まった。
母親に告げると、よほどうれしかったのだろう、親戚縁者からご近所、友人に話して回った。
再起を図るのにこんなにいい条件はない。
今度こそ、という思いで初出勤し、女将さんのもとへ挨拶にいった。
ところが、神妙な顔つきの女将さんが突然、 「真鍋くん、今回は縁がなかったということにしてくれる? かんにんな」 と解雇を告げられる。
何がなんだかわからなかった。
しばらく鴨川に佇んだあと、ふらふらと歩いたことを覚えている。
気がつくとハローワークの前に立っていた。
初めて知ったルートセールスで再びトップ営業マンに
ハローワークにいくと「ルートセールス」という仕事を紹介される。
初めて聞く言葉だ。
聞けば、訪問販売とは違う営業スタイルだという。
営業=訪問販売=飛び込みと思っていた彼には衝撃だった。
紹介を受けて面接に向かったのは雑貨メーカー。
過去の経歴が買われ、無事に採用が決まる。
いざルートセールスを始めると、仕事が楽しくてたまらなくなった。
人を騙すことなく、存分にものを売れる。
各店舗の店長さんと仲良くなれる。お店の売上が上がる。
話が弾む。信用を得られる。
すべてが新鮮だった。
やっと自分の居場所を見つけた気がした。
成績は伸び続け、すぐにトップ営業マンとなる。
単価数百円の雑貨で、コンスタントに月4,000万円の売上だったというから驚きだ。
29歳になったとき、真鍋氏は結婚した。
公私ともに充実した日々だった。
ヘッドハンティングが一転、六畳一間からのスタートに
業界でも一目を置かれる存在となった彼を、他社が放おっておくわけがなかった。
ヘッドハンティングである。
条件は今の会社の倍近く。
自分の力をもっと試したい。
そう思った彼は転職を決意した。
しかし、蓋を開けてみると、給与は半分以下しかもらえなかった。
話がまったく違っていたのだ。
もといた会社に戻ろうにも、転職の挨拶はすっかり済ませている。
今さら戻るわけにはいかない。
そんなとき、尊敬する先輩営業マンから「独立してみたらどうだ」というアドバイスを得る。
その一言がすべてを決めた。
2006年7月21日、個人事業のエールがスタートした。
エールという社名には4つの意味を込めた。
お店にエールを送れる存在であること。
皆様のエールに応えられるよう努力すること。
まなべエール(学べる)、生涯初心であること エールはフランス語で「翼」も意味する。
自分もいつか翼を広げ、大空高く舞い上がりたい。
自宅の六畳一間を事務所兼倉庫とした事業が始まった。
営業で全国を飛び回ったが、ホテルに泊まる経済的な余裕がなく、車に泊まりこみ、駅のトイレで体を拭いて次の営業先へと向かう日々が続いた。
発送作業は自宅前の駐車場で行った。
雨の日にはブルーシートをかぶせて商品が濡れるのを防いだ。
自由に使えるお金は200万円。
家のローンもある。子どもは生まれたばかり。
でも、やれる自信があった。
しかし、独立後の売上は20万円。
かつて月4,000万円売っていたというのに。
資金200万円は生活費にどんどん消えていく。
気ばかりが焦った。
営業の電話をしていると、隣で赤ん坊がグズる。
先方からは不審がられ、自宅裏の畑に出て電話をした。
取引がなかなか広がってくれない。
奥さんの両親からは「もう辞めてくれ」と懇願された。
眠れない日々が続き、どうしていいかわからず、奥さんに相談したときだった。
「『あんたの心臓は毛が生えているから大丈夫や!』と赤ん坊を抱きながらいってくれましてね。この人がいればやれるって思いました」
大きな気付きもあった。
会社員だったころは営業だけに専念できたが、個人事業主になってからは、細かな事務処理、経理、すべてを1人で行わなければならない。
いや、1人じゃない。
仕事は1人だが、奥さんをはじめとする家族がいる。
自分は多くの人に支えられている。
それからは吹っ切れたように、一層仕事に打ち込んだ。
性格も明るく、前向きになった。
そして、「人を喜ばせたい」という持ち前のサービス精神で営業に回り、少しずつ取引先を増やしていった。
3年後には大山崎に事務所を借り、従業員も少しづつ増えていく。
「それ、おもろいやん」が生んだチャリCAP
エールに転機が訪れたのは、設立して4年目のときだった。
それまでは雑貨の問屋業に専念していたが、スマホやゲームなどの普及もあって、年々雑貨業界の売上は減っていた。
このまま雑貨だけの問屋を続けていてはまずいと考え、オリジナル商品の開発に踏み切ることにした。
決めたはいいが、具体的なプランはなにもない。
こんなとき、真鍋氏はいつも周囲の人に意見を求め、どんな些細な話でも真剣に聴く。
そして、必ず心を込めてこういう。
「それおもろいやん! いけるんちゃう!!」
言われたほうは、お世辞であっても嬉しくなる。
こうなれば、アイディアは次々に溢れ始める。
そんなアディアのなかから生まれたのが、エール初のオリジナル商品「チャリCAP」だった。
従業員の1人が、かわいいサドルカバーについて話したのがきっかけだった。
「それおもろいやん! いけるんちゃう!!」
早速、周囲の人に聞くと、上々の評価を得る。
商品化するための試行錯誤がはじまった。
10時間の実演販売で売れたのは、たったの5枚…諦めかけた自分を救ってくれたのはお客様からのエールだった
当時、サドルカバーといえば、黒かグレーだけだった。
しかも、ブカブカとしていて、いかにもみすぼらしい。
せっかくのカバーが、自転車の見た目をダメにしている。
そこで、型くずれしないように上部とサイドの繋ぎ目にパイピングをつけた。
こうすることで、見た目も美しく、長時間の使用にも耐えられる構造になる。
チャリCAPの特徴はなんといってもデザイン性だ。
これまでになかったおしゃれなデザイン、かわいいデザインを次々に商品化。
デザインだけでなく、キャラクターものも扱っている。
実用新案も取得した。
しかし、発売当初はまったく売れなかった。
大手ショッピングセンターの売り場の一角を借り、10時間にわたって実演販売したが、
売れたのはたったの5枚。
「これあかんかな」と諦めかけたとき、つい今しがたチャリCAPを購入してくれた中年の女性が近づいてきた。
「自分の自転車につけたら、めちゃよかったで。これ絶対売れるわ。がんばりや」といって励ましてくれた。
人にエールを送りたいと思って会社をつくったのに、逆にエールを送られる自分がいた。
こうして喜んでくれるお客さんがいる。諦めるにはまだ早い。
フロア中に響き渡るような声を出し、実演販売を続けた。
「日本の自転車 の10台に1台はチャリCAPを」
当初は思うように売れなかったものの、地道な営業活動によって、その後は徐々に受けいられるようになり、現在までに累計20万枚売れるヒット商品になった。
今では大手自転車メーカーも、デザイン性のあるサドルカバーを扱うようになっている。
だが、掲げる目標は高い。
「日本の自転車の10台に1台はチャリCAPを」というのが目指す数字だ。
日本の自転車保有台数は約6,910万台(2012年一般財団法人自転車産業振興協会発表)、10 台に1台となると691万枚の計算になる。
普通の人が聞いたら「無理に決まっている」というに違いないが、真鍋氏は大真面目だ。
目標達成に向け、今日も明日も全国を駆けずり回る。

かわいくてオシャレなものから、クスッと笑エールものまで幅広い
ラインナップのチャリCAP。
本当に笑エール(わらえーる)仲間を増やすために
順調に業績を伸ばしているが、訪問販売していたときの自分と比較すれば、まだまだ頑張りが足りないという。
それに、あの頃の自分に勝つためには、ただ売上げを上げるだけではダメと考えている。
今は一緒に働く仲間=従業員が増えた。
まずは彼らに愛される会社になり、好かれる商品を取り扱うことが大切だと考える。
もっとも身近な存在である従業員に愛されないようであれば、会社も伸びないし、商品だって売れるはずがない。
そのためにどうすればいいか、模索を続けている。
一方、新しい取り組みとして、となり町にある児童養護施設にチャリCAPをプレゼントしている。
訪問販売をしていたところは法外な利益を得る一方で、誰かに還元することはなかったからだ。
「買ってくれた人が心から喜び楽しめるものを取り扱っていきたい。その利益の一部が、誰かのためになるなら、笑エール(わらえーる)仲間がもっと増えるように思えるんです」
そういうと彼はチャリCAPで顔を隠し、こちらの様子を伺いながら、
「これがほんとのチラリCAP」
といって、おどけてみせた。
(取材・文:TouchWork ユグリサトシ)
行動者ストーリー詳細へ
PR TIMES STORYトップへ
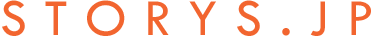
 LINE
LINE
