個として際立つエンジニアに組織の恩恵を。フリーエンジニア専門コミュニティが提案するエンジニアの新しいつながり方
Hello World!
世界のみなさま、こんにちは。
株式会社Stanfitの松下航平です。
Stanfitは中級以上のフリーエンジニアを対象とするコミュニティです。
なぜ中級以上に限定しているのか、理由はのちほど説明します。
私たちが考える「フリーエンジニア」とは、専業のフリーランスエンジニアだけでなく、企業に所属しつつ副業でエンジニアをしている人も含めた広い概念です。
Stanfitでは、フリーランスや小規模事業者などの「個」として活動しているエンジニアにむけて、経理・法務などのバックオフィス、技術の提供やノウハウのシェアなどをおこなっています。
今回のSTORYでは、私がStanfitを立ち上げた背景をお伝えします。
使えないアプリとインベーダーゲームが教えてくれたプログラミングの世界

私がプログラミングを始めたのは大学時代です。先輩に誘われてスマホのカメラアプリを作る講座に参加したのが、プログラムと呼ばれるものとの出会いでした。
しかし初めは誰もがそうであるように、私が作ったカメラアプリは、特別な機能はなにもついていない「使えないアプリ」でした。とはいえプログラミングが初めてだった私にとって、無から有を生みだす体験はとても刺激的だったのです。
初めてのプログラミングで「ものづくりへの意欲」に火がついた私が、次に取り組んだのがインベーダーゲームの開発でした。
600ページもある分厚いテキストとモニターを交互に凝視する日々。先輩のアドバイスもいただきつつ、なんとか一人で完成させたものの、「たった一つのプログラムを仕上げるだけで、こんなに大変なのか……。」と、プログラミングという世界の巨大さを痛感しました。
誰と競い合うわけでもなく、誰かに賞賛されるわけでもない。
華々しく顔と名前を売るわけでもなく、だからといって誰にでもできる簡単な仕事ではない。
つまりエンジニアという仕事は、裏方であり職人でもあるわけです。
カメラアプリとインベーダーゲームの開発によって、プログラミングに開眼し、その世界観に魅了された私は、「エンジニアとして生きていこう」と心に決めました。
フリーエンジニアに「安心」はない

大学を卒業した私は、国産ブラウザでトップシェアを誇るSleipnir(スレイプニール)を開発したフェンリル株式会社に入社しました。フェンリルは副業を認めていたので、私もECサイトのアプリ作成やディレクションなど、積極的に副業をしていました。
振り返ると、すでにこの当時からエンジニアの働き方について確固たる未来を描いていたようにおもいます。
「エンジニアが一つの組織、一つの専門職に注力する時代はもう終わる」
フェンリルを退職した私は、フリーエンジニアとして数社のプロジェクトに参加しました。
フェンリルでの仕事を通じて、エンジニアリングのスキルは大幅に向上ました。しかし当時の私はまだ20代前半。「フリーランスとして、組織の人間とどう向き合うか」というコミュニケーションスキルにやや不足がありました。そのため現場では何度か役員と衝突することも……。
フリーランスと組織の関係は、たった1枚の業務委託契約書でつながっています。そこには雇用契約のような強固な関係は存在しません。
社員エンジニアなら、仕事の最中はもちろん、仕事を離れた時間も、同僚との交流関係を深めることができます。
しかしフリーランスは、基本的には「会社の外からやってきた労働力」とみなされます。したがって仕事を離れてしまえば、同僚との関係はどうしても希薄になりがちです。
仕事の最中も、業務に必要なかぎりで一定のコミュニケーションはありますが、それを超えたさまざまなサポートは受けられません。
たとえば確定申告などの経理作業はその典型です。クライアントとの契約や労務管理といった法務まわりの問題も、社員であればすべて会社が主導し、不足があればフォローしてくれますから心配無用です。
しかしフリーエンジニアの場合、経理も法務も自己責任で処理しないといけません。
「エンジニアとしてどれだけスキルや経験があっても、フリーであるかぎり、社員エンジニアが享受するような『安心』は得られない」
この決定的な現実に直面した私は、フリーランスとして活動を始めた1年半後、Stanfitを創業します。
はみだして、なじめ

ONE OK ROCK の「Stand Out Fit In」という曲をご存じですか?タイトルの和訳は「はみだして、なじめ」。
この曲を初めて聴いた2018年、私は会社の創業に向けてアイディアを練っていました。とくに悩んでいたのが社名です。YouTubeで大好きなONE OK ROCKのナンバーを流しながら、ああでもないこうでもないと思案に暮れていた私の耳に飛び込んできた曲が、「Stand Out Fit In」でした。
・・・・・
ありのままでいたい
他の誰かになんてなれない
あれこれ指示されるのはうんざりだ
同じことの繰り返しに飽き飽きしている
・・・・・
まるで私のことを歌っているかのようでした。
ただボーカルのTakaは、「自分の好きなように、自分の思うように生きればいい!」とあおっているのではありません。
・・・・・
現実を見ろ、夢を持て
はみだして、なじめ
・・・・・
愚痴りながら、好き勝手に生きるだけではいけない。夢を持つことも、現実社会のなかで生き抜くことも、どちらも同じくらい必要だ。
(個として)はみだしてもいい。でも、(組織や集団に)なじむことも大切なことなんだよ。
そんな風に問いかけられているような気がした瞬間、頭の中にStanfit(スタンフィット)という造語が浮かんできたのです。
(Stand Out=個としてはみだす)
フリーのエンジニアとしてスキルを高め、どんな仕事にも対応できる存在になること。
(Fit in=組織になじむ)
フリーとして活動しながらも、まるで組織に属しているかのようなメリットを得られること。
「Stanfit」という社名は、こうして誕生しました。
2019年8月に株式会社Stanfitを設立し、2020年5月からコミュニティの会員募集を始めました。現在では50名を超えるエンジニアが全国から参加しています。
エンジニアの未来は「個と組織のハイブリッド」にあり

Stanfitは「個と組織のハイブリッド」を目指しています。
エンジニアが個として存分にそのスキルを発揮するには、経理や法務といった組織に属するエンジニアなら当然受けられるサポートを提供する必要があります。
またフリーエンジニアの場合、日々の仕事で生まれたちょっとした疑問について、いったい誰に相談すればいいのか迷うことがよくあります。社員エンジニアであれば、机を並べて仕事をしている同僚に相談できますが、一人で仕事をするフリーエンジニアだとそうはいきません。
同様に、仕事の進め方や将来のキャリアについて、大局的見地から助言してくれる仲間は、フリーで仕事をしているとなかなか出会えません。
フリーであるがゆえに生じる不安や不自由を解消すること。
それにより個としてのパフォーマンスを最大化すること。
これがStanfitのミッションです。
アフターコロナの時代、「働く」という概念は大きな変容を迫られています。職場に出勤することは、決して当たり前ではなくなりました。
副業を推進する国の方針とあいまって、個人と組織の結びつきは年々弱まりつつあります。組織の内と外を隔てていた壁はどんどん薄くなり、境界線が曖昧になっているのです。
このような時代では、ますますStanfitのような「出入り自由のゆるやかな組織」が強く求められている……そう実感しています。
腕に覚えのあるエンジニアは奮ってご参加を!

Stanfitは、あらゆるエンジニアに門戸を開放しているわけではありません。参加条件は「中級以上のスキルや経験の持ち主」であること。
Stanfitは、会員同士でスキルや経験を共有することを重視します。定期・不定期に開催する勉強会はもちろん、ちょっとした質疑応答やがっつり話し合うキャリア相談など、エンジニアとしての自己の知見を他の会員に無償で提供し、活用してもらう機会が数多くあります。この相互扶助の関係なくして、Stanfitの活動は成り立ちません。
そこでStanfitでは、他のエンジニアに対して自己のスキル・知識・経験を積極的に提供できるGiver(ギバー)であることを、会員になるための必要条件としました。
他のエンジニアに対して提供できるだけの、スキル・知識・経験を有することは、駆け出しのエンジニアでは難しいのが現実です。そこで、「中級以上」という目安をつけた次第です。
個として際立つ(Stand Out)優れたエンジニアが、仲間と知見を共有しながら組織(Stanfit)になじむことで(Fit In)、一人ひとりのパフォーマンスを最大化する。
このミッションに共感していただいた方は、ぜひお気軽にお問合せください
お問い合わせはコチラ▼
弊社のコンセプトや提供するサービスは、これまでに発表したプレスリリースでもくわしく紹介しています。ぜひこちらもあわせてご覧ください。
【業界初】フリーエンジニアの悩みを一挙に解決するサービス「Stanfit」始動!
【無料会員募集!】教育×バックオフィスをワンストップで!フリーエンジニア専門コミュニティ「Stanfit」がPR動画を配信
【株式会社Stanfit】オープンソースソフトウェアを限定公開!開発速度UPや新人研修の教材に最適
フリーエンジニアの経理・法務は「Stanfit」におまかせ!月額5,600円から利用できる有料会員募集スタート
行動者ストーリー詳細へ
PR TIMES STORYトップへ
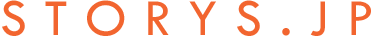
 LINE
LINE
