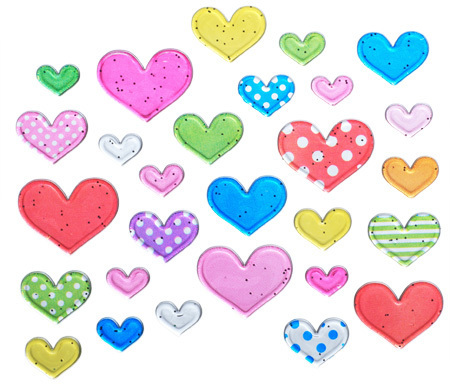15の春を泣かせるな、に思いっきり泣いた話
保健室に居場所もない中学三年生
中学3年生の時点で、私には友達がいないかった。お弁当も一人で食べていた。それも昼休みではない。3時間目と4時間目の休憩時間の間に食べたのだ。
昼休みに教室にいるといじめられる。クラスには居場所がなかったからだ。
授業3分前に、筆記用具を音を立てずに片付ける。問題集を机の中から出す。それらを持って、チャイムが鳴ったらすぐに図書室に向かった。
いじめられない場所。これが私には必要だった。25年前の学校の保健室はいじめられっ子や不登校の子どもには非常に厳しい場所だった。
「サボることは許されない」という空気がただよっていた。もっと頑張れとやんわりと養護教諭からプレッシャーを受ける。だから保健室で過ごすことは許されない。
「よし、30分の間にここまでやろう」
数学の問題集を開き、ガンガン問題を解く。いつも数学だった。一つしかない答えに向かって必死に問題を解く。このことで辛い学校生活を一時忘れることができるからだ。
「あと半年耐えれば、この生活を終えられるんだ」
いじめられ、からかわれ、時には石を投げられたり、足をひっかけられたりする生活はまもなく終えられる。なんとかして、時間をやり過ごすんだ。学校には毎日行く。あいつらのせいで人生を棒に振るなんてありえない。私はあいつらには力では勝てないけど、もうかかわらないでいい場所に行くんだ。
そう必死で奮い立たせながら、学校生活を送っていた。
地元集中運動という名の攻防
体育祭も終わってしばらくたったある日、図書室にいる私のところに担任の先生がやってきた。
担任の先生は私なんてほぼ無視している。「いじめられている」と私が窮状を訴えても、「何事も問題も起こすな」と拒否した先生だ。完全に迷惑な存在だと思われているのが伝わっていた。
その先生が、私のところにやってきたのだ。
「下川、ちょっと話があるんだけれど」
ーーいったいなんだろうか。
よくわからないまま、私は先生の後ろをついていった。場所は職員室ではない。普段使っていない空き教室だった。
「そこに座りなさい」
私は、先生のとなりに座った。すると、一枚の紙を先生が机の上においた。その紙は私が書いた進路希望用紙だった。
「なんで、この高校を希望しているんだ?」
「それは、行きたいからです」
私は先生の顔を見ずにうつむいて答えた。私が書いたのは学区で一番の進学校だった。冒険でも何でもない。私はもう他人以上に疎遠なクラスメイトがいる場所から離れるべく必死で勉強した結果、そこには手が届いていた。
「どうして、地元の高校を書かないんだ?」
「行きたくないからです。先生わかりませんか」
「わからないね。君の進路はみんなを見下すような選択だ。地元の高校と書きなさい」
「先生、私はみんなを見下していません。見下しているのはみんなです」
「それは屁理屈だ」
ーー屁理屈。屁理屈を言っているのは先生ではないか。
当時、私の地元では、「地元集中運動」という運動が繰り広げられていた。学力格差により就職格差が生まれ、社会の不平等が生まれる。だからそもそもどんな成績の人間も同じ高校に行けば、レベルの格差は生まれない。だから、同じ地元の公立高校に行きなさいという強烈な運動だった。
私は、クラスの中ではもう本当に居場所がなかった。クラスの空気になじめず、集団行動が全くできない私はつまはじきものだった。それを15歳時点でわかっていたから、進学校に行って、まずいい大学をめざしたい。いい大学に入れば、進路が広がる。集団行動が全くできない人間も生きていく道を見つけられる可能性が広がる。そう思ったから必死で勉強をしていた。
その思いを先生は汲むことはない。もともと学校になんの希望も持っていなかったけれども、まだまだ地獄は深かったのかと絶望をした。
「先生ですら、私の味方ではないのだ」そう思ったとき、私は猛烈に死にたい気持ちになった。

受験直前に学校で見せられた映画
担任の先生と何度も進路でドンパチし続けた。そして受験直前にホームルームで映画を見ることになった。その映画は「翼をください」だった。
https://www.youtube.com/watch?v=o5ZsXSSiIwc
「君たちは進学校に行かなくたって、十分キラキラとできるんだ」ということを先生は声高らかに話をした。
進学校を目指す人間は虚栄心から目指す。人より上だと言いたいから目指す。そんな気持ちは邪だ。みんな同じ高校で、それぞれ同じ場所で輝けばいいのだと。
正直、これ以上に自分の思いをわかってくれない出来事はその後の人生にない。
私は集団行動ができるかできないかという評価軸の中でカーストの下に追いやられている現状をどうにかしたかった。だから別の学業という評価軸の中で生きる道を目指したのだ。
誰かを見下すためではなく、どうにもならない自分の閉塞感を打破するために勉強を必死でやってきたのに。先生は、どうして、そのことをわかってくれないんだろうかと本当に涙が止まらなくなった。
そんなことを今日、桜を見ながら思い出した。
「15の春を進路格差で泣かせてはいけない」という先生の思いが私のこころを思いっきり泣かせていたことを。
結局私は希望の進学校を合格し、本当にいじめられっ子生活からおさらばした。勉強ばっかりだったので高校が楽しかったというわけでもなかったけれど、地獄ではなかった。それだけでも私は本当に心が救われた。
今年40歳。もう四半世紀も前のことだ。今はもう地元集中運動は存在していない。
著者の大西 明美さんに人生相談を申込む
著者の大西 明美さんにメッセージを送る
著者の方だけが読めます


 LINE
LINE