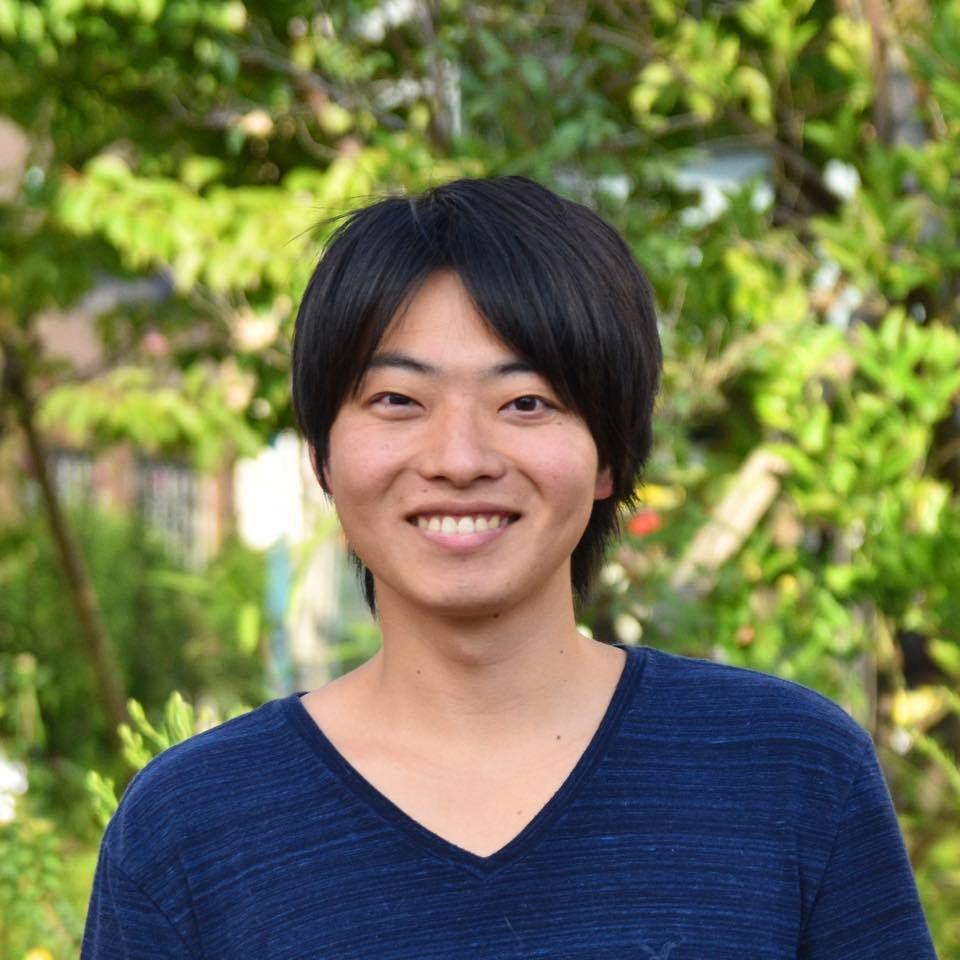輝かしくも灰色だった高校時代、涙とともにさようなら
迎えた2008年4月。湘南工科大学附属高校(以下:湘工)に入学し、水泳部に入部した。
この高校は普通科や特進コースなどの他に体育コースがあり、各部活動で推薦で入学をするスポーツのエリート達が集まっていた。ボク達の代は2クラスあったが3年間クラス替えはなし。まさに仲間意識・共同体感覚が否が応でも強くなる3年間が幕を開けた。それと同時に初めての部活動生活もスタートする(中学校は水泳部がなく大会の時だけ先生に引率の同行をお願いしていた)。
新入生を交えて先輩達との最初の顔合わせ、教室に入りミーティングが始まる。
「これからミーティングを始めます。」
『しますっ!!』
統一された返事、教室内に緊迫した空気が解き放つ。新入生のボクらは圧倒された。昔のスポ根よりはマシかも知れないが、それなりに厳しいルールや先輩もいたりして「全国で勝つための集団」という感じだった。
「我々が目指すのはインターハイでの総合優勝。ここしかありません。各自が自分の目標とするタイムを一つずつクリアして、夏までに準備を整えて行きましょう。」
『はいっ!!』
「それではミーティングを終わります。」
『したっ!!』
たまたまなのか運命なのか。ボクら同期は各種目で全国トップクラスの選手が集まっていた。小学生の頃からしのぎを削ってきて、大会では毎回のように顔を合わす気心の知れたメンバーだった。これだけのメンツが一つの高校に集まるのは珍しくまさにオールスター状態だった。一個下の代は「上が強すぎて試合に出られないかもしれない」と考え、別の高校にあえて進学をするという選手もいたそうだ。全国にある強豪校では日本中から速い選手をスカウトするという高校もある中、湘工は地産地消、一部東京から通うメンバーもいたが殆どが神奈川県出身のメンバーだった。
一年生は朝、授業が始まる前に早く学校に来て部室の掃除をすることが部のしきたりになっていた。ここで同期の男子8人、みんなでふと話し合う。
「なぁ、おれらの代で3連覇したらさ、最高じゃね?」
「いや。。それもし出来たら鬼ヤバいね!」
インターハイのシステムはポイント制になっていて、出場した選手の順位が高い順に点数が割り振られ、その合計点が1番高い高校が団体としての優勝を決めるというものだった。つまり一人だけ速い選手がいる高校よりも、どれだけ多くの選手が決勝まで進み高得点を狙えるかが重要で、チームとして各々がいかにレベルの高いレースをできるかが優勝するために必要不可欠だった。
今でも昨日のことのように鮮明に覚えている。この時のこのやり取りが自分の唯一と言ってよい心の支えになるだが、高1の入学当初の時点でそれはまだわからなかった。
誰が出る?
「一つの種目に対し、各高校から出場できる選手は3人まで」
高校の試合ではこのようなルールが決められていた。例えば100m自由形という種目の中では、一つの高校から3人までしか出場できないということ。これがレギュラーと控えを分けるものだった。100m・200mバタフライがボクが出場できる種目だったが、当時バタフライに出場しようとする選手の枚数は多く、自分も含め5人選手がいた。
持ちタイムの速い順からレギュラーを確保でき、うち2人は出場することはできない。ボクはちょうど3番手に位置していたが4番手5番手の選手とは殆ど差がなかったため校内レースを実施し、そこで出たタイムで残り一枠を決めることになった。
FUJIWARAの原西のように一発ギャグを一兆個くらい持っていたチームのムードメーカーと、文化祭の当日でも暇な時間に部室で腕立て伏せとか始めちゃう超絶ゴリマッチョな一個上の2人の先輩だった。結果ボクの持ちタイムを越えることは出来ず、先輩を蹴落とすような形で3番手としてレギュラー入りを果たした。
高校は各都道府県で予選会を通じ、各種目の上位8名が関東大会への出場権を獲得できる。そして関東大会でインハイの参加標準記録を突破しはじめて全国大会出場への道が開かれる。梅雨真っ只中の6月、初めての県高校を迎えた。レースに出場すると100m・200mバタフライ共に大沈没。元々200mは苦手で見込みはなかったが、100mも全中で出したタイムより2秒以上遅いタイムだった。
中学までは結果が出なかったとしてもちゃらんぽらんしていられたが、自分の成績がチームの成績へと直結する高校の試合ではそうはいかない。何より先輩2人は出場したくてもできなかったという中で1年坊主がやらかしてしまった。冷や汗と申し訳無さが止まらない。中学上がる時に感じていた「追われる苦しみ」なんて・・・なんて甘ちゃんなことを思っていたのだろうと痛感した。チームの役に立てない、力になれない、これ以上に苦しいことはなかった。
ボクの成績とは裏腹に、8月のインターハイでチームは男子総合優勝を果たす。湘工では通算3度目の団体での優勝だった。あれよあれよという間に高校1年目の夏が終わってしまった。
中学からこの時にかけて、クラブ内で顕著に表面化してきた「コーチ選手間のコミュニケーション不足」や「練習や取り組みに対する不平不満」に加え、更なる問題が噴出してきていよいよヤバいぞということに拍車がかかってきた。JOに出場している時にEくんが表彰台が狙えそうなレースの予選前に突然お腹が痛くなりトイレに籠もっていたら招集漏れしてレースに出られなかったり、先生自身がそこそこ大事な大会のエントリーをし忘れ、大会に出場すらできず「あれ?何のために練習してるのボクら?」状態になったり、とにかくありえないような奇怪現象とも思えるミスをチーム全体で連発するようになっていった。
「ちょっとさ、あのクラブヤバくない?」
この噂は徐々に広まっていき、他クラブの人たちからの目が変わっていくのを感じるようになる。冬に差し掛かるある日、ある辞令が通達された。
「選手コースのコーチ変更」
幼稚園の時からずっと一緒にやってきたW先生から、他系列店に所属しているO先生というコーチが移籍してきてコーチを変更するということだった。寝耳に水だった。しかしこの体たらくな状態はクラブ全体でも大きな問題として上がっていたそうで体制変更せざるを得なかったのだろう。
他の仲間はどう思っていたかわからないが自分にとっては大きな衝撃を受けた。このまま高3までは確実に一緒にやっていくものだと、なにより10年以上どんな時も一緒にやってきた先生と選手という関係がこんなにも突然終わりを告げるのかと、呆然とするしかなかった。その驚きと同時に「このままだと3年間何も出来ずに終わってしまうかも」という危機感と恐怖感もあったので新たな環境を迎えることは悪くないかもしれない、とも思えた。
複雑な気持ちでもやもやしながらも、4月からの体制変更の前にクラブ内で説明会が開かれた。
「えー、◯◯からきたOです。今まではW先生のもとでやっていたかと思いますがー、聞く所によるとだ〜いぶ甘い感じでしたので、私はそうはいきません。すべて以前とは変えます。今は週8回の練習ですが11回に増やします。1回でも練習に参加出来ない人は辞めてください。例外は認めません。」
O先生はこの時から遡ること10年前に一番上のクラスを担当していて、インターハイで優勝する選手を輩出しているベテラン名コーチだった。絶対的な指導に対する自信と自負を持っているような話し方だった。
新体制
こうしてW先生はクラブを去っていく。最後はこうもあっさりかと思うくらい、悲しんだりする余韻と余裕はなかった。
新体制がスタートしていく。O先生の指導はW先生の指導とは180度違ったやり方だった。完全なるトップダウン、ひたすら練習量を課し週11回の練習が始まった。月曜日の朝と夜・火曜日の朝と夜・水曜日の朝と夜・木曜日はOFF・金曜日の夜・土曜日の朝と夜・日曜日の朝と夜。今やれば完全に過労で死んでいようことも高校生はすごい。必死になりながらでもなんとかできてしまう。
練習中では「歯を食いしばっていけぇ!」がよくプールサイドに鳴り響いた。「歯を食いしばったらどうやって呼吸するの?頭悪いのかな?」としか思えなかったがスポーツ界の雰囲気では圧倒的屁理屈な考えで、悪はボクの方だった。
「あのさぁ〜、文句があるんだったら、結果を残してからにしてくれます〜?そしたら何でもしてやるよ!」
「お前のそれが全力かよおい!なめてんじゃねぇよ!ばぁああかぁ!!」
セクハラパワハラが叫ばれる昨今ではあるが、当時こんなのは日常茶飯事でボクと後輩のRくんは特に”標的”として集中砲火を浴びせられていた。O先生は恐らく叱咤激励からボクらを奮起させようとしていたのだろうが、怒られると異様に萎縮する性格と、気合や根性論よりも何をどうやればどうなるのかの理論理屈(若しくは根性論でもギャグ要素高めであればOK)で指導してもらいたい自分の思考が、相性の悪さを感じさせた。
とはいえボクも変わらなければいけない。このままでは何もできない。そういう考えもあったのでとにかくこのやり方に慣れようと必死になって食らいついた。
2009年6月、2回目の県高校を迎える。全中決勝以来約2年ぶりに自分の自己ベストを0.1秒更新した。高校2年でも関東高校にすら進めないしょぼすぎるものだったが「あぁこれでなんとか怒られれずに済むな」とほっとして上に戻っていった。梅雨の時期、外では雨が降り続く中、会場内にもカミナリが降り注ぐ。
「おーい、おい!!!おぉぉぉいいいい!!!!!」
身体が築地であがったマグロのように硬直する。
「お前こんなんで許されると思ってんのかぁ?よくもオレの顔に泥を塗ってくれたなぁおい!!どうしてくれんだよ?どうすんだよ?おい!!!」
どうすんだよ??何を言っているのか…自分は1ミリもふざけず真剣に全力を出し切って、確かに結果は満足出来ないけど持てる力の全てを出し切ったのになんで怒られてるの??混乱しかなかった。
「わかりません。。。」
「わかりませんじゃねーよ!丸坊主じゃすまされねーぞお前よぉお!」
「。。。。」
「明日の練習までにどうするか考えてこい!誠意見せてこい!!!ふざけやがって!!!バカじゃねーのかお前ら…いいな!わかったかよ!?」
「・・・はい。。。。」
とりあえずボクと先輩のHさんは頭を5厘刈りにし、全面的にボクたちが悪い、申し訳ないですという稚拙な反省の弁を述べた。なんとかその場は納得してもらい練習へ戻るも、この日を境に何かが自分の中で崩れ落ちた。
「オレの顔に泥を塗ったってどういうこと?ボクは先生の面子を保つための道具?」
「自己ベストを更新して怒鳴られるなら、これ以上ボクは何をすれば良いの?」
「なんで坊主にすると許されるの?逆にナゼ?誠意ってナニ??」
自分が出場することで試合に出られなかった先輩には会わせる顔がないくらい申し訳ないし、入学する前に高校3年間は本気でやると誓ったけれど、もう頑張ることを止めよう…そう決意した。今まで張っていた糸が切れるように、完全にバーンアウト(燃え尽き症候群)した瞬間だった。
その日から「どう手を抜いて高3の引退を迎えるか」がボクの頭の中を支配する。水泳を辞めて退部するとスポーツ推薦で入学しているので高校も退学することになる。ここまで来てそれはできない。かといってもう頑張ることはできない。行き場のない地獄の日々が始まった。この時の自分は物の例えじゃなく無味無臭の世界が広がり、全てが灰色に見えていた。
オワリを数える日々のハジマリ
個人的な状況とは打って変わり、チームは全国で大暴れし爆進していた。
2009年のインターハイは大阪で開催され、男子の自由形種目は全て湘工の選手が優勝するという快挙を成し遂げたのだ。ボクはそれを練習の合間に自宅からテレビで見ていた。インターハイの最終レース・花形種目でもある800mフリーリレーを取り、レース後インタビューに答える選手たち。みんな笑顔で楽しそうで、ちらっと映る応援席も皆一致団結している。眩しかった。同じチームに在籍しているとは思えない心境になった。
「こんなにもみんな輝いているのに、自分は何をやっているのだろう・・・」
心が引き裂かれる。チームの一員であればもちろん喜ぶべきことなのだが、ボクはとてもじゃないがそんな精神状態にはなれなかった。チームは見事団体2連覇を達成。その中でも自分は相変わらず死んだ魚の目で練習に向かっていた。そういう腐り果てた日々が続くといい加減O先生も呆れ果ててしまう。
「うちでちゃんとやれないなら邪魔なので消えてくれない?お願いだから。M先生と話しして学校で練習した方がいいんじゃねーのか?とにかくうちにはいらないから話してきて下さ〜い。」
水泳部監督M先生へ相談しにいく。「学校練に切り替えてもうちは構わないよ」と。環境を変えればまた気持ちも入れ替えられるし、みんなからも刺激を貰えるから。でもそれもボクにはできなかった。もう頑張れない以上、全国大会で良い成績を残すために前を向いて必死に頑張っているチームメイトに迷惑はかけられない。ボクのような腐ったみかんがその場にいるだけで悪影響を与えてしまう。そう思い込んでいた。
あまりにも見るに見かねて我慢できなかったのか、スイミングクラブの同期女子2人に呼び出された。
「悠生さ、もうあたしたち高3になるんだよ。1番上だよ!このままでどうするの?後輩のお手本にもなれないし、何より悠生自身このままで終わっていいの?」
「…………。」
「ねぇ。聞いてるんだけど!」
「いや、その………。」
著者のYuki Sakaiさんに人生相談を申込む
著者のYuki Sakaiさんにメッセージを送る
メッセージを送る
著者の方だけが読めます


 LINE
LINE