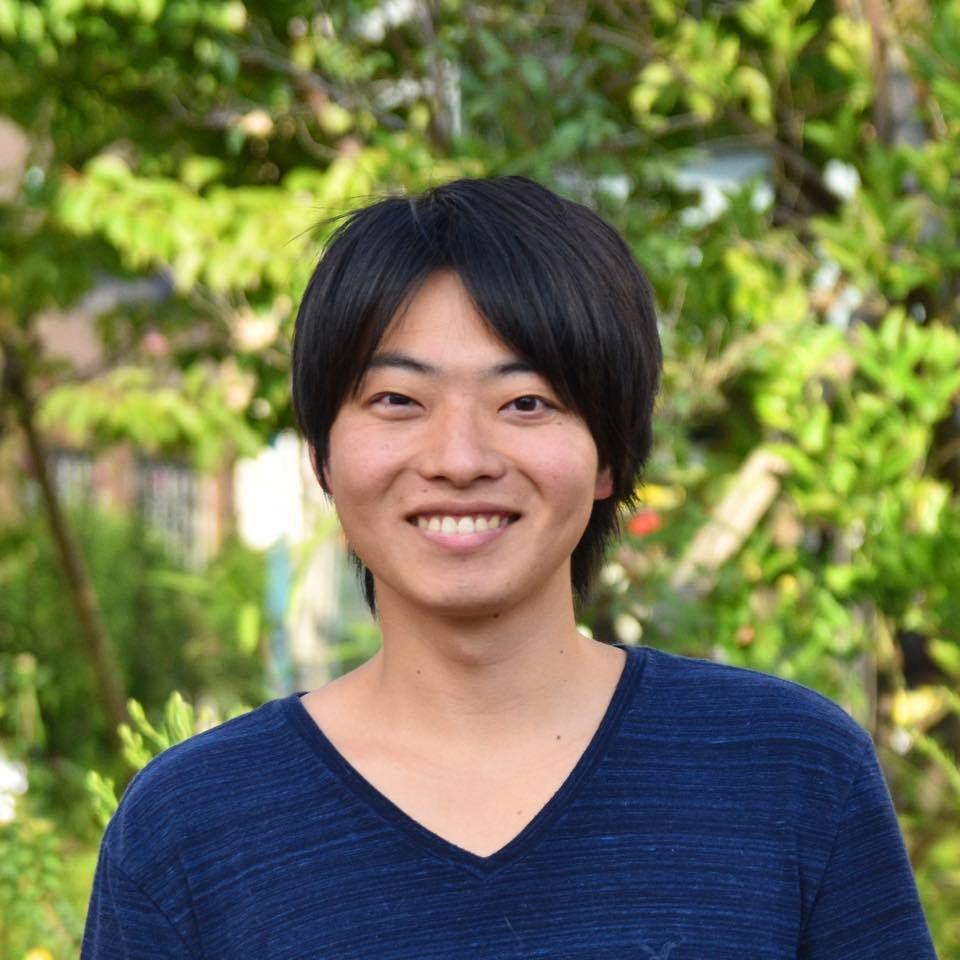輝かしくも灰色だった高校時代、涙とともにさようなら
「なに!?!?」
「もう・・・頑張れないんだ。」
「意味わかんない!それで終わっていいの?」
「よくないけど。。」
なんとも惨めなものだった。せめてもこの高校の片隅に在籍することを許してもらうには何か存在できる理由をつくらねばと思い、それまで大っキライであった勉強もそこそこちゃんとやり学内では良い成績(といっても偏差値40に満たないスポ科の中で)を取っていった。
O先生からは匙を投げられ、M先生の救いの手も振り払い、同期女子からはブチギレられる。もう水泳をやってきたこと全てをなかったことにしたい。どこか遠くへ流れていって、自分の存在をみんなの記憶から消し去りたい。自分の殻に閉じこもりひたすら闇に飲み込まれていった。
ある日練習に向かう途中、買い物帰りの母とチャリですれ違う。母が止まり、ボクを止め、驚きのことを口にする。
「悠生、あんたもう、練習行かなくていいよ。」
「は?何言ってんだよ」
「このままじゃあんた、おかしくなっちゃうよ…」
「意味わかんねーこと言うなよ・・・もう遅れるから行くわ」
サボったりいい加減な行動をすることに厳しかった母が、母の方から休めと言ってくる。意味がわからなかった。足止めを振り払って「ヤバい、遅刻したらまた怒られる!」とダッシュで練習に向かった。ボクの原動力は「どう逆鱗に触れず、かといって頑張ることもせず、終わりの日を迎えるか」それだけを考え練習していた。
何のために練習をしているかなんてことは重要ではなく、事を荒らげずにささっと終わりたい。それだけだった。なんでそれを続けるの?と傍から見れば思うのだろうが、この時は「それでもやらなければいけない」洗脳意識が自分の身体を突き動かしていた。
県高校まであと〇日、練習はあと〇回。あと〇回やれば全てから開放される。ちょくちょく精神がおかしくなって同級生の仲間を誘っては江ノ島の岩屋に行き海を眺めて黄昏れたり、授業中や休み時間に突然奇声をあげたりなど、所々要所で逃避行動に走りながら一日一日が早く終わることを願うように。
ついに高3の6月、最後の県高校を向かえた。
すべてのおわり
100mバタフライ。ゴールタッチし、電光掲示板を見上げた。
59.4秒。3年前の全中の決勝の時よりも遅いタイムだった。結局高校3年間ではただの一度もインハイには出場すら出来なかった。努力というのはただやればよいというものではなく、明確なゴールとビジョンの元そこへ到達しようとする健全な精神状態と意志、限界を超えた取り組みや行動を持ってはじめて実る可能性が生まれるものだと、全てが終わったあとに気付くことになった。
プールから上がり一礼する。荷物を持ってサブプールに向かうと同じクラブの仲間や水泳部の後輩が号泣していた。
「なんでお前らが泣くんだよ。。」
彼らはボクが苦しんでいることを身近で見ていてよく知っていた。小学生の時に背中を見て憧れていた”高校3年像”と、無残で哀れな自分の姿とのギャップにいたたまれない気持ちになった。彼らの表情を見て自分もヤバくなったのですぐさまサブプールに飛び込んだ。最後を噛みしめるようにこれ以上なくゆっくりダウンする。プールから上がるとO先生のもとへ最後の挨拶をしに行った。
「終わりました。今までお世話になりました。ありがとうございました。」
「うん、おつかれさん。」
それだけを言い残し去っていった。上の観覧席に戻るとかつてお世話になったW先生が立っていた。最後のレースを観に来てくれていたらしい。なにか励ましの言葉をかけてもらったようだったけど何を言われたのか全く耳に入ってこなかった。ひたすら涙がこぼれ落ち何も話すこともできず、ただその場で立ちすくむ。
これまでの自分の人生のすべてであった代名詞を捨てる日。いつかくると思っていて、むしろそれを願っていたけどいざその日を迎えると表現し難い感情が自分を包み込んだ。
栄光と挫折、両極端の橋を渡って辿り着く。涙にまみれたボクのすべてが確かに終わりを告げたのだった。
夏の締め括り
県高校が終わり次の日の朝、目が覚める。快晴だった。起きてふと外を見つめ、徐々に実感が湧き出てくる。
「あぁ、、そうか、もう終わったのか。。。」
「おれの人生。 終わったな。」
若いくせに何を言うかと激を飛ばされそうだが、この時滲み出るようにそう思った。そう、紛れもなく自分は終わったんだ。その日から練習に行かなくなった。朝練も行かなくていいのでゆっくり起床して学校に行って、チンタラ脳天気に授業を受けてチャリで帰る。帰宅途中、小田急鵠沼海岸駅近くのファミマでジャンプやサンデーを立ち読みし、家に帰っても貪り漫画を読み続ける日々。ルフィとナルトのメンタリティにめまいがする。数日、数週間かけて、現実を受け止めていった。
自分自身は引退してもチームは止まらない。迎える夏のインターハイ、高校3連覇をかけた戦いが待っていた。
一旦ボクの今までのことはすべて忘れもう開き直るしかない。最後くらい、少しくらい、このチームの役に立ちたい。ここからは完全にサポートメンバーとしてチームを支える立場になった。同じサポートメンバーの後輩1・2年には「お前ら、来年は絶対選手で出ろよ!サポートする側はこれで最後だからな!」と、ボクが高1の時に先輩から言われたことを今度は彼らに託した。
サポートメンバーは、マネージャーが行う仕事の補助に加えメインは選手の応援。声のデカさだけは誰にも負けなかったこともあり「いよいよお前の本領を発揮するときがきたな」と笑われながら会場へ到着する。2010年のインターハイは沖縄で開催され屋外のプールで強い日差しが肌に突き刺さる。南国特有の突然のスコールに見舞われ、汗なのか雨なのか何で濡れているのかわからないが、そんなことは気に留めることもなく準備に取り掛かった。
会場のスタンドと控え場所の場所取り、チーム備品の荷物運び、控え場所からサブプール・メインプールまでの移動距離をみてどのくらい時間がかかるか確認する。選手用のスポドリの粉を水と混ぜて作り、ウィダーやカロリーメイト等の補助食品がどこにいくつ必要なのかそれぞれの場所に設置。マネージャーの手が回らない時はウォーミングアップでは選手のタイムを図ったり、スタンドからレースのビデオ撮影をする。挙げればいくらでもある仕事をみんなで役割分担して一つ一つ順序立てて取り組んでいった。
徹夜で会場の前にシートをひいて会場入りを待つ。アブや色んな虫と戦いながら選手が最高のパフォーマンスを発揮できる準備を整えていった。
「〇〇のレースがこの時間にあるからこれとこれは用意して!あと部旗は絶対一番目立つところに張るぞ!」
『はいっ!!』
「ウィダーいくつ?〇〇は?」
「おい!〇〇ねーじゃねーか、動けよ1年!!」
『はい!!!すいませんっ!!!!』
まるで新卒1年目とワンマン上司がいる激烈ベンチャー企業のようなやり取りが飛び交い、選手自身も戦っているがこっちはこっちで色んな戦いがあった。水泳は個人競技ということからあまり理解されないのだが、この時の湘工水泳部は各々の役割がしっかりと割り振られ組織化されており、一つのチームとして動いていた。
そんなボクらの誰にも知られることのない裏の努力の甲斐もあってか、4日間の激闘の末に湘工は首位をキープしながら最後の800mフリーリレーを迎える。2位チームとの差は殆どなく、どちらかがこのレースに勝った方が男子団体総合優勝を決められるというドラマのような脚本が仕上がっていた。
インターハイの最終レース、笛の音がなり選手がスタート台に上がる。これまでの3年間、いや13年間の思い出が走馬灯のように蘇る。このレースが多分本当の最後。顔は既にぐちゃぐちゃだった。
「みんな・・・がんばれ!」
約7分半に及ぶ時間はこれまででもっとも遅く刻が流れていった。
ありがとう
このレースを見事に勝ちきり、ボクらは高校3連覇を達成した。
“ボクらは”なんて言っていいのか。お前最後だけ調子よくねーか?あんなに死んでたくせに自分はチームの一員になれていたのか?今でも全く自信はない。でもあの時に部室で語り合ったことが間違いなく現実となったんだ。
「なぁ、おれらの代で3連覇したらさ、最高じゃね?」
間違いなかった。最高だった。
自分がどうだとか、もうそんなことはどうでもよくなった。みんなでこの瞬間を3年間目指してきて本当に掴み取ったのだ。なんて凄いやつらなんだろう。もちろん同期だけでなく先輩・後輩の力もあってこそ。心底凄い仲間達を持ったと恐れを感じるほどだった。
だがあの時の話を後になってすると、皆それぞれで苦しみを抱えていた。チーム内、先輩後輩、選手とコーチ、男女、各個人同士、それぞれで確執なり問題なりを抱えていて、最高の結果をチームとしては収めたがそれなりに苦しいものだった。
特別なことを、誰かと違うことをしようというのは痛みが伴うことなのかもしれない。良し悪しでは語れない、その範疇を越えてただただチームが全国で1番になる。そのためだけに選手、サポートメンバー・マネージャー・コーチ・トレーナー・家族、皆が一つになった。
「気に食わない」「納得できない」「あいつがキライ」「理不尽」日々負の感情に苛まれることもあったが、たった一つの目標だけをみて各々の役割を遂行しようとする意志の結晶。チームとは何なのか、言語化できないがその本質のようなものを見た気がした。
。。。。。。
あれから9年余りが経つ。
銀行マンや保険の営業マンになったやつ、幼稚園の先生になったやつ、飲食店を何店舗も経営する実業家になったやつ、ミスタージャパン(!?)になったやつ、皆それぞれの道を歩んでいる。
今や同期の結婚式くらいしか集まらないがそんなんでいいと思っている。彼らがどこで何をしていようとも別に何も変わらない。あの時の想い出は、忘れたくても忘れることができない。元気でいてさえいれば、たまに何してるのか耳に入ればそれだけでいい。
あまり面と向かっては言えないが、いつも思っていることがある。
ありがとう。
こんなクズを仲間でいさせてくれて。
彼らがいなければ確実に途中で折れていた。いや、実際は折れていたんだけどなんとか繋ぎ留めてもらいながら引っ張ってもらいながら、やってこれた。
タレントの上地雄輔さんが「高校時代に戻ってまた松坂選手とバッテリーを組みたいですか?」という質問に「いえ、1億積まれても戻りたくありません。あの3年間は何にも代えがたい宝物です。」とテレビで言っていたのをたまたま見たことがあったが、その気持ちがよくわかる。二度とあんなに辛い想いはしたくない一方で、誰もが経験できるわけではない最高の体験を皆から与えてもらった。
濃すぎるほどに濃密で、ただただ苦しく泣きじゃくるも、人生で最も得難い経験をした3年間だった。
 もれなく全員アホだけど、最強で最高な同期たち
もれなく全員アホだけど、最強で最高な同期たち
追伸:
私が経験したような選手としての炎が消えることは、日本のスポーツ界では珍しいことではありません。きっかけや経緯は様々ですが、後に大学でスポーツコーチングを専攻し、多くのアスリート達との話を通じその状況を理解しました。この話を書いた経緯としては偶然の出来事ではありましたが、私の過去を蒸し返したいわけではありません。未だに声なき声として埋もれている”弱き立場”の選手がいるということ、似たような経験を通じ自分が行ってきたスポーツを嫌いになって辞めてしまう選手がいること。私の持つ影響力はほんの微々たるものかもしれませんが、少しでもこういった現実があることを知るきっかけとなれば幸いです。日本・世界中の全てのアスリートが自身の競技結果を問わず、幸せで有意義な選手生活を営める環境作りがなされることを私自身、切に願っております。
著者のYuki Sakaiさんに人生相談を申込む
著者のYuki Sakaiさんにメッセージを送る
メッセージを送る
著者の方だけが読めます


 LINE
LINE