CO₂から資源を生み出す。新たな電極材料開発に挑んだ東京理科大・寺島教授のストーリー

2050年までのカーボンニュートラルの実現に向け、さまざまな取り組みが行われています。CO₂排出量削減のため、燃焼時にCO₂を排出しない水素などの非化石エネルギーへの転換が進んでいます。しかし、水素はエネルギー密度が低いことから、航空機や船舶、大型トラックなどの燃料の水素化は、技術刷新がない限り、今後数十年は難しいと考えられています。
そこで、水素転換が難しい領域における切り札として注目されているのが、大気中のCO₂を回収して有用な化学原料へと資源化する電気化学プロセスです。
東京理科大学の寺島千晶教授は、CO₂を還元して、合成ガスの原料となる一酸化炭素(CO)と水素を同時に、かつ利用に適した比率で生成できる新たな電極材料を開発し、2023年8月に発表しました。今回は、研究の内容やその裏側のストーリーについて寺島教授にうかがいました。

CO₂の回収と資源化を同時に目指す試み
——CO₂から資源を生み出すというのは一石二鳥で非常に魅力的に感じますが、まだ一般には普及していません。実用化・普及にはどんな課題があるのでしょうか?
CO₂は有機物が燃えた(=酸化した)最終形態なので、非常に安定な物質です。そのような物質を元に戻す、つまり還元させるためには、多くのエネルギーが必要となります。
CO₂を還元して有用な資源に変換できたとしても、そのために多大なエネルギーを使っていては本末転倒です。火力発電で作られた電気など、CO₂の排出を伴う方法で生成したエネルギーを用いると、トータルで見るとCO₂排出量の方が大きくなってしまうのです。
つまり、究極的には、CO₂還元技術を実用化するためには、そのために必要なエネルギーを太陽光のような自然エネルギーでまかなう必要がある、ということです。これは非常に難しい課題です。
——なるほど。電気化学プロセスを利用すると、それが可能になるのですか?
将来的には、その可能性はあると思います。私も以前は、自然エネルギーのみを利用したCO₂還元技術開発を目指し、ダイヤモンド半導体による光触媒の研究を中心に行なっていました。

しかし、気温上昇に歯止めがかからず、『気候危機』とも言われる今、気候変動への対策は待ったなしの状況になっています。ダイヤモンド半導体による光触媒技術は学術的には非常に価値がありますが、喫緊に実用化を行うには、自然エネルギーのみを利用した手法を脱却する必要があると感じました。そこで、電気エネルギーによる電解還元法に着目し、そのための新たな電極材料の研究開発に取り組みました。
安価かつ安定な酸化チタンに着目
——今回の研究で開発された電極材料は、これまで寺島教授が研究されていたダイヤモンド電極とどのような違いがありますか?
反応させる面積が格段に広くとれる点が、一番大きな違いです。
ダイヤモンドは材料としては非常に優れた特性を示し、理想的な材料なのですが、プラズマによって合成しようとするとどうしても平面状にしかコーティングできないという課題がありました。粒子状のダイヤモンド電極が開発されれば理想的ですが、まだ研究開発途上で実用化はまだだいぶ先になるでしょう。
そこで今回、平面ではなく三次元的な構造を持ち、反応面積が大きな電極材料を開発しました。
——どのようにして反応面積の大きな電極材料を作ったのですか?

液中プラズマ処理後の酸化チタン
ポイントは酸化チタン粒子でした。
CO₂還元はAg触媒で行われますが、そのAgナノ粒子を付ける母体として酸化チタンを活用したのが今回の研究です。
これまでに、導電性カーボン粒子を積層した電極によって高い電流密度でCO₂還元できたとの報告があり、粒子を積層させることで三次元構造ができ、優れたCO₂還元能を示すことはわかっていました。
しかし、実用化には電流密度だけでなく、安定して長期間作動することも重要です。電流密度が高いということは、そこでの反応がものすごく進むということを意味します。つまり、電極材料にとっては過酷な条件と言えます。カーボンのような柔らかい材料ではもたないと、直感的に感じました。
そこで、光触媒の材料として既に産業でも使われている酸化チタンに注目しました。酸化チタンは安定性が高いことに加え、とても安価な工業材料であることも、実用化を考えると魅力的でした。

——光触媒の材料としての実績もある上に安価となると、理想的な材料に思えます。これまで酸化チタンがCO₂還元電極の材料として使われてこなかったのはなぜでしょうか?
酸化チタンは本来、半導体材料で、光が当たることで励起して光触媒として機能します。光電気化学材料ではあっても、電気化学材料ではない、ということです。そのため、なんらかの処理をして、電気の流れる材料に仕上げなければならないという大きなハードルがあったのです。
キーワードは「液中プラズマ処理」。異なる環境に身を置いて掴んだヒント
——どのようにして酸化チタンに電気が流れるようにしたんでしょうか?
液体の中でプラズマを発生させる「液中プラズマ処理」を施しました。
プラズマは気体分子が電子と陽イオンに分かれた状態を指す用語で、固体、液体、気体につぐ第四の物質の状態です。高いエネルギー状態にあるのがプラズマの特徴で、プラズマを利用することで、物質の表面にさまざまな機能を付与することができます(プラズマ処理)。通常、プラズマ処理は気体中で行いますが、液中で行うことによって(液中プラズマ処理)、気体中とは異なる性質を付与することができ、今回はそれを利用しました。
液中プラズマ処理をすることで酸化チタンに酸素欠損を導入できることをすでに報告していたので、この酸素欠損により導電性が発現させ、電極にできると目論見ました。

——液中プラズマ処理……、素人目には何だか難しそうな技術ですね。
実は私自身も、もともとプラズマに興味があったわけではありませんでした。
2010年から2年ほど在籍した名古屋大学の高井治教授と齋藤永宏教授の研究室(当時)で、液体の中でプラズマを発生させる研究に初めて触れ、それが大きな転機になりました。
液体の中でプラズマが発生する反応機構の構造や条件を模索するところから始まり、発生したプラズマの特性を理解して応用に結び付けるという一連の研究を肌で感じることができ、大きな衝撃と刺激を受けました。その経験が今回の研究では大いに役に立ちました。
予期せぬ結果は失敗ではなかった。試行錯誤の末、一度の反応でCOと水素の生成に成功
——今回の研究で、一番苦労したことは何ですか?
液中プラズマ処理をした後の酸化チタンに、プラズマ発生用電極のタングステンが微量に付着していたことです。これは不純物にもなりますし、意図した材料合成が行えなかったことを意味するので、非常に困りました。
ところが今回発表した論文の筆頭著者である高木海君(博士課程2年生)が実際にCO₂還元の実験を行ってみると、予想外に良い結果が得られました。これは、CO₂還元と同時に起こる水還元による水素発生を抑制したためと考えられました。結果的には、一度の反応で、合成ガスに最適な比率で、COと水素を生成することができるようになりました。
これは、高木君がさまざまな条件で実験を繰り返し、粘り強く努力したからこそ得られた成果です。指導教員としてとても誇りに思います。

——本来好ましくない反応が、逆に予期せぬ良い結果につながったのですね!
実はもう一つ、うれしい誤算がありました。
通常、高温で処理すると酸化チタンは焼結して、粒子同士が引っ付いて大きな塊を作り、表面積が小さくなってしまいます。しかし、液中プラズマ処理では、液体の沸点以下の温度で処理できるので(今回の場合100℃以下)、ナノ粒子の酸化チタンはそのままの形状を維持することができました。表面積の大きな電極を作るという点においても、液中プラズマ処理が有効に作用しました。

液中プラズマ処理後の酸化チタンナノ粒子を電子顕微鏡により観察(挿入図はナノ粒子の写真)
実用化を見据えた電極触媒開発に手応え
——今回の研究の意義を、改めて教えてください。
CO₂還元技術では、1. 効率よく還元すること、2. 使いやすい還元物質を生成すること、の2点が重要です。今回の研究は主に2.に貢献できる成果で、合成ガスの原料として実際に化学プラントで使われているCOと水素を同時に、そして、合成ガスとして反応させるのにちょうどよい比率となるように生成できた点が意義深いと思います。
酸化チタンという安価で安定で、産業化にも実績のある材料を母材とした電極触媒を開発できたことも、実用化を見据えた優れた点と言えるのではないでしょうか。

——今回開発された技術の応用に向けて、どのような課題がありますか?
一つには液中プラズマ処理のコストです。
酸化チタンが安価な材料とはいえ、処理コストが高額だと、総合して工業化に適さない材料となってしまいます。現在、液中プラズマ処理装置を電源から含めて一から見直し、その装置開発をある民間企業とともに行っています。
もう一つの課題は、CO₂還元能力をより向上させるための触媒開発です。
今回はこれまでの報告例を踏襲したAg触媒を付けましたが、よりCO₂還元に適したAg触媒のサイズや形態、またはAg以外の触媒との組み合わせが必要となります。
※本研究についてより詳しい内容を知りたい方は下記リンク先をご参照ください。
https://www.tus.ac.jp/today/archive/20230905_6249.html
鮮やかな色を生み出すパレットのように
——研究の今後の展望や目標について教えてください。
東京理科大学の学生や研究者は、さまざまな特質を持った人たちがいます。その集まりをあたかも絵具のように混ぜ合わせて、これまでにない素晴らしい色合いを出せるようにしたいと考えています。研究室はそれを具現化する場だと考えています。

研究室で取り組んでいる研究テーマは大きく、「プラズマ」、「材料」、「SDGs」の3本柱となっています(図)。前職の名古屋大学高井治研究室にて、プラズマや材料科学を学ぶ機会がありました。それまでの研究では、機能性材料としてダイヤモンド電極の機能発現などを探求し、分析化学分野への応用を模索していました。東京理科大学に移籍してからはそれら研究分野を継続しつつ、持続可能な社会につながるような技術開発に取り組んでいます。
さまざまな技術を融合し、パレット上でこれまでにない鮮やかな色を生み出すような研究をイメージしています。材料、プロセスを混ぜ合わせ、モノ、コト、そして、人がワクワクと活性化する研究室を目指し、世の中に貢献できる研究を進めていきたいと思います。
「東京理科大学×SDGs」について

東京理科大学は創立150周年を迎える2031年における本学のあるべき姿を描く長期ビジョン「TUS VISION 150」をさだめています。SDGsをはじめとした課題解決にも貢献するこのビジョンの実現に向けた「中期計画」を策定し、達成に向けた取り組みを進めています。東京理科大学はこれからも科学技術の創造による持続可能な世界の実現を目指して、人材の育成、理科大ならではの研究の推進、 研究成果の社会への還元などに取り組んでいきます。
東京理科大学SDGs特集ページ
行動者ストーリー詳細へ
PR TIMES STORYトップへ
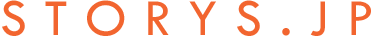
 LINE
LINE
