大ヒット絵本「おさかなちゃん」シリーズのメイキングを一挙大公開! 「編集」という仕事が、“のんびり屋の少女” を“魔法使い“へと変えた。
学研プラス(Gakken)が生み出す、数々の個性的で魅力的な商品・サービス。その背景にあるのはクリエイターたちの情熱だ。学研プラス公式ブログでは、ヒットメーカーたちのモノづくりに挑む姿を、「インサイド・ストーリー」として紹介しています。第7回は、シリーズ累計58万部のヒットとなっている絵本『おさかなちゃん』を手掛けた絵本編集者、北川美映。絵本のみならず、全30巻で累計351万部の『一期一会』シリーズ、累計230万部の『こどもずかん』シリーズ、18巻累計45万部に達した『王女さまのお手紙つき』シリーズなど、児童書でも人気作を手掛けてきたヒットメーカーです。

北川のヒットメーキングの源泉である「編集力」。原石が秘めた輝きを見出し、そのきらめきをヒットにつなげる彼女の魔法「編集力」は、どこで生まれ、どのように培われたのか。その原点には、地味で目立たないけれどもポテンシャルを秘めている、スポットライトの下で輝く前の原石たちへのシンパシーと、真摯で温かな眼差しがありました。
才能、ポテンシャルを、陽のあたる場所へ。もっと輝ける場所へ。

翻訳本を手掛けることの多い北川は、しばしば海外のブックフェアへおもむく。北川が絵本『おさかなちゃん』に出合ったのは、2013年3月、イタリアのボローニャで行われたブックフェアでのことだった。『おさかなちゃん』は、ベルギーを代表する絵本作家、ヒド・ファン・ヘネヒテン氏の作品だが、日本での知名度はまだ低く、その魅力も十分に知られてはいなかった。
ひと目見たとき「あぁ、かわいい絵だなぁ」と、原書の魅力にすなおに感銘を受けた。しかし、次の瞬間には、この本をさらに輝かせるためのアイデアが、編集者北川の頭の中で静かに、しかし渦を描いて流れ始めていた。そして確信した。この本は、日本でもっと輝ける、と。
海外で作られた絵本を翻訳出版する場合は、一般的に文章の部分だけを翻訳して出版されることが多い。文章以外のイラストなどは原書の作品性を生かしたままで出版するのが通例だ。一方で、北川が手掛ける翻訳出版は、そうした常識とは異なっている。内容やイラストまで、日本向けにアレンジ(ローカライズ)を行うのである。しかし、先方出版社がこれから大々的に売り出そうとしている新作は、出版する国や地域に合わせてローカライズが許容される幅が、極めて狭いもの。そこで北川は、ローカライズがしやすいよう、あえて発売してから少し時間の経った作品や、目立ってヒットしていない作品を選ぶことが多いという。
「ローカライズにあたっては、原作の出版社や原作者との信頼関係が大前提です。原作出版社Clavis や、原作者のファン・へネヒテン氏は、海外のパートナーのなかでも、最も柔軟で革新的な姿勢を持った相手でした。ベルギー国内ではもちろん原書の形がベストなのだと思いますが、その形だけではなく、日本向けにローカライズする提案に対しても、もうひとつの『おさかなちゃん』の形としてすごくおもしろがってくれています。大きなアレンジにも快く話をきいてくれるので、相談がしやすく、アイデアの幅もひろがりやすいんです」
シリーズ累計で58万部というロングセラーを生み出したマジックは、この翻訳出版のローカライズに隠されている。

「わたしの性格もあると思うのですが、すごくメジャーな作家さんとか、既に売れてるものの別バージョンみたいな本には、はじめからあまり興味が湧かないんです。むしろ、普通だったら目に留まらないような作品を掘り出してきて、日本の読者向けに売れるよう、チャレンジしたい。隅っこにいて目立たない作品や作家を表舞台に紹介したい! という思いが強いです」
まだ世に知られていない、在野にある作品の“ポテンシャル”を見いだすこと。それが、北川の持つ能力のひとつだ。
こうして、ブックフェアで見つけた何冊かの本を携えて、日本へ帰国。帰国後に、すでに人気シリーズとなっていた『一期一会』シリーズを一緒に作ったメンバーに、収穫を共有した。そのなかで、もっとも好評だったのが『おさかなちゃん』だった。北川は絵本の購買層に最も近い、育休明けのメンバーのひとりと、日本での出版に向けて動き出した。
判型、体裁、そしてイラスト…。『おさかなちゃん』日本版ローカライズの秘密とは

『おさかなちゃん』シリーズを日本で出版するための、さまざまなローカライズが始まった。原書では3歳〜4歳くらいだった対象年齢を、0歳〜3歳へと下げた。併せて、体裁を原書よりもふたまわりほど小さなサイズに変更。また、幼児でもページをめくりやすい厚い紙を採用し、ページ表面には汚れに強く、発色があざやかに見えるコーティング加工を施した。
もっともっと、日本の子どもたちに楽しんでもらえるように――。その思いから、原作にはなかったオノマトペ(擬音語、擬態語)の手法を盛り込んだ。キャラクターの特徴を表す言葉や、キャラクターの名前をすべてオノマトペをつかった表現に。日本語に特徴的なこの表現効果を使ったことも、ヒットの一因となった。
今回、2021年の改訂にあたっては、変更はイラスト自体にも及んだ。通常であれば、絵本作家のオリジナリティを尊重し、印刷時の色調整にも最も気を使うカラーリング。それを、原書とはまったく違うカラーリングに変えていく。海藻の紫色を黄色に、砂地のベージュ色も黄色に――。作業は画像編集アプリケーションのAdobe Photoshopを使って進められる。
色使いの多い画面が、黄色の統一感を持った画面へと変わった。
カラーリングの変更が完了した絵本を見ると、ページをめくるごとに、青系の世界から黄色系の世界へ、そして赤系の世界へと、ダイナミックに変わっていくことに驚く。次々に登場するキャラクターの体の色に合わせて、各ページの背景アイテムや文字の色が、同系色でまとめられているのだ。



ターゲット年齢にした、赤ちゃんから幼児期の子どもは、脳の神経が劇的に発達し、認知能力が育っていく年頃。色調がページごとにはっきりとわかりやすく変わることで、「キャラクターのイメージ=色のイメージ」として認識しやすくなる。その結果、多色づかいにしていたときよりも視点が定まって、じいっとキャラクターをみつめたり、物語の内容に集中できるようになるのだという。これが、おさかなちゃんが日本のママ・パパに支持され、ヒットしている理由なのだ。
「原書では、“カニの色は赤”など、文章で色彩を表現しています。物語を楽しむだけでなく「色の名前」も覚えるという教育的要素を含んでいるんです。ですが、日本版のターゲットとして設定した0歳から3歳には、物語以外の要素まで文に盛り込まれているのは情報過多かもしれないと感じました。そこで、文のなかに色を表す言葉は入れないかわりに、色の違いを目と心で感じ取れるようにする……といった作りにしていきました」
編集は、色だけでなく、イラストのサイズにも。原書や海外版では大きく描かれている主人公のおさかなちゃんを、国内版では、とても小さくして配置した。北川によると、子どもの多くは、物語の主人公を自分と重ね合わせて投影するという。そして主人公は、自分と同じく小さく描かれていた方が、より架空の世界にいる主人公に感情移入しやすいのだと。

「日本ではキャラクター文化が発達しているので、キャラクターとして認識されることや、“かわいい”と思ってもらうことには、法則のようなものがあります。でも、原書では、原作者がおさかなちゃんの顔や体の形などを自由に描いていて、ページや巻によってブレが大きかったんです。これらを原作者の監修を受けながら少しずつ調整していきました。例えば黒目の大きさの割合、目の位置などの細部にまで手を入れて、キャラ自体のかわいらしさをより引き出すようにしました」
* * *
こうした細かいローカライズを行うことで、『おさかなちゃん』シリーズは、日本の子どもやママ・パパに愛される代表的な絵本のひとつとなった。原作は現在、28言語に訳されているが、日本語版がダントツで売れ続けている。原作出版社からは「incredible!(信じられない! すばらしい!)」と、称賛の声が届いた。
2021年7月には、読者の意見を集約し、色使いを効果的に使ったページ展開などの人気要素を結集してリニューアルされた『改訳新版 おさかなちゃんの ぴんぽ~ん』『改訳新版 おさかなちゃんの あのね、ママ』が発売となった。

“不器用だった”少女時代への想い
北川は、「世の中の、声の小さな人たちにスポットをあてたい」という思いが強い。ブックフェアの端っこに目立たずに置かれていた『おさかなちゃん』シリーズを日本へ持ち帰ったのも、そうした思いが根底にあるからだろう。
そんな北川に、子ども時代の思い出をきくと「常に学年のなかでは不器用で、ちょっとどんくさいような位置にいたような気がします」と振り返る。
「同級生の間で流行っているものも、自分が手にするのは周回遅れくらい。読み物だったら、なんとかついていけるけれど、雑誌となると1、2学年くらい遅く読み始めるみたいなところがありました(笑)」

そんなのんびりとした性格は、大学生になっても変わらなかった。出版社に就職したいという思いはあったが、そのための活動は一切しておらず、バンド活動に熱をあげていた。インターネットも一般的でなかった時代、就職活動の情報も少なく、気がつけばバブル期にはよくあった第一陣の“青田買い”の時期は過ぎ、少し遅れて通常募集の枠で、学研へ入社したのだという。
入社後に配属されたのは、同期の間では「『あそこに配属されたら、ちょっとダサいよね』という雰囲気が漂っていた」という、中学生向け学年誌の編集部だった。
「配属は正直、ちょっとショックでした(笑)。でも、学年誌で鍛えられたなー、という感謝の思いが強いです。12星座毎日分の細かい占いのページ、ファッションページの撮影、読者や先輩中学生のインタビュー取材、テスト勉強のやりかたページなど、本当にいろいろな経験を積むことができました。毎月、読者アンケートで記事の人気投票結果が出るんですけど、どんなアンケートをとれば記事に活かせるレスポンスをもらえるのか、いただいたレスポンスをどうしたら記事に活かせるのかなど、今につながるとても濃い経験ができました」

その後は、小学生向け学年誌の『学習』編集部から、幼児向け教材の『はなまるきっず』編集部へ。その『はなまるきっず』が、絵本の部署と統合されたところから、絵本の製作に携わるようになった。著名な絵本作家さんに心酔し、その世界観の中で仕事ができることに夢中になる編集者が多い中、北川はちょっと馴染めないものを感じていたという。
「大御所の先生が描かれている絵本が大好き、というのもあまりなかったので、どちらかというと、名作と言われる絵本は知らない、よく分からない、というママ・パパに向けて『わたしも同じだよ』という気持ちで作っていました。むしろまだ世の中に知られていないけれど、いいものを作りそうな作家を探し出すことが楽しかったです」
こうした姿勢はその後、『こどもずかん』や『おさかなちゃん』シリーズなど、名作シリーズを生み出すこととなった。

教室の隅っこにいる子どもたちに送りたいメッセージ
北川の「目立っていないところにスポットライトを当てる」という意識は、本づくりにも反映されている。多くの子どもたちのなかで、トレンドに乗った人気者や成績が優秀な子たちがいる一方、小学生や中学生の頃の北川がそうであったように「隅っこにいる人たち」が見て楽しんでもらえるものを、無意識に追い求めているのだという。
「私は、そうした位置にいる子どもたちに向かって『だいじょうぶ、そこから始めればいいんだよ』と言いたいのを、作る本の中で無意識に表現しているのかもしれません」
こうした優しさは、北川が中心となって手掛けた『王女さまのお手紙つき』や『一期一会』シリーズにも見て取れる。いずれも、メインのターゲットは、読書は苦手だけど、なんとなく「読書をしなさい」という空気の中にいる子どもたち。そんな少女たちが、おとぎの世界への空想を広げられる体裁にしたのが、翻訳本『王女さまのお手紙つき』。そして、小学校の中学年や高学年になり「朝読の時間に、何を読んでいいか分からない」という子どもたちに向けたのが、雑誌のようなテイストを取り入れた書籍『一期一会』シリーズである。

『一期一会』シリーズは、読み物でありながら、恋、占い、ファッションなど雑誌的な魅力を取り入れたことで人気を博した。読書が苦手な小学生が、『一期一会』シリーズだけは親にねだって購入する。また、大人からは「これは読み物ではなくマンガなんじゃないか?」という声があがる、などの現象が起こるほどのセンセーションを巻き起こした。
書籍は通常、一冊を編集者ひとりで制作することが多いが、『一期一会』シリーズは、チームを作って書籍を製作していた。ここにも雑誌づくりのノウハウが活かされた。入社直後に配属された学年誌編集部の経験が、想像もしなかった形で実を結ぶことになった。
「スタッフのいろんな意見をミックスさせながら、内容に偏りのないように作っていきました。『全員、児童向け書籍づくりの素人なので、これまでの固いやりかたはよくわかりません。何がいいと思うか、本音で選んでいきます』という雰囲気を、そのまま本にしちゃおうよという感じで。イラストの顔の部分に文字を乗せちゃうのも、書籍ではあまりやらないけど、雑誌や映像だったら平気でやるよね、という感じで判断して、あえて洗練されてないけど楽しい雰囲気を作っていったように思います」
誰も気づかなかった輝きを見出すのが編集の面白いところ

数々の児童書をヒットさせてきた北川に、編集の仕事とはなにか、を尋ねた。
「世の中の多くの人が気づかない、それどころか、本人すら気づいていないクリエーターや読者のポテンシャルや本音を見出して、それを輝かせることができたとき、編集という仕事をやっていてよかった! と心から思います。完成して有名になっているもの、光を放っているものよりも、一見地味なものの中に潜んでいるこれからどうなるかわからない輝きを、私なりに引き出して形にしていくことに、魅力を感じます」
また、海外のパートナーと話しながら仕事をしていくのも魅力だという。
「文化がかなり違うので、日本だけの凝り固まりがちな視点とは、異なる考え方ができるようになりました。また、海外と日本を比較することによって、日本人の持つ誠実さとか頑張る力みたいなものが、かなり優れているのではないか、って思えるようにもなりました。だからこそ、翻訳本であれば、同じ原書を使ったどの国の翻訳本よりも売れるものにしたいと思っています」
北川の話を聞くと「地味で目立たないけれど、何かの力を持っている人たちを、救い、輝かせたい」という使命感のような強い思いを感じてしまう。かつては“不器用だった”自分を、ずっと心の中で大切にしながら、作品や読者と接していく優しさと力強さ。それこそが誰にも真似できない、編集者・北川だけが持ち得ている魔法なのかもしれない。
(取材・文=河原塚 英信 撮影=多田 悟 編集=齊藤 剛、櫻井 奈緒子)
クリエーター・プロフィール
北川 美映(きたがわ・みえ)

大分県育ち。大学入学を機に上京。1990年に新卒で学習研究社に入社。「中学コース」「学習」「はなまるきっず」と、学研の柱であった学年誌やその派生商品を長く経験後、絵本の編集を多く手掛けるように。230万部のヒット作『こどもずかん』シリーズなどを手掛ける。また絵本の手法、ポエムの手法を小学生向け読み物にいかし、編集者チームを組織して作った書籍「一期一会」シリーズが350万部を超えるロングセラーに。海外のブックフェアで翻訳出版の世界に出会い、以降、ローカライズを大胆に加えた絵本や小学生向け読み物シリーズを次々にプロデュース。累計58万部の「おさかなちゃん」シリーズを生み出している。
担当作品紹介
絵本「おさかなちゃん」シリーズ

ベルギーの絵本作家ヒド・ファン・ヘネヒテン氏による、世界で28言語に翻訳されているベストセラー絵本。学研プラスからはこれまで計8タイトルが発売され、シリーズ累計発行部数は58万部。0~3歳児定番の「おはなし絵本」として、世界中のママ・パパに愛されている。
「王女さまのお手紙つき」シリーズ

原作は、イギリスで2013年に発行され、アメリカ、イスラエル等、世界で175万部を突破した「The Rescue Princesses」シリーズ。
主人公は、おとぎの世界にある、様々な国でくらす12人のキュートな王女さまたち。巻ごとに、主人公が変わります。王女さまたちは、魔法のジュエルや思いがけない事件、動物とのふれあいなどを通じて、友だちとの友情や自分の性格、家族との関係など、思春期の女の子ならではの悩みに、答えをみつけていきます。
行動者ストーリー詳細へ
PR TIMES STORYトップへ
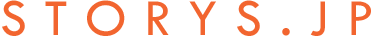
 LINE
LINE
