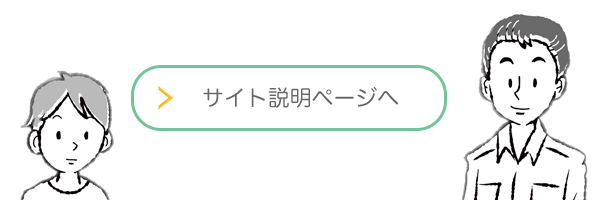陸の孤島の小さなクレープ屋さんの物語
■井崎先生の最初の教え

先生から最初に教えてもらった事は、経営の話ではなく、人生の考え方だった。
「人生の目的は幸せになること。仕事をすることが目的じゃない、お前は仕事のために人生を生きてないか?仕事は人生を豊かにする手段に過ぎない。仕事よりお前の人生の方が大事なんだ。だからビジネスごときでグズグズ言うな!!仕事なんてクソくらえ!!」
僕はこの言葉で、一気に肩の荷が下りて心が軽くなった。
その頃の僕は正に仕事のために人生を送っていたからだ、自分も幸せになりたい、親も幸せにしたいと言いながら、朝から晩まで仕事してプライベートの時間も金も無い、毎日のように親には文句を言い愚痴をこぼし、親やスタッフとは十分なコミュニケーションを取らないくせに経営者の集まりにスコスコと出掛けて行っては偉そうにビジョンを語る。
本来、自分のビジョンを伝え、コミュニケーションをとらなければならないのは親やスタッフなのに、外部の経営者とばかりビジョンを語りコミュニケーションをとっておきながら、「親は俺の事をわかってくれない」とか「スタッフが俺のビジョンをわかってくれない」とか愚痴をこぼす、もともとコミュニケーションをとってないのだからわからなくて当たり前なのである。
頑張っているのに結果が出ないから、親やスタッフへの後ろめたさがあった、だからチヤホヤしてくれる外部の人達に逃げていたのだ。
もう仕事のために生きるのはやめよう!
僕はもう一度自分の人生の目的を考え直した。
人生には「リズム」がある。自分の心がすさんでいると、ビジネスは上手くいかない。
気持ちが吹っ切れると、ビジネスが不思議と上手くいく時がある。
これが「リズム」だ。
やっぱり僕は「家族を幸せにしたい。」
これが僕の人生の目的だと思った。
もちろん、人生の考え方を変えるだけではビジネスは上手くはいかない。
でも、人生の目的が明確でないと、仮にビジネスが上手くいったとしても幸せにはなれない。
僕は先生に経営より大切な事を、一番最初に教えてもらった。
僕はそれから、お店の経営を一から見つめなおし、先生の元で学びながら少しずつ改善していった。
すると、あれだけ本を読んだり、他のセミナーを受講したりして、頑張っても頑張っても全然良くならなかったお店の業績が徐々に好転し始めたのである。

僕が井崎先生から学んで実践したことは「難しい経営理論」や「素晴らしい経営理念」や「気合と根性の精神論」ではありません。
とてもシンプルな事を実践するだけで、お店の業績は好転していったのです。
多くの経営者がわかっているようでわかっていない、出来ているようで出来ていない、
そのシンプルな事とは。。。。。。
*井崎貴富先生は令和3年2月3日に逝去されました。
井崎先生には僕の人生の窮地を救っていただき、本当に感謝しかありません。
井崎先生を通して沢山の出会いもありました。
それらは全て僕の財産になっています。
本当にありがとうございました。
<第3章 ここまで>
<第4章>
■すべてはFor the Customer(お客のために)
僕は井崎先生に経営より大切なのは「自分の人生」だと教えてもらい、心は軽くなったが、そうは言ってもお店の経営は相変わらずのピンチなのである。
当然のことだが、考え方を変えるだけではビジネスは上手くはいかない。
次に必要なのは「正しい知識」と「行動」なのだ。
僕は井崎先生の元で必死に経営を学び、次々と手を打っていった。
「本当にお客様のために商売ができているか?」
本当にお客のために行動が出来て、お客の望む状態が実現出来ているならば、お客が来てるはず、売上も上がるはず、でもお客も来ない、売上も上がらないという事は、お客のために出来ていない、お店のどこかに問題があるという事なのだ。
本当の「お客のために」とは、考え方や心構えではなく、「行動の仕方」と「実現している状態」のことを言うのである。

■間違った「お客のために」
僕が最初に取り組んだ事は、それまで100種類以上あったメニューを半分以下に減らすことからだった。
その頃、豊富にあるメニューの中には、月に1回注文があるかないかくらいのメニューもあった。
それまでの僕の考え方は、たとえ月に1個しか注文されなくても、注文するお客様が居ればそのメニューは無くさない。という方針だった。
しかし、このやり方だと、材料を仕込んでもなかなか出ないので、時間が経つにつれ品質が低下していき、期限が切れロスになる。ロスになると利益が減る。
利益が減ると満足のいくサービスが提供できなくなる。
結果、出数の少ないメニューを残す事は「お客のために」ならないのだ。
そしてもう一つ僕が間違っていたのは、クレープのメニュー数が多い事は「お客のために」良い事だと思っていた。
お客は豊富なメニューの中から選びたいのだから、選択肢は多い方がいいに決まっていると思っていた。
しかし、メニューが多すぎるとお客は迷い、選ぶ気持ちが萎えてしまうのだ。
しかも、作る方も手間がかかり、効率も悪いのでオペレーションが複雑になり、提供時間も遅くなる。
結局、メニューが多いことも「お客のために」なっていなかったのだ。
「豊富さ」とはあれこれ沢山ある事ではなく、お客の欲しいモノが欲しい価格で沢山ある事なのだ。
■仕入れ業者の変更
その頃の僕は「1つの仕入れ業者さん(以下業者さん)と末永く付き合うことが、業者さんと良好な関係を築く事ができるし、お店にとってもその方が良い」と思っていた。
しかし、それは大きな間違いだった。
業者さんを1社だけにしていると、仕入価格は絶対に下がらない。
仲良くなった担当の人に「もうちょっと安くしてよー」と言って、まれに少しだけ安くしてくれるのが関の山だ。
●仕入れの大原則:「仕入れは2~3年置きに、3~4社で相見積もりを取り競争させよ」
僕はそれまで付き合っていた業者さんとは別の業者さんを3社見つけてきて、仕入れていた食材や備品の見積もりをそれぞれに出してもらい競争させたのである。
著者の山本 顕太郎さんに人生相談を申込む
著者の山本 顕太郎さんにメッセージを送る
著者の方だけが読めます
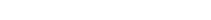

 LINE
LINE