明治6年創業の老舗刃物メーカー 三星刃物の軌跡。挑戦し続ける企業風土で、次の時代へ
社長の妻のひとことが契機に。OEMから自社ブランドへ――
三星刃物株式会社(以下、三星刃物)は刃物の町 岐阜県関市に本社を置く刃物メーカーだ。現在の経営者は5代目となる渡邉隆久。創業は明治6年である。
三星刃物は今年、創業150周年を迎えた。

創業後、市内の同業他社に先駆けて海外販売を開始した三星刃物は、現在も北米やヨーロッパを中心に世界中の国々へ輸出をおこなっている。その多くはOEM(Original Equipment Manufacturing)――納入先商標による受託製造だった。
長らくOEM事業をおこなってきた三星刃物が、初の自社ブランド「和 NAGOMI」を開発し世に送り出すに至った物語を、会社の歴史とともにお伝えしたい。
「どうして老舗刃物メーカーなのに自社ブランドがないの?」
あるとき妻 友佳理がふともらした言葉に、渡邉はハッとした。2010年頃のことだ。
当時、三星刃物のビジネスの中心はOEMだった。デザインや開発にコストを掛けずに済み、在庫リスクもない反面、価格勝負の薄利多売となる。少しでも値上げをすれば容赦なく契約を切られてしまう。
顧客の多くは欧米企業で、コスト面の理由から製造の中心は中国だった。折からの原油高・原料高に中国人の人件費高騰も重なり、OEMという業態にかげりが見え始めていた。
このままではいけないという渡邉の危機感が、いっそう強まっていた時期だ。
自社ブランド。長きにわたり「ものづくり」をしてきた会社だ。一度も考えなかったと言えば嘘になる。しかしこの時の渡邉にとって、三星刃物にとって、それはまだ現実感のない話だった。

刃物の町 関の老舗刃物メーカー。創業と躍進、そして暗転
三星刃物は明治6年(1873年)、刀鍛冶だった渡邉の曽祖父 善吉が創業した。侍の時代の終焉とともに農耕具などの製造販売を開始したのだ。
その後、ナイフやはさみ、包丁などラインアップを拡大し、祖父である2代目善吉が1912年、東南アジアへの輸出に打って出た。
父 鉞夫の時代には57年にニューヨーク、71年にシカゴに支店を開設。高度経済成長の波に乗り会社は著しい成長を遂げた。当時は1ドル=360円の固定相場制であり、安い上に品質が良い日本製品は人気が高く、飛ぶように売れた。

潮目が変わったのは73年に変動相場制へ移行してからだ。85年のプラザ合意を経て急激な円高が進み、経営は悪化した。
渡邉が入社したのは86年。最悪のタイミングだった。国内外の支店は次々に閉鎖・撤退を余儀なくされ、三星刃物はそれまで経験したことのないどん底の状況にあった。反して、日本はバブル経済の只中で雇用においては完全に売り手市場だ。中小企業では人を雇うこともままならない。「日本製品の輸出」が厳しい状況となったこともあり、渡邉は中国での製造に活路を見出した。
社運をかけ、中国へ進出
経済特区として開発が始まっていた深セン(セン=土へんに川)だが、当時はまだ高層建築などなく、彼方には地平線が見えた。そんな土地で、計画生産が比較的しやすい洋食器の工場を立ち上げたのだ。
また、「中国と言えば三國志。三國志と言えば青龍刀。青龍刀――つまり刀の国なのだから、中国にも関のような町があるはずだ」とのひらめきから刃物の町 陽江に辿り着いたのも渡邉自身だ。
87年の深セン洋食器工場を皮切りに、92年には同じく深センにキッチンナイフ工場を設立、96年には陽江に合弁工場を設立した。

ところが、当時の中国はインフラの整備は不十分で物資も乏しい。たったひとつの金型が壊れただけで、巨大な工場の製造ラインが止まってしまう。渡邉自ら重い金型を両手に中国へ飛んだことも、一度や二度ではなかった。
労働に対する意識の違いや、技術力の差。現地従業員による製品の盗難。地方政府からの理不尽な罰金や、横行する賄賂。日本では考えられないようなことが、次から次へと起こった。そのたびに渡邉は持ち前のコミュニケーション能力と粘り強さで周りを味方につけ、社員らと共に苦境を乗り越えてきた。
着実にやってきたことの中に、解決の糸口が
中国でのビジネスの黒字化には成功したものの、「日本企業が中国で製造を行い、欧米へ向けて販売する」というビジネスにはさまざまな問題もあった。安い工賃を求めての海外進出は、やがて行き場を失う。技術をもって進出すればコピーされる。現地での技術者の育成は容易ではなく、日本人社員が長く駐在するのも難しい。
そして2000年代後半からは、原油高・原料高に加え中国の人件費高騰もあり、価格勝負の薄利多売では業績を伸ばせなくなっていた。
状況を打開しようと始めたのが、「提案型OEM」だった。既存の製品を受託製造するのではなく、デザインや素材、ラインアップについてアイデアを出し、価格をすり合わせ、顧客とともに商品を作り上げるスタイルのビジネスだ。しかし、いくつものサンプルを作りやっとの思いで商品化に漕ぎ着けても、価格変更すれば次の日には他のメーカーに……。ここでも行き詰まる。OEMの限界だった。

「わたしこのデザインが好き」
商品化に至らず山のように残ったサンプルから、友佳理が1本のステーキナイフを取り上げた。波刃ブレードと木柄でできたステーキナイフだ。積層強化木にステンレスの象嵌。
後に世に出る高級包丁「和 NAGOMI」の原型となる製品であった。
「これ、自社ブランドにできるんじゃないかな?」
顧客への提案は何度もしてきた。要求に答えようとデザインをブラッシュアップしたり、よりよい鋼材、あるいは焼入れ方法を模索したり。他社ではなく自社のために、同じことができるのではないか?
「和 NAGOMI」の開発が始まった。
初めてづくしの試行錯誤
今でこそメディアに取り上げられたり、プロの料理人やインフルエンサーに愛用されたりすることも多くなった「和 NAGOMI」だが、始めから順風満帆だったわけではない。そもそもブランド包丁としては業界最後発。社内には、デザインの専門家もマーケティングの専門家もいなかった。
まずは友佳理が主宰するパン教室の生徒に対し、アンケートがおこなわれた。せっかく自社からブランドを打ち出すのだ。渡邉は、実際に包丁を使う人たちが本当に求めているものを作りたいと思った。すると、料理好きの主婦たちが皆、包丁に対して疑問や不安、ちょっとしたモヤモヤを抱えていることが分かった。
- 始めはよく切れても、結局切れなくなっちゃうよね。
- 切れなくなった包丁、捨てられずにどんどん溜まっちゃうの。
- 自分では研げないよ。
- 簡易研ぎ器って、包丁が傷まないか心配。
- 重い包丁は疲れるけど、軽すぎたらそれはそれで力が要るから疲れるわ。
主婦たちが求めているものは見えてきた。しかし、どう形にする?
友佳理の選んだステーキナイフをベースに調理包丁のフルラインアップを揃えようにも、正確な図面を引ける社員はいない。デザインを検討する段階で外部のデザイナーに依頼をしてしまえばコストが掛かりすぎる。
苦肉の策としてとられたのが、「写真を参考にハンドルの絵を描き、さまざまな刃先を貼り合わせ、実寸でプリントする」という非常に原始的な方法であった。作業に当たったのは、美術やデザインを専攻したわけでもない、ただ絵を描くのが好きなだけの社員だ。「刃渡りをあと3mm短く!」「刃幅1mm狭く!」などというやりとりを繰り返した。
そして試行錯誤の末、【するどい切れ味が長もちし、家庭でも手入れしやすい鋼材】を採用した【ちょうどよい重量バランス】の「和 NAGOMI」が誕生した。

現場の猛反発、繰り返された衝突、それでも――
そうしてなんとか形が決まっても、次は製造の問題があった。
刃物の町として有名な関市であるが、実は各社が包丁づくりのすべての工程を行っているわけではない。基本的には「分業制」だ。焼入れや刃付け、ハンドル造形など工程ごとに異なる会社が作業を分担している。各工程を熟練工が担当するため非常に高い品質を実現できることと、必要な設備を無駄なく共有できることがメリットだが、スケジュールの管理が難しい。複数の製品が一箇所の工程に集中しないよう整理する必要があり、納期に影響が出る。また、一社の技術継承問題が、複数の会社に波及することもある。技術者の高齢化、後継者不足は関の刃物産業が抱える問題の一つだ。
そんな中で大変な手間ひまのかかる高級包丁を作ろうというのだから、ある程度の摩擦は予見されていた。

しかし、実際は想像をはるかに超えた大きな衝突を生むこととなった。
長らくOEMの品質基準で製造を行ってきた三星刃物 製造部と、並々ならぬ思いで「和 NAGOMI」を送り出そうとする渡邉が求める品質基準に、大きな乖離があったのだ。品質を巡って何度も衝突した。最初に製造した600本の包丁は、渡邉の要求を満たせず、すべて廃棄処分となった。人手が足りない中で通常の量産とは別に残業し、丹精込めて研ぎ、磨きあげた包丁が、ゴミになる……?これに対し怒りを爆発させたのが製造部長だ。
「俺たちは美術工芸品を作っているわけじゃない。社長の言う通りにやっていたら商売にならんぞ」
もちろん、ビジネスとして行う以上は生産性も重要だ。中国での紆余曲折を知る製造部長の言葉には重みもある。それでも、渡邉は諦めたくなかった。コストカットや生産性重視でやってきたことの結果が、薄利多売のOEM事業ではなかったか。自分たち三星刃物は、そこからの脱却を目指すのではないのか。
製造部の検品に納得がいかず苦言を呈することもあった。すると現場からは「どうせ社長がやり直すなら俺の検品には意味がない。最初から社長がやったらいい」といった突き放すような声も出た。実際に、渡邉自らたったひとりで検品に当たることもあった。
渡邉は根気強く理想を語り、自分自身が動き、製造部に働きかけ続けた。
いざ販売開始!と思いきや、まさかの反応。ドイツ フランクフルトにて
2015年春、着想から5年あまりを経てようやく「和 NAGOMI」は納得のいく製品となった。渡邉は、やっとの思いで作り上げた製品を手に、フランクフルトで開催される国際見本市へと乗り込んだ。そこでずらりと並んだフルラインの「和 NAGOMI」を見たドイツ人から、思いもよらない言葉をかけられる。
「美しい……まるでBMWだね」

言わずと知れた高級外車であるが、決して褒め言葉ではなかった。
品質は最高。でも、日本の会社がBMWを作って欧米で売ってどうするの?こんなの誰も買わないよ。日本人ならTOYOTAを持って来ないと!という皮肉だった。
当時も今も、欧米では槌目を打ったダマスカスや白木のハンドルなど、いかにも日本らしいデザインの人気が高い。彼は、そういった包丁を提案しろというのだ。
絶望的な言葉だった。日本へ帰って製造部の面々にどう説明したらいいのだろう。
その様子を隣のブースから見ていたフランス人シェフが、渡邉に声をかけた。リヨンに店を構える日本人シェフを知っているから、製品を見てもらったらどうかと言うのだ。渡邉は藁にもすがる思いでコンタクトをとり、ぜひ使ってみてほしいと言って包丁を贈った。
1ヶ月後、リヨンから1通のメールが届く。内容は「和 NAGOMI」を大絶賛するものだった。曰く、凛とした佇まいがあり、フォルムが美しい。使いやすく、長時間握っていても手が疲れない。本当に素晴らしい、と。
メールにはシェフが実際に「和 NAGOMI」を使用している写真が添えられており、「応援しているから頑張ってください」と結ばれていた。
涙が出るほど嬉しかった。「和 NAGOMI」の良さを分かってくれる人がいた。それも、世界の第一線で活躍するプロのシェフだ。そのシェフが日本人であることが、渡邉にとっては啓示のように思えた。
そうだ、日本で売ろう。

手探りの販売戦略。どこで売る?誰に売る?
その後も渡邉は社員と協力しながら精力的に動いたが、悩みは尽きなかった。
展示会に出展することもあれば、デパートの催事に立つこともあった。朝の10時から閉店までフロアに立っても、売れるのは数えられる程度だ。原価と出店費用を差し引けば赤字になってしまう。
大手デパートとコネクションができても、常設販売しようと思えば商社を通さなければならない。すると今度は掛率が合わない。ギフトカタログも然り。採算が取れない。
膨大な手間ひまがかかる「和 NAGOMI」は、原材料費・人的コスト・希望小売価格を考えたときに“卸せる先がない”のだ。
導き出した答えは、D2C(Direct to Consumer)
やがて「自分たちで直接エンドユーザーへ届ける」という方法こそが、最適解であると気づく。オンラインショップだ。
対面で販売するのと違い、オンラインショップはそこに表示する情報が全てだ。細部の質感まで分かる製品写真。ライフスタイルをイメージできる写真。ぐっと来るキャッチコピー。分かりやすい商品購入ページ。当然、内製できるものではない。
コストが嵩むことは承知で、クオリティの高いものを求めて一流のコンサルタントに力を借りた。

大逆転できるような方法はない。
製造部がよい製品を地道に作り続け、営業がプロの手を借りて効果的なプロモーションを行う。日々の業務では丁寧なお客様対応をする。バイタリティのある若手営業マンや、こまやかな受け応えを得意とする女性が尽力した。
商品ページ同様、SNSにも力を入れた。プロのフォトグラファーやフードコーディネーターに入ってもらい、すてきな生活をイメージできるような写真を継続的に投稿した。フォロワーとのコミュニケーションも大切にした。
ギフト需要にも着目した。
元来「縁を切る」と言われ贈り物としては忌避されてきた刃物であるが、実際には晴れやかなイメージとの結びつきも強い。例えば、オープニングセレモニーのテープカット。例えば、結婚式のケーキ入刀。節目や門出の贈り物として、“未来を切り拓く”包丁はぴったりなのだという啓蒙を行った。
ラッピングや「のし」に力を入れ、もらうことはもちろん、贈ることにも喜びを感じられるような物をめざした。
最後発だからこそ、他社がやっていないことをやろうという信念があった。

少しずつ、本当に少しずつ歯車が噛み合い始める。
商品やサービスに対して、良いレビューが書き込まれるようになった。直筆の手紙が届くこともあった。それらのコピーを工場内に掲示すると、社員の意識も変わっていった。
人気インフルエンサーが私物として使用し、それをきっかけにご購入いただけるというケースも増えた。
そして「和 NAGOMI」は徐々に売上を伸ばし、2023年6月、シリーズ累計販売本数10万本を突破した。
これからの三星刃物、次の150年のために
こうして「和 NAGOMI」は、胸を張って自社ブランドだと言える包丁となった。
初の自社ブランドを世に送り出したことは、渡邉にとっても社員にとっても大きな成功体験である。
しかし渡邉の胸のうちには、異なる思いもあった。「和 NAGOMI」はゴールではない。社員には、「和 NAGOMI」に負けないような新しいブランドを立ち上げて欲しい。
技術と知識のある若い社員も増え、社内はここ数年でもっとも活気にあふれている。
「和 NAGOMI」がゴールではないのと同様に、150周年もゴールではない。
この先また150年、200年、その先も会社が栄えていくためには、関の刃物産業そのものが繁栄しなければならない。市内の同業他社は、ライバルではあるが仲間でもある。互いに切磋琢磨し、業界全体が未来を見据えて進んでいくために、新しいことにも怯まず一緒に挑んでいきたい。
どんな困難の中でも、挑み続けていればふっと道が拓ける瞬間があるはずだ。それが絵空事ではないことを、「和 NAGOMI」が証明している。

行動者ストーリー詳細へ
PR TIMES STORYトップへ
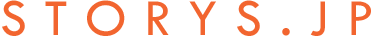
 LINE
LINE
