創業時の精神に立ち戻り、“日本一”を目指して ~「久保田」誕生物語~
朝日酒造のルーツは、1830(天保元)年に新潟県長岡市に創業した「久保田屋」です。創業以来150年近く、「朝日山」のみを醸し、県内のトップメーカーに成長しました。
しかし、1980年代に入り、清酒業界で大量生産・大量販売を背景とする廉売競争が勃発。結果、コストダウンによる品質低下を招くことになり、その過当競争に巻き込まれることは経営危機に他なりません。
「価格競争では太刀打ちできないのだから、高品質な美味しいお酒を届けていこう」との想いから、1984 年、社運を賭けた一大プロジェクトが始動しました。従来の「朝日山」のワンランク上に位置づける「新しい美味しさ」を提供する商品、開発ネーム「東京Ⅹ」の開発が始まったのです。
高品質なお酒をお値打ちな価格で届けたい

「久保田」の生みの親と言える重要な人物の一人、嶋悌司(ていじ)。新潟県醸造試験場長として、長年、新潟清酒の質の向上と酒造技術者の育成に努めていました。
そしてもう一人が、朝日酒造四代目社長・平澤亨(とおる)。両者には、日本酒への共通の想いがありました。
1970年代、日本酒は灘・伏見の大手酒造メーカーで造られた芳醇甘口タイプが好まれていました。しかし1980年代に都市で地酒ブームが起こると、各地で造られていた地酒が全国区に。その人気を牽引したのが、新潟のある酒造メーカーのすっきり辛口タイプの日本酒です。
これまでとは全く異なるタイプの日本酒はやがて首都圏で評判となり、人気のあまり入手困難に。一時期は通常の何倍もの価格で流通するなど、「幻の酒」とも言われていました。
この「幻の酒」の話を耳にした嶋悌司は、「高品質な美味しいお酒をお値打ちな価格で、新潟から全国のお客様へお届けしたい」との想いを強くし、求めるお客様に手の届かない「幻の酒」にはしないと決意したのでした。
また、当時の清酒業界は大手酒造メーカーを中心に、大量生産・大量販売を背景とする廉売競争が勃発。「朝日山」も、酒ディスカウント店では安売り商材にされ、ブランドの毀損が著しくなっていました。
そんな中、朝日酒造四代目社長・平澤亨は「量より質の時代」の到来を感じ、高品質な酒をお値打ちな価格でお届けする必要性を感じていました。
嶋と平澤、両者の「新潟から高品質な酒を適正な価格で提供したい」との共通の想いが実を結び、1984 年、平澤は新潟県醸造試験場を中途退職した嶋を朝日酒造の工場長として迎え入れました。
都会のお客様にも受け入れられるお酒を

「幻の酒」のように都会の方々から支持される酒とは、一体どんな酒なのか。「東京Ⅹ」の開発に向け、まずは都会の人々の食生活や嗜好のニーズを徹底的に追求しました。
そこでたどり着いた酒質は、「淡麗辛口」。経済がめざましい成長をとげていた当時、仕事の質が肉体労働から頭脳労働へと変わり、塩分やカロリーを必要としないようになりました。食べ物と同じように、酒もこってりした甘いタイプではなく、すっきり飲める、飲み飽きしない酒が好まれる。嶋はそう予見しました。
「時代が求める味わい」を目指した魂と魂のぶつかり合い

目指すは、万人向けではない「淡麗辛口」な、朝日山の1ランク上の日本酒。社運を賭けた酒造りが始まりました。
まずは酒造りの基礎である米の選定から。今回の「東京Ⅹ」では、1957年に新潟県で誕生した酒米「五百万石」を全面的に採用しました。米自体のたんぱく質が少ないため、すっきりキレが良く、いわゆる淡麗な味わいを目指す酒造りに適している品種です。現在は、酒米の王様・山田錦と並んで酒米の二大トップですが、当時はまだ五百万石を全面的に採用することは稀でした。
山田錦など思うように入手できない西日本の米にこだわるより、新たな酒は新潟の米・水・人で醸しだしてこそ地酒ではなかろうか、「新潟発信」から旨酒を…根底には「オール新潟」への想いがありました。
造りの面では、造りを担う杜氏と蔵人たちに、まずは平澤と嶋の共通の想いを理解してもらうことから始めました。
「秋になって蔵人たちが集まった。社長の意向と私の考え方を伝え、計画に基づいて工程を説明した。いざ作業に着手すると、案の定、抵抗が広がった。伝統の手順に慣れ、『違う造り方はだめ』だと杜氏も言う。保守的な意識を変えさせるのに苦労した。対策の一つとして、幹部クラスを組み分けして県内の蔵へ、お手本となる酒蔵へ見学に出したのは成功した。出向いた技術者たちは設備や手順など、格差を認識した」(嶋悌司(2007) 酒を語る 新潟日報事業者社 p195)
朝日酒造という閉ざされた環境から脱し、他のメーカーの酒造りにも目を向けさせたことで、杜氏と蔵人たちに意識の変化が起こったのです。
「現状に満足せずさらに上を目指し、日本一の酒を造ろう」
共通の想いが彼らにも芽生えたことで、現場の士気も高まりました。

酒造りにおいて特に重要な工程である麹造りでは、吟醸型の突き破精麹を造るべく、寝泊まりしながら麹の温度・湿度管理を追求。妥協なしの性格むき出しで、嶋は杜氏と相対しました。
「時間が来ると麹室に上がっていって、“切り返し”に立ち会う。『こうしろ』とか『もういっぺんやれ』とかうるさく言いましたから、皆『殺される』とか言っていたと、後で聞きましたよ」(嶋悌司(2007) 酒を語る 新潟日報事業者社 p212)
嶋と杜氏、蔵人たちの試行錯誤の酒造りは日毎夜毎続き、酒造りの品質は日に日に向上、納得できる酒が出来上がりました。淡麗辛口ながら、まろやかさとキレ味を感じさせる「東京Ⅹ」の誕生です。
“創業時の精神(初心)に立って真剣に良いものを造ってお届けしてゆこう”との決心から、創業当初の屋号“久保田屋”の名を冠しました。その名は「久保田」。
そうです、後に朝日酒造の代表銘柄となる「久保田」がついに誕生したのです。
創業時の精神に立ち戻って
徹底した品質管理を行ない、お客様へ最良の状態でお届けするため、販売をお願いする酒販店については、商品管理・商品説明など価値を伝えられる専門性の高い販売店にしぼり、商品もお店にメーカーから直接納める異例の方式を採用しました。ちなみに当時の希望小売価格は、一升瓶で、一級酒(千寿)が2,000円、二級酒(百寿)が1,500円でした。
また、新聞やテレビなどの広告は一切せず、省いた経費は、品質向上に振り向けてお客様へ還元。そのため、お伝えする情報は店頭での店主とお客様のコミュニケーションの中で「久保田」のストーリーや価値を伝えていく、今でいう「口コミ」による拡散を狙いました。お客様に信頼されている店主が「久保田は美味しい」と本気で薦めてくれる、そういうお店と力を合わせていきました。
当時、営業担当は7人ほど。全国各地を飛び回り、久保田に込めた想いや価値を、思い思いの言葉で伝え続けました。創業時の精神に立ち戻り、久保田を単に売るのではなく、「酒販店と一緒に久保田を育てていこう」「日本一の酒に」という決意を胸に灯しながら。
朝日酒造と酒販店、酒販店とお客様、人と人とのコミュニケーションを地道に重ねた結果、発売翌年には、久保田は朝日酒造の清酒出荷量の10%ほどに到達しました。
大きな転機が訪れたのは、1990年に入ってからです。それまでは家庭用・ギフト用での販売展開のみでしたが、新たに飲食店への展開が開始。県内を代表する割烹から「久保田をお店でもお客様に飲んでいただきたい」と話があったのです。
このことが契機となり、久保田は「飲食店で飲める酒」に、消費者との接点がしだいに拡大。新潟の日本酒の「淡麗辛口」のイメージを「久保田」が決定づけることとなりました。
「久保田」で思い描いた、皆様の笑顔

「贅沢な気分になりたい時、楽しい時、良い友達が来た時、お土産にする時…そう考えれば、誰でも、毎日の生活の中のアクセントとして使えるのです。自分はどんな時に飲もうか、誰なら喜ぶだろうと頭に描いてみてください」と当時の嶋は語りました。
朝日酒造は、お客様の喜びのひとときを彩るのにふさわしい「久保田」の味わいを、これからも磨き続けていきます。
行動者ストーリー詳細へ
PR TIMES STORYトップへ
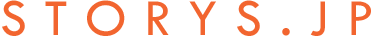
 LINE
LINE
