稀代の銘店から大きな信頼を集めるうどん粉。味の良さで遠方からも引き合いのある乾麺や半生麺。100年企業が、祖業を大切にしつつ、次の100年を粘り強くしなやかに生き延びるストーリー。
 ▲愛知県産小麦「きぬあかり」を使用したうどん
▲愛知県産小麦「きぬあかり」を使用したうどん
大正6年、米や麦の賃挽きからはじまった(株)金トビ志賀。現在では、用途などで繊細に作り分けるうどん専用粉の「製粉」と、乾麺・半生麺・生麺と客先のニーズに合わせて作り分ける「製麺」を主として、堅実な経営を行なっています。とはいえ、結成時に数十社の製粉会社が集った地域の組合も、近年の解散時にはわずか5社しか残っていませんでした。大手数社とそのグループ企業で国内市場のほとんどを占める現在の製粉業界。志賀重介社長は一言、「運が良かった」と言いますが、この百余年の間、同社にも大きな試練が何度も押し寄せました。第二次世界大戦に始まり、国内の食糧事情の変化や人々の食習慣や嗜好の変化、複数回にわたる自然災害からの復活、オイルショックやバブル崩壊、近年では新型コロナなど。一言では片付けられないドラマがそこにはあったでしょう。
このストーリーでは、(株)金トビ志賀の創業時からの歴史を振り返り、併せてこれからの将来展望を語ります。
水車小屋での丁稚奉公から。独立を果たし、時代の波に乗る。
明治26年、名古屋市西区に生まれた創業者・八五郎(写真人物)はその名の通り8人兄弟の5男、学校もそこそこに父親の生家に近い幡豆町の水車小屋で丁稚をすることになりました。仕事は米や麦の賃挽き。やがて強運にも丁稚先の長女の婿となったものの、元々独立心が強かった八五郎は、婚家に跡取りとなる息子がいたことも考慮し、婚姻から4年後の夏、妻と1歳になったばかりの娘を連れて、現在の蒲郡の地へ移り住みます。水車は利用できない土地でしたが、当時、小事業者への電力利用が可能になったことを機と捉え、一馬力のモーターに、2斗張り棒杵式精米機、精麦機、石臼式製粉機、米粉製粉機などを付け替えて、それまで同様の賃挽きを開始。当時の家土地の賃料が1年で45円のところ、設備一式の購入額は380円。当時としてはそれなりに思い切った投資であったことでしょう。2代目となる甚一が生まれるのはその2年後。さらにその5年後の大正13年には木造瓦葺きの製粉工場を新設し、事業は順調に波に乗っていきます。当時の賃挽きは、動力を使ってはいてもビジネスとしては江戸時代のそれと変わらず、手間賃をもらって挽く、手間賃を払えない客には持ってきた穀物の一部を対価として受け取る、挽いた粉だけが欲しい客には金銭をいただいて販売する、というもの。在庫を抱えがちな小麦粉を回転させるために製麺工場を作り、機械製麺の製造販売に乗り出したのは昭和3年のことでした。
▲石臼式製粉機の上臼
接収は免れても仕事はできず歯痒いばかりの戦中。GHQの食糧政策で米国産の麦を学ぶ。
やがて始まった第2次世界大戦は、(株)金トビ志賀のような地方の小さな事業者にも仕事の中断を求めました。幸い製粉や製麺の機械の多くはまだ木や石の部品が多く使われており金属部品はわずか。さらに使っていても鋳物であって、武器や飛行機になるような良質の鋼鉄がほとんど使われていなかったため、供出や接収の対象にはなりませんでした。八五郎はすでに徴兵される年でなく、息子たちもまだ少年で戦地に赴かずに済みましたが、学徒動員で他所に労働に駆り出される日々。仕事ができないことを悲しんだ八五郎は、農家は普通に米麦を作ることができるのに加工ができないのは理不尽だ、と、しぶとく国に働きかけ、昭和20年4月に未利用資源製粉の許可を取り付けるも、程なく終戦。戦後はGHQの食糧政策により米国産の多くの種類の小麦が大量に流通、日本は米軍にとって朝鮮戦争の物資輸送基地とされたこともあり、加工のニーズも莫大に増加しました。しかし、普通の小麦は問題なかったものの、パン用の小麦はそれまで日本に無かったもので特性がまるで違ううえ、どちらも扱うにはさらに新たな設備投資が必要。八五郎は昭和25年1月に株式会社志賀製粉所を設立、2月には製粉工場本館を竣工しますが、このとき、敷地が手狭であったこと、また、巨額の投資を避けたことから、パン用小麦には手を出さない、という決断を下します。奇しくも、その後麺用粉に特化していく第一歩となりました。
▲設立当初の㈱志賀製粉所
金トビ印の誕生。災害を乗り越えてさらに急成長を続ける。
八五郎は地元・蒲郡の空を高らかに飛ぶトビに自社の成長を重ね、戦前より製品であるうどん粉に「トビ印」の銘をつけていました。戦後しばらくは政府による麦類統制が続いたため自社製品を自由に販売することができなかったのですが、やっと昭和27年になりそれも解除、製粉各社が再びそれぞれ独自の商標をつけて製品を販売できるようになりました。この時八五郎は、神武天皇の戰を勝ちに導いたとされる金鵄(きんし。金色のトビ)の故事にならい、最高品質のうどん粉を「金トビ印」と命名。金トビ印は瞬く間に評判となりましたが、翌28年には台風13号による高潮で140cmもの冠水被害に遭遇、原料・製品の全てが水浸しになります。災害の痛手は大きなものでしたが、この経験をその後の工場運営をする上での大きな教訓とし、新たな設備投資を行い、戦後の復興に沸く日本でさらに右肩上がりに急成長を遂げていきます。昭和31年には戦前から「八百富の糸」の名で売っていた乾麺を「金トビめん」に改称。製粉と製麺、共に「金トビ印」となり、「金トビ」は地域のブランドとして確立。高度成長期の波に乗り、売上も順調に伸びていきました。
▲「トビ印」マーク
電話の開通を受け、名古屋に営業所を設立。やがて通販事業で全国に乾麺を届けるように。
昭和31年、ついに社内に電話が開通、それを機に八五郎は名古屋に営業所を開設します。このころは戦後に修行を開始したうどん職人がちょうど独立するタイミングでもあり、たくさんの新店が金トビ印のうどん粉を導入してくれたと言います。やがて昭和35年、八五郎は会長になり、社長が2代目・甚一に交代。作れば作っただけ売れていく時代、甚一はそれまでに確立した国産麦と外国産麦をブレンドした数種類の麺用粉、そして金トビ印を冠したそうめんやきしめん、うどんなどの7品目の乾麺を、工場をフル稼働させて製造販売。着々と売り上げを伸ばし、企業規模を拡大していきました。オイルショック時には、乾麺の乾燥工程に重油を燃料とするヒーターを使っていたために、原油価格の上昇が販売価格にそのまま反映されましたが、どれほど値上げが続いても販売量が落ちたりクレームにつながることはありませんでした。堅調に成長を続ける中、名古屋に単身赴任等で訪れたサラリーマンから、金トビ印の麺のファンになり次の土地でも食べたいから送ってくれないか、といった声が会社に届くようになりました。それを受けて、昭和50年には通販課を新設。金トビ印の躍進はさらに続きました。

▲金トビ印の乾麺
バブルに先んじた乾麺市場の縮小。それはむしろ幸運だった、かもしれない。
右肩上がりだった売上に陰りが見え始めたのは昭和58年。スパゲティなどの洋麺類が家庭に浸透し、インスタント麺やカップ麺、さらに冷凍麺も徐々に台頭。そうめんや冷麦などの乾麺市場は緩やかに縮小し、次第に「伝統食品」というカテゴリーに収束されるようになっていきました。そんな苦しい時代に社長の荷を背負ったのが3代目の弘嗣でした。幸い、ここまでに潤沢な蓄えを作っていたことで、右肩下がりが続く中でも赤字を出さずに堅実に経営を継続。やがて世間がバブルに浮かれ、その崩壊後に大きな危機に直面しても、同社にとっては全く関わりのないことだったと言います。堅実経営のなせる業でもあろうと考えられますが、同社では、ただ「運が良かった」と認識しています。とはいえ、一度縮小に向かった市場が再び大きくなることはないと、弘嗣は正社員採用を一時的にストップ。従業員が退職しても正社員補充はせず、できる限りパートに切り替えたほか、離散していた工場の機能を1箇所に集約するなど、無理のない経営のスリム化を進めました。やがて平成12年、製粉・製麺を事業とする「(株)志賀製粉所」と、その輸送・配送を担っていた「(株)金トビ食品」を統合し、現在の「(株)金トビ志賀」が誕生。「一つの同じ電話番号で電話を受けても、電話をかけて下さったお客様に不都合がないように」という理由で決まった社名でしたが、おかげで大きな混乱を招くこともなく浸透していきました。
ブランディングと新規事業開拓。強みは活かし、前例のないことにも歩を進める。
現社長の重介が社長に就任したのは平成19年末。就任前より各種の業務改善に取り組み、最新の食品工場のあり方やブランディングについて学ぶとともに、オリジナル商品の開発にも着手していました。20年には「めん用の小麦製粉に特化し、乾めん・半生めん・生めんを自社製造している」と言う独自性で「愛知ブランド企業」に認定。続いてモンドセレクションなどの各賞を獲得し、ブランド価値を着実に向上。さらに、すでにあった通販のノウハウを活かして楽天市場に出店したり、新規事業として宅配水事業や太陽光発電事業にも乗り出します。一方で、就任前に取り組んだISO9001に続いて平成25年には浜町の工場でHACCP認証を取得。職人気質な製造現場を、客観的な評価基準に基づいて管理・記録していくという、現代に求められる食品メーカーとしての基盤を固めていきました。
 ▲宅配水事業 クリクラ蒲郡( 公式HP https://www.11mizu.jp/ )
▲宅配水事業 クリクラ蒲郡( 公式HP https://www.11mizu.jp/ )
そんな中、蒲郡のソウルフードとして一躍全日本に名前を轟かせたのが「ガマゴリうどん」。平成25年のご当地うどんサミットでグランプリを獲得したのを皮切りに様々なコンテストで入賞します。これに対し、翌26年、同社自慢の乾麺にレトルトの具などをセットにした「ガマゴリうどん」2人前と4人前を商品化し、ご当地メーカーとして素早くお土産需要に対応。その後、国産アサリの不漁から一時終売するも、原材料の見直しとクラウドファンディングへのチャレンジで見事復活、発売から10年を数え、今では毎年数万食を売り上げる新しい蒲郡の土産物に育ちました。

▲ガマゴリうどんお土産ギフト
祖業を大切に。現代的経営手法を取り入れ、この100年もしなやかに、粘り強く。
平成29年に創業100年を迎えた(株)金トビ志賀。令和を迎え、ビジネスのあり方は加速度的な変化を求められています。経営手腕を見込まれて経営を引き継いだグループ会社の神藤製麺は、茹で麺の製造販売を手放すところから始め、10年を経てついに赤字を脱却。創業時より製粉と製麺が売上ベースで半々なのは変わらないものの、製麺の主力は乾麺から半生麺へ、それも全国からのOEM生産が9割を占めます。また、一時は使用量ベースで10%程度に下がっていた国産麦は、国産原料へのニーズの高まりに加え、「きぬあかり」という優良品種の登場により55%を超えるまでに復活。新型コロナの影響で3割落ちた売上も、やっと以前に近いところまで戻りつつあります。「香りがいい」「色艶がいい」「小麦のうまみがある」と評価の高い同社の麺用粉と製麺ですが、その言葉はあくまでも主観的。同社は令和6年4月から運用開始された3GeV高輝度放射光施設での試験対象に名乗りを上げており、高評価の理由が客観的な数字となって、他社との差別化につながるのではと期待します。祖業を大切にしながらも、新しい取り組みを常に模索する(株)金トビ志賀。同社が作る麺のように、しなやかに、粘り強く、光り輝く未来を見つめ、これからの時代に歩みを続けようとしています。
▲㈱金トビ志賀 代表取締役社長 志賀重介
行動者ストーリー詳細へ
PR TIMES STORYトップへ
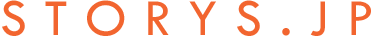


 LINE
LINE
