落ちこぼれボク、グランプリ受賞までのキセキ!〜異星人ボクと宇宙人母さん〜 苦悩編
<概要>
高校に入って、治療法のない難病にかかり、授業も休みがちで成績は落ちこぼれ。それでも、ボクの宇宙人母さんは見放さなかった。母さんに励まされ、高校の支援はゼロだったけれど、有名なビジネスプラングランプリで優勝した。そのアイデアを実現しようと、今、ボクは米国ノースカロライナ州の大学に留学中だ。
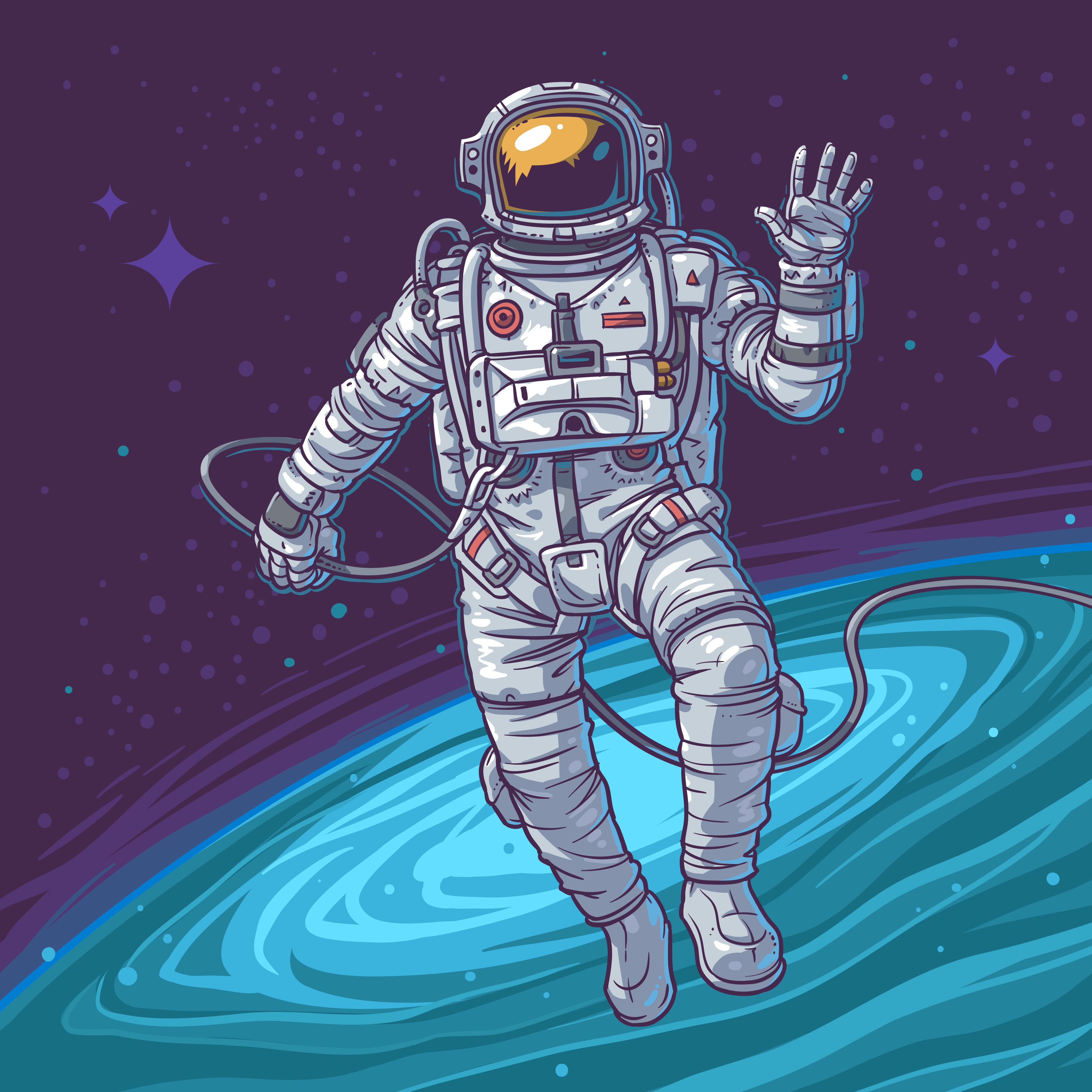
ボクの宇宙人母さんのイメージ。
いつもなにやら楽しげだけど、頭の中では、何をかんがえているのか、ちんぷんかんぷん。
1)治療法のない病気にかかってしまったボク
★ ★「魔の”X Day”」がやってきた!
ある日。突然、なんの前触れもなく、ボクにとっての「魔の”X Day”」がやってきた。
高校2年の夏休みが始まって間もなくのある日。いつものように部活へ行こうと駅へ向かっている最中、足首をケガしてしまった。
「これなら、大したことがないな」と、そのまま学校へ行き、いつものように軽く流していた。ただ、ケガをしたのが、足首ということもあり、念のため、近くの接骨院で治療をしてもらった。
ところが、2日後の夜中。突然、異常な足の痛みで目がさめる。
「なんで、急にこんなに痛むんだよ」
足首に手を当てると、パンパンに腫れ上がり、しかも熱い! 小さい頃から痛みは慣れ親しんできていたけど、こんな痛みは一度も経験したことがなかった。我慢の限界だ。
痛む足を引きずりながら、親の寝室の扉を開いたと同時に、叫んだ。
「母さん、起きて! 足が、おかしいんだよ。これまで、こんな痛くなったことない。救急病院、連れてって!」
「とにかく、一旦冷やそう」と、大急ぎで氷水の袋を患部にあててくれた。その後、これまでお世話になってきた大きな病院に、手当たり次第次々と電話をかける。
しかし、30分たっても病院は見つからず、結局、朝まで待つことにした。
親は、病院へ行く支度を整えた後、朝まで寝る。
一方のボクは、時々襲ってくる激痛で眠れない。「一体全体どーしたんだ、ボクの足」——だんだんと、全身が熱くなってきたように感じる。あと、3時間もこの痛みに耐えられるのだろうか?
8:00、ようやく、見つけた横浜中央病院へと車を走らせる。
休日だというのに、病院は長蛇の列。
忙しいながらも、ボクの痛みを察した看護婦さんが、車椅子を用意してくれた。
初めての車椅子—。
時々襲ってくる激痛に耐えるためには楽だが、みんなの目線が集まり恥ずかしくてしょうがない。★★「足のかかとの骨の中に穴が空いています」
検査を終え、診察を待つ間に、何度も「足が取れ落ちたか」と、思うほどの激痛に襲われ、自分の足がついていることを、その度に確認する。
ようやく、名前が呼ばれ、診察室に入り、椅子に座った次の瞬間だった。
「足のかかとの骨の中に穴が空いています」と、画面を見ながら困ったような医師の声が耳に飛び込んできた。
そして、医師から詳しい話が始まった。
「恐らく、怪我をした時の衝撃かなにかで、この穴に痛みが伝わってしまったのでしょう。残念ながら、ここの病院では、専門医も機材もないので、治療ができません。1日も早く、大学病院へ行き、適切な治療を受けられることをお勧めします」と、親切に教えてくれた。
マジでいってるの? 足の骨に穴が空いている?
そんな話、聞いたことがないよ。
一方の親は、持ってきたパソコン(なんで、持ってきているの???)を開き、近隣の大学病院を次々と調べては電話をしている。
ところが、どこも「担当医師がいないため、よくわからない」と、断られてしまう。
しばらくしてから、「しょうがない。とにかく、一旦、うちに帰ろう。こうなったら東京女子医大にお願いをしよう!」と、そこでも受け入れてもらえるかどうかわからないのに、妙に自信たっぷりに話す親。
改めて、診察室に戻り担当医にその旨を伝え、必要書類の準備をしてもらう。
会計を終え、足早に車に戻る親の後姿をみながら、相変わらずの冷静さぶりに感心する。
いったい、何でパニックになったり、感情が高ぶったりしないんだろう?
しかも、車に乗ったら、すぐに、パンと水を差し出す用意周到ぶり。一体全体、なんだってそんなに冷静で緻密に動くことができるんだろう。もしかしたら、ロボットなんじゃないか?
その夜は、薬のおかげで、朝までぐっすり眠れたボク。久しぶりに痛みを感じることなく、気分もさわやかな朝を迎えることができた。
★★来る日も、来る日も、「検査、結果」、「検査、結果」
翌朝、東京女子医大の受付で名前を伝えると、診察の前に、MRIをとってくるように言われる。「MRIって、なに? 昨日、CTとったばっかりだよ。また、電気を体にあてるの?」と、親の言う通り、
どうやら「人生初体験」の幕が開けたらしいことを悟った。
それにしても、奇妙な装置。音がうるさくて、頭にガンガン響く!
ずいぶん長い時間待たされて、ようやく診察が始まった。
優しそうな女医と対面したボクは、「えっ女医さん?」と、お世話になる人に対して、本当に失礼だが驚いてしまった。
東京女子医大なんだから、当たり前なのかもしれないが、これまで小児科以外で女医を見たことがなかったボクは、驚きを隠せなかった。
さらに、問題の箇所の説明が始まると、
「穴は、問題ではないですね。それよりも、ここに気になる影があるんです。もしかしたら、腫瘍かもしれないので、念のため検査をしましょう」と、その言葉を聞いた瞬間、思わず絶句する。
腫瘍???それって、ガンってこと???
そしてこれが、検査漬けの幕開けとなった。
来る日も、来る日も、「検査、結果」、「検査、結果」。
いったい、いつになったら原因がわかるんだろう。
症状は一向に良くならず、原因も特定できない。
足への負担を軽減するための松葉杖生活だが、1ヶ月を過ぎた頃から、足の感覚もなくなり、腰まで痛みが走るようになる。そして、ついに歩くことすら難しくなっていった。
腰の痛みを取り除くために、リハビリを取り入れることになった。
そうしているうちに、一人で、ベットから起き上がることもできなくなり、薬の効き目も徐々に短くなり、痛みとの戦いは夜中まで続くようになった。
悪夢で、何度も寝汗をかいては、目覚めるという回数も増えていった。
闇夜の中を彷徨い続ける、ボク。
いったい、この先どうなるんだろう。
もしかしたら、大学病院って、病気を治すところじゃないのかもしれない。
ただ単に、人間をモルモットのように研究に使う場所なんじゃないか?
「人体実験場」、何かの本で読んだ言葉が何度も頭の中で点滅している。
★★この激痛と、この先、一生涯つき合っていくしかない???
そんな疑問を持ち始めたある日。
医師から、「反射性交感神経性ジストロフィーという症状です。
しかし、現在の医学ではこれという治療法がない」という痛烈な一撃をくらう。
さらに、今年(当時)の難病認定リストに入る可能性が高い病気の一つだと、ありがたいお言葉が続く。
「今、なんて言った? 治療法がないって、どういうこと? 難病予定って、なんだし?」
ことの発端は、ただのケガ。「なんだって、そんな病気になるの。どうやったら治るの?」
この激痛と、この先、一生涯つき合っていくしかないって、いうこと?
それが、医者の決断?これまで、いろんな検査をしてきた結果?
あのさ、この痛み、知っててそんなこと、平気な顔して言っているわけ?
先生って、専門家だよね?
その専門医が病気治せなかったら、誰が治せるんですか?
もっと真面目に勉強しろよ!
すげー、優しくて説明もわかりやすくて良い先生だけど、その時のボクは、この先生に、たくさんの罵声を浴びせたくなっていた。
口にしたい言葉が、次々と浮かんでは消え、また次の言葉が浮かぶ。
自分でも恐ろしいくらいに、罵声をいう自分が目の前にいるかのように感じた。
でも、ボクの口からでてきたのは、ごく普通の言葉だったー
「何か、方法はないんですか?」
「残念ながら、今はないの」——悔しさと冷静さの入り乱れた先生に、ボクは返す言葉が思い浮かばなかった。2)宇宙人母の提案は、いつも「突然」で「想定外」
「反射性交感神経性ジストロフィー」・・・治療法がない難病。
ボクは、この難病と戦って一生を終わるのか・・・真っ暗な闇に誘い込まれ、絶望の淵に立たされた。
★★「局部注射」のあとは「ブロック注射」
「成長期のアプローチが、最も難しいとは思います。薬も人との相性があるので、とりあえず、この薬を飲んで様子を診ていきます。効果がなかったら、また他の薬に変えていきます。例えば、局部注射やブロック注射、手術という手段もあります。ただし、まだ、国内の事例が少ないのでリスクもあります」と、気持ちを切り替えて冷静に説明をする医師。
「少し、様子をみさせてください。できる限り、体に負担のないような治療をお願いします」と、相変わらずトーンを抑えた口調の親の返事。
「えっ、今、母さん何て言ったの?成長期だからこそ、さっさと手術して治してもらった方がいいんじゃないの?」
あんたたち、二人とも変だし。
ボクの体の痛みは、どうでもいいわけ?
自分の体が少しでもいたかったら、ぜーったいに、「ギャーギャー」わめくはずだし。
「他人のことだからさ、そんなのんきなこと言ってんだろ!」
ボクの予想通り、1ヶ月たっても一向によくならず、巨大な迷路に入ってしまった。
「思った通りだよな。のんきなこと言ってないで、早く良くなる治療始めてほしい!」
というオーラをプンプンに発散して、定期診断を受ける。
初めの治療は、「局部注射」を打つこと。
大人の男の人でもその痛みに耐えられず泣く人も多いという説明をする医師。
ボクの激痛よりも痛い注射なんてないよ。と、心の中では思っていた。
案の定、体に“ずきんと重たい痛み”が走っただけだった。ほらね。
そして、残念ながら一向によくならなかった。
続いての提案は、「ブロック注射」を打つこと。
「この注射には同意書が必要です」と、手渡された同意書を読むと『研究目的』の治療だということを知り、愕然とする。
ボク、やっぱりネズミやモルモットと同じなんだ。
だんだん、人間とかけ離れていくように感じ始め、虚しさが漂ってきた。このころになると、本当に医者の言うことが信じられなくなり、「この注射をすれば、本当によくなるのか?」という強い疑問を感じ始めていた。
果たして、このブロック注射は、どの程度の効力を発揮してくれるのだろう。
そして、翌朝、ついに一人で、ベットから起き上がることができなくなってしまった。
予想通りの
『さ・い・あ・く・な、結果』だよ。
どんなに優れている医者でも、病気を治すことができない病があるということを、自分の健康と引き換えに知ることになる。たとえ確率が小さくても期待していた分、その落差は大きい。
自然と、目から涙がこぼれ落ちた。泣いている姿だけは、親に見られたくない。ベッドの中で、眠っているように、頭っから布団をかけて泣き続けた。
——くやしい。
——何なんだよ。
——どうなるんだよ。
「病は気からかぁ・・・」と、蚊のなくように小さな声だったが、ベットサイドに座っていた親のつぶやきを、ボクは聞き逃さなかった。
著者のKeita Kawasakiさんに人生相談を申込む
著者のKeita Kawasakiさんにメッセージを送る
著者の方だけが読めます


 LINE
LINE































