「うなぎパイ」の春華堂が、和栗の価値を国内外に伝える「掛川栗プロジェクト(仮称)」を立ち上げた理由
静岡県のお土産と言えば、うなぎパイを一番に挙げる人も多いだろう。うなぎパイを製造・販売する春華堂が、静岡県掛川市産の栗の魅力を国内外へ発信しようと「掛川栗プロジェクト」を立ち上げた。なぜ、春華堂がやるのか。春華堂の狙いは何か。地域への貢献か、あるいは新たなヒット商品の開発か。まだほとんど公開情報のないこのプロジェクトについて、春華堂の常務取締役の間宮純也と、広報室の髙山慎吾に話を聞いた。
ジレンマを抱えながら辿り着いた、地元に恩返しをしたいという思い
春華堂の歴史は、1887年(明治20年)までさかのぼる。創業者である山崎芳蔵が、浜松で「甘納豆」を売り始めたのがはじまりだ。浜松の寺院でお歳暮として配られていた「浜納豆」をヒントに、芳蔵は春華堂の「甘納豆」を生み出したという。「甘納豆」は浜松土産として根付く商品へと成長していった。

(甘納豆の看板と春華堂創業者・山崎芳蔵 )
その後、芳蔵の息子の幸一が2代目となる。幸一は、日本固有の鶏「ちゃぼ」の卵に見立てた和菓子「知也保(ちゃぼ)」を考案。同商品は全国でも珍しい菓子の実用新案を受け、全国菓子協会長賞などを受賞した。この商品のヒットを経て、1949年(昭和24年)に「有限会社春華堂」が設立された。
「甘納豆」「知也保」という看板商品がすでにあったものの、幸一はそれを超える浜松ならではの菓子を作りたいと日々模索していたという。
そんな中、旅先での会話が新たな菓子のヒントになった。旅先の方に「どこからきたか?」と聞かれた幸一は「浜松」と応えるが伝わらず「浜名湖の近く」と補足すると「うなぎが美味しい場所ですね」と相手に伝わった。この何気ない会話の中から幸一は、「浜松といえば、うなぎなんだ。うなぎがテーマの浜松らしいお菓子をつくろう」と納得して、早速職人たちと試作をはじめた。
そして誕生したのが、「うなぎパイ」だった。浜名湖の「うなぎ」と、当時まだ珍しかったフランス菓子の「パルミエ」を組み合わせるという斬新なアイデアに、世間は驚いた。さらに、東海道新幹線が開通したことで、浜松へのアクセスが格段としやすくなり、浜松の手土産としてまたたく間に大ヒット商品となった。そして現在に至るまで、「うなぎパイ」は春華堂にとって売上を支える大黒柱のような存在でありつづけている。
「ですが、それこそが春華堂の課題でもありました。『うなぎパイ』という強力なブランドがあるゆえ、次のブランドが育たないという課題を抱えてしまったのです。老舗企業だからこその安定感と保守的思考が、新しいイノベーションを生まれにくくさせていました」(間宮)

(缶入りだった頃のうなぎパイ)

(うなぎパイは年間約8,000万本製造されている)
さらに、浜松の土産菓子を販売しているにも関わらず、地域の住民や他の企業と関わることが少ないという事実についても、現社長の山崎貴裕は気がかりであった。浜松という地に育ててもらったからこそ、恩返しがしたい。そのためには、まず地元の人々に春華堂の商品を楽しんでもらうことが重要だと行き着いたという。
「自分たちが実際に足を運んだ生産者さんと契約させていただいたり、地元のものを使った商品開発を積極的に行ったりするようになりました。『地元の皆さまに喜んでもらえる菓子作りがしたい』という思いが、社内でより一層強くなっていきましたね」(髙山)
4代目社長のもとで進める「地域重視」の事業戦略
春華堂は和菓子と洋菓子の部門を擁する企業として成長を続けているが、「春華堂」という屋号はこれまでも、これからも浜松から外には出さないという意志を持っている。
ここ数年は4代目社長の山崎貴裕のもとで、「うなぎパイ」に次ぐ柱を創るべく事業開発を続けている。それは新しい菓子の開発にとどまらない。たとえば地域性のある食材の発掘、レストランや他企業との価値共創を通じて浜松市や静岡県といった都市の魅力、地域の魅力を発信すること。そして地域に住む子供たちに「地元を学ぶ」機会を作ること。
和菓子洋菓子問わず生菓子は、日持ちがしないので流通に乗りにくいという構造的な課題もあるが、だからこそ地元の顧客を重視している。
世界の栗市場の成長と、日本の栗市場の衰退。そして春華堂は掛川の栗と出会った
春華堂は地元の食材を使った商品開発を続けていたが、「うなぎパイ」に続くヒット商品を生み出すのはそう簡単ではなかった。
「『うなぎパイ』はユニークさを売りにしたブランドイメージが強いため、おしゃれ路線の新商品を発売すると、良い意味でも悪い意味でもギャップが生じてしまう。今まで築き上げたイメージを払拭するのか、それとも継承していくのか、いろんなことが手探り状態でした」(髙山)
そんな中、春華堂が出会ったのが掛川の栗だった。静岡県経済農業協同組合連合会から、「栗の需要が高まっているにもかかわらず、生産が落ちている掛川の栗を助けて欲しい」と、相談を受けたのがきっかけだ。静岡県西部に位置する掛川市は、県内でも有数の栗の産地。しかし掛川の栗の生産量は2004年をピークに、全盛期の約5分の1まで減り続けていた。その主な理由は、栗を流通させる難しさと後継者不足にあるという。



(掛川産の栗)
「栗は焼いたり、加工したりしないと食べられないので、近くに加工場がないと栗農家は安定した収入が得にくい状況にあります。そのため、今までは卸先にまとめて出荷するのが一般的ですが、そうすると価格が均一化されてしまい、豊作の年は逆に安く買い叩かれてしまいます」(間宮)
そもそも、世界で流通する栗には大きく分けて日本の和栗、チュウゴクグリ、ヨーロッパグリ、アメリカグリの4種類がある。モンブラン、マロングラッセなどの洋菓子の流行で栗の需要は高まる一方、日本の和栗市場は衰退していた。さらに、和栗は産地で分けられることはあっても、品種では区別されずブランド化しにくいのが現状だった。
「日本の栗は選別の基準が多く設定されていて、出荷するまでにそれらをクリアしていく必要があります。つまり、出回る栗は品質がかなり高いということなのですが、ブランディングがなかなか追い付いていませんでした」(間宮)
安定した収入につなげることの難しさにくわえ、栗の収穫作業は機械化しにくいというデメリットもある。さまざまな理由から、後継者が離れていくのも自明だった。間宮は和栗の現状を知るにつれて、掛川だけではなく、同じ問題を抱えている地域が国内に多くあることに気づいたという。
「今まで他の地域の栗農家同士が交流することは、あまりなかったそうです。自分たちが掛川の栗を盛り上げることで、他の地域ともつながりながら勉強会などができたら、日本の和栗の価値を上げていけるのではと考えました。せっかく同じような課題を持っているのだから、争うのではなく、共に生きる。品質の高い和栗を守るため、共生していくのが理想だと思いました」(間宮)
「掛川栗プロジェクト(仮称)」立ち上げの経緯、日本航空やヤマハ発動機などが参画する理由とは
そしてスタートしたのが、静岡県掛川市の栗を世界へ発信しようという「掛川栗プロジェクト」だった。掛川市の栗を後世に残したい。だが、文化は一度なくなると再興が難しい。その前に手を打つため、目先の利益よりも地域の魅力を掘り起こそうと立ち上げた取り組みだ。春華堂が声を掛けた結果、JAや地元百貨店、金融機関、日本航空など7団体がプロジェクトに参画することとなった。
「地方企業として、どうやって生き残っていくのか。その問題は、首都圏主要都市よりも大きくのしかかってきます。たとえば『うなぎパイ』はEC販売をしていないので、わざわざ現地に来てもらうことでしか購入につながりません。外からお客さまを呼ぶためには、観光業とも連携しながら、地域自体に魅力を感じてもらう取り組みが必要です」(髙山)
地域の産業の衰退に対して危機感を持っている企業が多いことを、常務取締役の間宮は日々の付き合いから知っていた。協業するのであれば、長いスパンで大きな成果をあげたい。2社間の協業はどちらかが諦めた時点で終わってしまうので、なるべく多くの企業や団体との協業を進めようと決めた。

(各社が集う勉強会にて)
そのためには、地域との密接な関わりが非常に重要である。各企業、地域に根づいてさまざまなアクションを起こしているが、それ自体は点としての活動であり内外的に周知されていないのも事実だった。
「今までの事業だけをやっていたら関わることのなかった企業と、このプロジェクトをきっかけにつながることができました。さまざまな企業が、地元の課題に取り組むことで、もっといろんな角度でイノベーションが起こったり、考えもしなかった可能性が生まれたり、これを軸にいろいろな取り組みができるのではと考えています」(間宮)
参入企業がそれぞれの強みを生かしながら掛川の栗を発信することで、まずは地元の人々に掛川の栗の素晴らしさを知ってもらいたいというのが目下の目標だ。プロジェクトの第一声をあげたのは春華堂だったが、あくまでも各企業とは横並びの意識で一緒に取り組んでいきたいという。
「『掛川の栗を通して地元の魅力を知り、そこに住む人が自分たちの地元を誇らしく思えたらいいよね』という形で始まったこのプロジェクト。参画した地元企業のメンバー全員が、同じ意識で一緒に作り上げていけたらと思っています」(髙山)
世界で勝負できる素材「掛川の和栗」が、ここから再出発する
今年の秋、掛川の栗を日本航空、ヤマハ発動機、遠鉄百貨店などのプロジェクト参加企業のメンバーでさっそく収穫した。10月には春華堂をはじめ、同じメンバーが集まり、収穫した栗の試食会を実施した。






(2022年10月の試食会にて)
なぜ、試食会なのだろうか。間宮によると、プロジェクトとして最初に行うべきことは、まず全員で生産者の現状を聞き、収穫を通して共に汗をかき、同じ釜の飯を食べることだという。体験を通して、全員が同じビジョンを共有することが、継続のための強い絆になる。

(試食会の間宮)
22年10月の試食会では、和栗の品種の食べ比べ、掛川の栗を用いた料理やお菓子が提供された。
「試食会では一般的な栗料理以外にも、茶碗蒸し、フィナンシェなども提供され、和栗の可能性を知る機会となりました。これをきっかけに、いろんな角度から可能性を探っています」(髙山)
ただ、栗は季節物のためいつでも手に入るわけではない。来年の収穫時期まで待つと時間が空いてしまうので、国内の和栗を取り寄せられるよう積極的に動いているそうだ。この希少性をどう上手く活用していくかも今後の鍵となるだろう。

(2022年9月の「収穫祭」にて)
「一方で栗は他の果物に比べて、イガで実が守られているため傷みにくいというメリットがあります。新しく農業を始めるにしては、リスクが少ない作物とも言われているようです。生産者が安定的な収入を得られるように、栗の需要を上げて特産地として復活させたいですね」(間宮)
まずは、春華堂が掛川の栗を使った商品を作ることで、遠鉄百貨店などで販売をめざす。さらには、日本航空の飛行機に開発した商品を乗せて、乗客らにアピールしていけたらという。引き続き、プロジェクトでは掛川の栗についての勉強会などを行いながら、年明けにはフォーラム形式で今後のより詳細なビジョンを発表する予定だ。
「地元の企業が連合しながら、地域活性化を図っていることを伝えていきたいです。面白いことをやっている企業があることを地元の子どもたちに知ってもらえると、今後何十年先も永く愛してもらえる会社になれるのかなと思います。まずは5年後10年後に向けて、『掛川栗プロジェクト』を進めていくことで、新たなる可能性が生まれるのを期待したいです」(間宮)
地元で掛川の栗のおいしさを知ってもらう。そこから徐々に国内での認知も広げていき、掛川の名産品として栗の存在を明確なものにしていく。そしてゆくゆくは、海外に向けて品質の高い日本の和栗を発信していきたい。これから長期にわたって「掛川栗プロジェクト」は進んでいく。挑戦は始まったばかりだ。

行動者ストーリー詳細へ
PR TIMES STORYトップへ
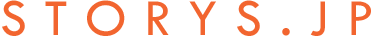
 LINE
LINE
