グローバル刃物メーカー貝印のこだわりを凝縮した『関孫六』 新製品『要』の開発までに込められた“ものづくり”に対する思いとは The Story of 要(かなめ)ーーー関孫六 マスターライン 第二章

国内家庭用包丁シェアNo.1ブランド※『関孫六』からこの秋、新たに発表された『関孫六 要』。その誕生にまつわるストーリーを、製品が完成するまでの期間と、完成後の様子を4つのフェーズに分け、各々について、このプロジェクトに深く関わってきた、商品企画部、デザイン部、開発部の各担当が時系列で語ります。
貝印の“ものづくり”に携わる各々の存在と役割、製品ができるまでには、どんなストーリーや苦労、想いがあったのでしょうか?
※自社調べ
調査期間:2021年1月-2021年12月まで 国内家庭用包丁売上金額において
「関孫六 要」リリース:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000394.000025105.html
語っていただくのは、『要』の“要”とも言える、この三方。

第二章 ――― 通過点〜生みの苦しみ
デザイン・仕様を考える(2020年12月〜2021年6月)
―――第一章では、『関孫六 要』の誕生の理由である、企画・構想について語っていただきました。プロジェクトはその後、デザイン・仕様を決めるフェーズへと進むわけですが、『関孫六 要』に課された、難題ともいえる、“らしさ”を表現するにあたり、さまざまな苦労があったかと思います。『関孫六 要』のデザインやコンセプトはどのように発想されたのでしょうか?
大塚
企画段階から、「こういう包丁をつくりたい」という話は聞いていましたので、イメージは先にふくらませていました。日本刀をベースにするという考えは最初からあったんですが、初期デザインでは、包丁“全体”の形というよりは、“ディテール”にこだわっていました。ハンドルや口金など、各部分に日本刀の要素を盛り込み、日本刀らしさ、日本らしさを表現しようと考えました。

大塚
第一段階では、“現代的なインダストリアルデザインの手法”というか、カミソリや美粧、キッチン製品のような造形処理によって新しさを出そうとしていたのですが、上長に差し戻されました…。
コンセプトの方向性や考え方のディスカッションを何度か繰り返した後、もう少し深掘りしてみようと、刀のミュージアムに行ったり、文献を読み込んでみたり、刀についてさらに勉強したんです。それで、次の段階では、刀の細かい要素に踏み込んでみました。刀の巾木(真鍮製)のディテールを持ってきたり、柄(ハンドル)の部分に、建築の技法にも使われる木材の表面加工である「名栗」のパターン(木の表面をラフに削り取る日本古来の技法)を引用したりしました。ほかにも、“紫”を差し色に使ったデザインで、“雅”な日本をイメージしたり…、いろんなことを試してみました。
―――試行錯誤されたようですが、デザインにはどのくらいの期間をかけているのですか?
大塚
ここまでで1ヶ月くらいですね。イメージスケッチはだいたい1〜2ヶ月でぎゅっとつめています。この段階では、ちょうど半分くらいまで来たところでしょうか。包丁のディテールに、“日本古来の◯◯”みたいなストーリーをいかにして盛り込むか、ということにこだわっていました。でも、それは少し違っていました。
―――それは、なぜでしょう?…必然性がないとか?
大塚
それもあるとは思いますが…、実のところ、他社メーカー各社から「和包丁」のブランドがたくさん出てきたこともあって、それらとの“差別化”ができていなかったんだと思います。正直、“オリジナリティ”がないというか…。
―――表面的だと?
大塚
そうですね。それで、この時期はさらに思い悩んでしまって、アイデアの方向性が“迷走”していた感もあります(笑)。
―――(イメージスケッチを見ながら…)かなり“洋風”なデザインもありますね。
大塚
はい(笑)。もう、いろいろなデザインを 考え、モデルをつくり、ああでもない、こうでもない…と繰り返していました。
―――飽和状態になってしまいそうですね。
大塚
実はそんな中、伊勢神宮を訪れる機会があったんです。岐阜にある勤務地からクルマで2時間くらいと近いこともあって、たまたま訪れたのですが、そこで目にした鳥居や、建築物の中にある“反った”ラインと“静謐な”感じがすごく印象的で、「これかな…」と感じたんです。それで、この“反り”形状に行き着くことができたんです。その他の要素はさておき、この“反り”を、このブランドの“造形言語”として集約しようと考えたんです。これには、上長もOKを出してくれました。

―――伊勢神宮との運命的な出会いだったわけですね!
大塚
そうかもしれないですね。それまでずっとこだわっていた“部分(ディテール)”ではなく、“全体”にひとつ通っている要素(=精神)こそが、日本的だと、伊勢神宮で感じたんです。それまでずっと、ディテールにこだわり続け、“構成的”になっていた思考をいったん止めて、考え方を変えたことがよかったのかもしれません。この“反り”形状を『関孫六 要』の“造形言語”と決めてからは、ブレることなく、試作品をつくりながら、デザインや形状を細かく詰めていく作業に集中しました。
―――進むべき道が見つかった、という感じですね。では続いて、“仕様”についてお聞きしたいと思います。それぞれどのように進められたのでしょうか?
丸山
まず、刃体の鋼材は、開発とも相談して、既存の『関孫六』で使用している鋼材の中でも最高位となる鋼材を採用することが決まっていました。
―――それは、どのような特性を持った鋼材なんでしょうか?
百瀬
鋼材としての“くくり”は「刃物鋼」です。特殊溶解法により、成分の均一化と炭化物の微細分散化を実現することで、優れた耐食性、耐摩耗性、研削性、加工性を得た、ステンレス刃物鋼の超高級鋼種です。
丸山
正確に言うと、最高峰の既存の鋼材を芯材に、側材には芯材より柔らかいステンレスを使用した三層鋼※を採用することにしていました。もちろん、検討段階では、それ以外にも適した鋼材はないかどうか開発には相談していました。
※三層鋼…サンドイッチのように刃の部分を両側から挟み込み、貼り合わせたもの。クラッド(CLAD)鋼とも呼ばれる。
大塚
実は、プロジェクトの初期段階で、企画からは、「コンポジットブレード(コンポジット技法による刃体)」という要望もありました。
―――「コンポジット」とはなんですか?
丸山
「コンポジット」とは“ろう付け”の一種で、貝印独自の接合技術になります。高価な鋼材を効率的に使用できるため、コストダウン、商品価格を下げる技術なんです。しかし、この『関孫六 要』で想定したターゲットはそもそも、道具にこだわりを持つ人であり、“研ぎ直し”をしながら、長く愛用していただけることを前提にしています。そのため、「コンポジット」では不向きだということで、やめたんです。
―――なるほど。ちなみに、三層構造ではなく、既存の鋼材の単層構造にするとどうなるんでしょうか?
百瀬
そうですね。三層ではなく、単層でつくった場合、まず、商品単価に大きく影響を与えます。
丸山
そして、単層にすると“硬くなり過ぎる”ので、研ぎ直しがしにくくなります。そのため、三層にすることで、コストを抑えつつ、研ぎ直しにも対応できるようにしたんです。
―――なるほど。理にかなっていますね。刃体についてはよくわかりました。それでは柄(ハンドル)についても教えていただけますか。
大塚
商品企画部からの要望で、色は“黒”がいいと言われていました。ターゲットが男性であるということもあって、黒の“八角形”にしたいというのが当初からのリクエストでした。四角いハンドルって、握った時に方向がつかみやすいのですが、その四隅を切り落とし、握りやすい形にしたのが八角なので、最小限且つ必然的な形だと言えると思います。しかもこれは、単純な八角形ではなく、下に向かってテーパー状になっているんです。ここは三次元的な形状の捉え方と加工方法を駆使した、繊細ではありますが進化させた部分です。
―――確かに。現代的なアレンジですね。
大塚
そうなんです。じっくり見ていただくとわかるのですが、シンプルに見えて、意外と複雑な形状になっているんです。

百瀬
口金部分は、MIM(メタルインジェクションモールディング:射出成形法)といって、金属を型に流して成形する製法を採用することにしました。
―――それは、金型鋳造のようなものですか?
百瀬
そうですね。技術分類としては異なりますが、金型を使用する意味ではダイカストにイメージが近いですね。金型に金属粉末とつなぎ(バインダー)を混ぜたもの射出成形し、その後焼結することで高精度な金属部品を作る技術です。他の包丁の口金でも使っている製法です。
―――刃体と口金が一体化していて、すっきりとしたデザインですね。
大塚
はい。当初考えていた日本刀のような口金のデザインはやめたんです。
―――あくまでも“反り”形状が『関孫六 要』の“造形言語”であり、“魅せ場”である以上、そのディテールにこだわりすぎる必要がなくなったということでしょうか。
大塚
そうですね。
丸山
この話、ちょっとこのタイミングで言うのもあれなんですが…、実は、先ほどからたびたび出ている既存鋼材は、不採用になってしまうんです。
―――えっ、そうなんですか?…ということは、全く違う鋼材が採用されたと?
丸山
そうなんです。
―――なぜ?既存の鋼材から変更されることになったのか…、その理由がとても気になるところではありますが、詳しいお話は次回に。
次回へ続く
行動者ストーリー詳細へ
PR TIMES STORYトップへ
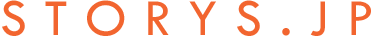
 LINE
LINE
